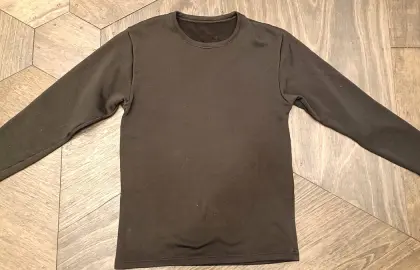特にルアーフィッシングで釣り人から親しまれているシーバスの釣り方のコツを解説します。
- Text
シーバス釣りの魅力・生態
シーバス釣りの魅力は枚挙に暇がありません。
あらゆるポイントやシチュエーションがあり、そのシチュエーションで明確に正解といえる釣り方やルアー選択が存在します。
確実にシーバスが潜んでいると思われるが全く釣れない、反対にこんなところで?と思うようなポイントで釣れまくることもあります。
また、シーバスは最大で1m前後と大型に成長する点でも釣り人を魅了します。
正式名称をスズキといい、各地域や大きさによって呼び名が異なる出世魚ですが、外観がルアーフィッシングの好敵手であるブラックバスに似ていて海で狙えることから、ルアー愛好家の間ではシーバスという呼び名が定着しています。
シーバスの釣り方(基本)
シーバスを釣る手段として多くの釣り人に人気なのが、疑似餌を使用したルアーフィッシングです。
ここではシーバスをルアーで狙う際の基本を紹介します。
ポイント選び
シーバスはおかっぱり(岸に立つ釣り)で釣果をあげやすく、釣り人に人気のターゲットである理由のひとつです。
シーバスは沿岸性が非常に強い魚で、ルアーで狙う際のポイント選びとしては岸沿いのシャロー(浅瀬)が基本となります。
明確に水深の目安があるわけではありませんが、膝下~腰くらいの超シャローで爆釣するようなこともあり、もし釣りに赴こうとしているエリアで水深10mのポイントと水深2mのポイントがあれば、後者を選ぶとよいでしょう。
また、海流や河川の流れによって水が動いている水域を好み、水面に泡や切れた海藻が浮いているような淀んでいるポイントは避けたほうがよいでしょう。
ちなみに東京湾など魚影が濃い(魚の数が多いこと)地域では水深のある海域でも多くのシーバスを釣ることができ、堤防の岸壁などでも釣果をあげやすく、ボートによる釣りも人気があります。
時期、時合

ポイント選びと並んで重要になるのが時期(シーズン)や時合(その日のタイミング)です。
ポイント選び、時期、時合、これがおかっぱりのシーバス釣りで釣果をあげる要素の8割以上を占めていると筆者は感じます。
本州付近において最も釣りやすい時期は、10月から12月初めの頃の晩秋で、シーバスは冬の産卵に備えて体力をつけようと積極的に捕食をします。
狙うべき時合としてはマズメどきは外せません。
マズメとは、日の出もしくは日の入りで周囲の明暗が切り替わるタイミングのことで、魚たちの食事のタイミングとされています。
そんな絶好のタイミングであるマズメどきの真っ最中に釣りをしていられることが、初心者がシーバスの釣果をあげる第一歩といっても過言ではないでしょう。
ルアー選択、ローテーション
初心者の方を最も悩ませることのひとつが、ルアー選択です。
おかっぱりのシャローで釣りをするのであれば、キャスト(ルアーを投げること)したのち、リールを巻くだけで表層をフラフラと泳ぐフローティングタイプのミノーをメインに使うとよいでしょう。
次にルアーのローテーションのコツとしては、まずは表層直下を及ぐフローティングミノー、続いてバイブレーションなどシンキングタイプの潜るルアー、最後に飛距離の出るシンキングペンシル等の順です。
初めに潜るタイプのルアーを使用して根掛かり(海底の障害物にルアーをひっかけること)をしてしまうと、魚に強い警戒心を与えるとともに釣りを中断せざるを得なくなり、場合によっては海中にルアーを残してしまいます。
また、もし複数のシーバスが潜んでいた場合、初めに深場や遠くのシーバスをルアーに反応させて、そのままルアーを追ってきてしまうと他のシーバスに警戒心を与え、そこに居たシーバスを全て散らしてしまう可能性があります。
マズメどき・夜間のルアーアクション

マズメどきや夜間など光量の少ない時間帯では、シーバスにルアーを見せつけることを意識し、基本的にはゆっくりとしたリールのただ巻きが最も釣れます。
リールを巻く速さとしては1秒間にハンドルを1回転くらいを基準とし、ブルブルというルアーが泳ぐ感触がギリギリ伝わってくる程度の速度に調整することを意識するとよいでしょう。
シャローなポイントであれば、海底に潜むシーバスも水面をフラフラと泳ぐルアーを発見することができます。
反面、シンキングタイプのルアーを使用する場合は、リールを巻く速度が遅いと沈んで海底に接触し、根掛かりの原因となってしまいます。
これが、シンキングタイプよりもフローティングタイプがシーバス釣りのメインで使われる理由の一つです。
日中のルアーアクション
光量が多くシーバスにルアーが偽物であると判断されやすい日中では、ルアーをシーバスにあまり見せすぎないようにします。
フローティングミノーを使用する場合は、マズメどきや夜間よりも速くリールを巻くことを意識し、たまに小刻みにロッドを煽るトゥイッチというアクションを入れてみるのもいいでしょう。
また、日中のシーバスは深場に潜んでいることも多く、重みもあり、よく沈むバイブレーションをロッドで小刻みに上下されるリフト&フォールというアクションも有効です。
マズメどきや夜間ではルアーを弱った獲物としてシーバスに捕食させるのに対し、日中は「暴れまわる縄張りの侵入者」としてルアーを攻撃させる使い方を意識するとよいでしょう。
シーバスの釣り方(シチュエーション別)
続いて、シチュエーション別にシーバスを狙うコツやタックルを紹介します。
おかっぱり

最もメジャーなポイントである河口付近をはじめ、干潟、サーフ(砂浜)や堤防、磯に至るまでシーバスは岸沿いのありとあらゆるポイントで狙うことができ、各ポイントに適したタックル(釣り道具)が存在します。
今回は、アクセスや釣りのしやすさから初心者に最もおすすめなポイントであるサーフのシーバス釣りについて紹介します。
シマノ(SHIMANO) サーフロッド ネッサSS
サーフゲームに求められる継続的なキャストを可能にする「曲げるブランクス」コンセプト。基本構造スパイラルX、強化構造ハイパワーXがロッドのネジレやつぶれを抑制。
タックル
シマノ(SHIMANO) ストラディック 4000XG
ボディ:アルミニウム / ローター:高強度樹脂 / ドライブギア:超々ジュラルミン / ベール:ステンレス
広大なサーフで使用するタックルは、キャストの飛距離が出ることが求められます。
ロッドは9.6ft以上の長尺でパワーランクの強いものが遠心力によりキャストの飛距離が出るためおすすめです。
反面、あまり長すぎたり強いロッドはキャストを続ける上で体力が要り、ルアーを細かく動かす動作もやりづらくなってしまいます。
シーバスが回遊してくるのを待つ時間が大半を占めるサーフでは、自身の体力とも相談し長時間釣りを続けられるタックル選びが大事になります。
リールは長尺のロッドに合わせた際に、バランスの良い重量になる4000番クラスがおすすめです。
ルアー
メガバス(Megabass) カゲロウ 124f
Length:124mm Weight:22g Type:Floating Hook:#4 x 3
シマノ(SHIMANO) トライデント 130S ジェットブースト
レンジは水面直下の激浅系。バチパターンからイカ、ベイトパターンまで対応する、今までになかった驚異の飛距離の激浅シンキングペンシル。
サーフは水深があまりない場合が多く、水面直下をじっくり泳がすことができるフローティングミノーをメインに使用するとよいでしょう。
サーフでは飛距離が重要になるため、ルアー内部のオモリが前後に移動することでキャスト時のルアーの弾道を安定させる重心移動機能のついたものが大変おすすめです。
サーフではボイル(獲物を水面で捕食した魚の魚体が飛び出ること)が発生することも多く、ボイルの付近にルアーをキャストできれば高い確率で食いつかせることができます。
ボイル発生場所にミノーでは届かないこともあるため、より飛距離の出るシンキングペンシルやメタルジグもタックルケースに入れておくと良い釣果が得られるかもしれません。
ポイント・シーズナルパターン
シーバスは汽水域を好む性質があるため、広大なサーフの中でも河川の流れ込み付近は大変有望なポイントになります。
また、シーバスなどのルアーフィッシングでは、その季節やタイミングで捕食している獲物(ベイト)が異なり、その獲物のみを狙って捕食する性質に着目したベイトパターンという考え方があります。そのベイトに似た大きさや色、動きを演出できるルアーを使用することが釣果のカギとなります。
春から夏にかけては遡上前の稚鮎やカタクチイワシといった5cmから10cm未満のベイトが多く、秋~冬にかけては15cm以上のコノシロや、産卵を終えて流下してきた大きな鮎などもベイトになります。
ボート

汽水域を好むシーバスの性質から、流入河川の多い都市部の港湾ではボートからのシーバスルアーフィッシングも広く楽しまれています。
特に東京湾は流入河川の多さなども相まって、シーバスの魚影が日本一ともいわれるほど濃いエリアです。そのため、ボートシーバスのメジャースポットとなっています。
回遊を待つことの多いおかっぱりの釣りと違い、次から次へとポイントを巡り、よく釣れる個体を狙っていくため釣果をあげやすいのがボートシーバスです。
また、ボートであればタックルも多く持ち込めたり、レンタルタックルを用意していることもあるため、勝手の分からない初心者にも大変おすすめです。
タックル
ダイワ(DAIWA) ボートシーバスロッド LATEO BS 64MS・W
ノンストレスでルアーを操り、シーバス&アングラーを魅了するロッド
シマノ(SHIMANO) ストラディック 3000MHG
ボディ:アルミニウム / ローター:高強度樹脂 / ドライブギア:超々ジュラルミン / ベール:ステンレス
ボートシーバスでは広い大場所を巡りつつも、堤防の際や橋の橋脚付近などの障害物に潜むシーバスをピンポイントで狙い撃つスタイルも多くなります。船上では大きく振りかぶることができないため取り回しのしやすい長さのロッドを使用しましょう。
リールはロッドの重さに合わせたバランスになる、サーフで使用するものより一回り小さい中型サイズの汎用スピニングリールがおすすめです。
また、シーバスは大型になる魚であることからタックルへの負荷も大きく、中型サイズのリールでは本体の強度が重要になるため、ボディが金属製のタイプがおすすめです。
ルアー
Jackson(ジャクソン) 鉄PANバイブ
プレート部に設けられたスリットにより、単なるプレートだけのものより複雑な水流を発生。スリットはフック絡みしない絶妙な位置に設定。
ダイワ(DAIWA) モアザン ソルトペンシル
「これはエサだ」と称えられる元祖ウォータースルーギル搭載の爆釣ペンシル。
ボートシーバスで使用するルアーは多岐に渡ります。
おかっぱり同様のフローティングミノーはもちろん、水深のある港湾部ではより深く潜るバイブレーションも使用する場面が多くあります。
さらにシーバスが水面のベイトを偏食している場合などは、水中に沈まないルアーであるトップウォーターを使用することもあります。
ボートシーバスはその時の状況やポイントに合わせてルアーを選択し、沈めて使ったりロッド操作で動かしたりと、ルアーフィッシングの醍醐味が詰まった釣りです。
ポイント
ボートシーバスのポイント選定は基本的にはキャプテン任せとなります。
ボートで巡るポイントのシチュエーションは多岐に渡り、河川の流れこみ付近をボートを流しながらおかっぱり同様に広く探る場合や、障害物や地形に潜むシーバスをピンポイントで狙うシチュエーションもあります。
中でもボートシーバスの醍醐味は、障害物などに潜むシーバスを狙い撃つスタイルで、ピンポイントへのキャストが決まり、そこからシーバスが不意に食いついてくるスリルが、釣り人を虜にします。
そのようなポイントでは、キャストの精度が要求されるため、練習を積んでおくとよいでしょう。
ルアー以外の釣り方
続いて、ルアーフィッシング以外でシーバスを狙う釣り方を3つ紹介します。
ルアーフィッシングのターゲットとしてメジャーなシーバスですが、もちろんエサ釣りでも釣ることができます。
ルアーは活き餌を使わないため手軽に始められますが、その分、魚を釣り上げる難易度はやや高めです。
初心者の方がシーバスを手に取りたいのであれば、ルアーに比べて準備や片付けの手間はかかりますが、エサ釣りの方がシーバスの食いつきはよく、釣果は得られやすいでしょう。
また、ルアーフィッシングで使用するシーバスタックルは大変汎用性が高いため、各エサ釣りでもそのまま使用できます。
投げ釣り

投げ釣りは、エサでシーバスを狙う釣りのなかでも比較的手軽な釣り方です。
使用するタックルは本格的な投げ釣りタックルはもちろん、ルアーフィッシングで使うタックルをそのまま流用するちょい投げスタイルでも狙うことができます。
釣り針は丸セイゴ針の1本針を使用し、エサはアオイソメの房掛け(3匹~4匹のエサを1本の針に刺す)やユムシを使用します。もし手に入るようならアジやイワシのような小魚がおすすめです。
釣りのポイントは断然河口がおすすめで、仕掛けを遠投して糸を張らず緩めずくらいのテンション(ゼロテンション)で待つだけの簡単な釣りです。
ウキ釣り

シーバスのウキ釣りは夜間に行うのがメジャーです。
ウキ釣りの仕掛けは投げ釣りに比べて遠投が効きづらいことから、足元付近まで回遊してくる潮通しの良い堤防や護岸整備された河口域がおすすめです。
また、常夜灯の明かりが水面に落ちるような箇所は、シーバスが回遊してくる大変有望なポイントになります。
夜間でも視認できる電気ウキを使用し、針は丸セイゴ針、エサはアオイソメの房掛けやエビがおすすめです。
エビを撒きながらウキ釣りを行う「ハネ釣り」は関西地方でよく親しまれています。(ハネとは小型シーバスの関西地方での呼び名)
泳がせ釣り

アジやイワシなどの餌を活かしておくバッカンやエアポンプが必要なことから少々敷居は高いですが、泳がせ釣りは、シーバスだけでなくあらゆる大型の魚が狙えるため大変ワクワクする釣りでもあります。
活き餌を沈めるためのナスオモリ(8号から10号程度)、釣り針は生き餌の背中に刺すハリと、シーバスの掛かりを良くする孫バリと呼ばれるハリス付きのハリを垂らして使用します。
重たい仕掛けなのでロッドに負荷をかけず、また活き餌が弱らないようにそっとキャストし、ゼロテンションでアタリを待ちます。
モゾモゾと生き餌が嫌がるような感触がしたらチャンスで、その後に大きなアタリがあればアワセ(ロッドを大きく煽り釣り針を刺すこと)を入れます。
ちなみに、シーバスの魚影が濃い地域であればサビキ釣りでかかったイワシやアジを放置しておくと、シーバスが食いつくこともあります。
シーバスは釣り人を魅了する好敵手!
シーバスをルアーで釣るのは、はじめのうちは難しいかもしれません。
しかし、正解となる釣り方が実践できれば意外と簡単に釣ることができ、その答え合わせのような釣りは「ゲーム性が高い」と評され多くの釣り人を魅了します。
あらゆるフィールドで挑めるシーバスのルアーフィッシングに挑戦してみてはいかがでしょうか?