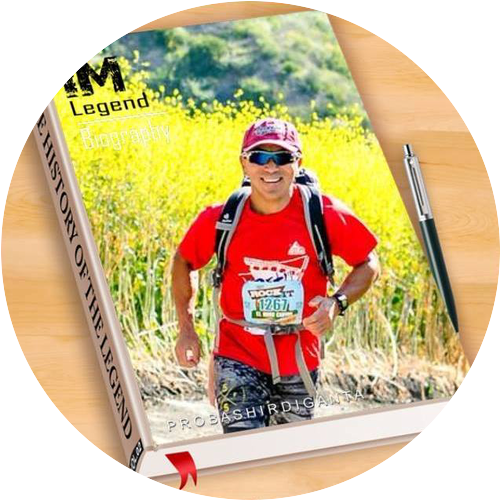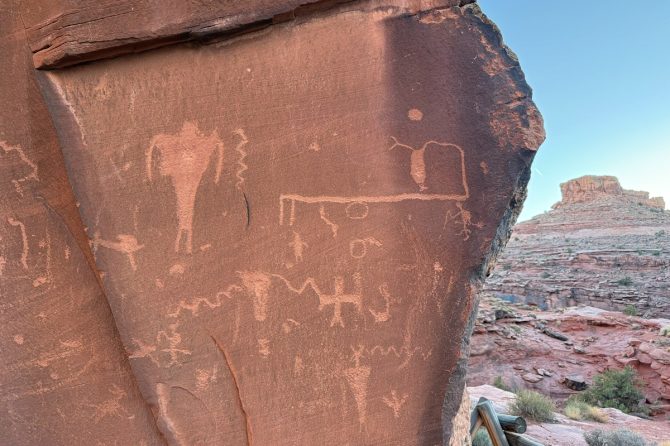ところが、そんな街のシンボル的存在とも言えるヤシの木がロサンゼルス近辺で徐々に数を減らしていることをご存知でしょうか。多くの自治体でヤシの木を別の樹木に植え替える動きが盛んになっているのです。
昨年からロサンゼルスでは日本人観光客が激増しています。言うまでもありませんが、ドジャース観戦ブーム、というより大谷翔平ブームのおかげです。さらに、2026年のFIFAワールドカップ、2027年のNFLスーパーボウル、そして2028年のオリンピックと、これから数年にかけてロサンゼルスには大規模なスポーツ系イベントが連続してやってきます。
日本からの観光客もますます増えることが予想されますが、ひょっとしたら、これまでの「いかにもロサンゼルスらしい」景色に出会う確率はやや減っているかもしれません。
- Text
元々は「外来種」だったヤシの木

そもそもヤシの木はロサンゼルス近辺に自生する植物ではありません。つまり「外来種」なのです。
この辺りの気候は、「地中海性気候」に分類されます。冬に少し雨が降るものの、それ以外の季節は暑く、また非常に乾燥しています。夏になると何ヶ月も雨がまったく降らないこともあります。
自然に植物が生育するにはかなり厳しい環境です。都会から少し離れると、背の高い木をほとんど見なくなります。せいぜい、乾燥に強い低木や灌木、あるいはサボテンが生えているくらいの半砂漠が広がっています。
現在のロサンゼルス近辺にニョキニョキ立っているヤシの木は、そのほとんどが外部から人の手によって持ち込まれ、植えられたものです。つまり、「風に揺れるヤシの木」は、この地域の自然の姿からは大きくかけ離れた、きわめて人工的な景観なのです。

ロサンゼルスにヤシの木が大量に植えられるようになったのは、20世紀前半、とくに1920~30年代のことです。「狂乱の20年代」と呼ばれたこの時期、ロサンゼルスは人口が急増し、「映画の都ハリウッド」として世界中から注目を集めるようになっていました。
市当局は、観光都市としてのイメージづくりの一環として、街の美観を整えるために街路樹を大量に植えることを決定しました。そして選ばれたのが、乾燥に強く、見た目もエキゾチックで印象的なヤシの木だったのです。さらに、1932年ロサンゼルス五輪を前に、市は約4万本ものヤシの木を植えるという一大プロジェクトを実施しました。
ヤシの木の寿命は平均して約80~100年ということで、現在多くの木が寿命を迎えています。枯死や倒木による道路への落下といった安全性は緊急の問題ですが、それ以上にヤシの木の実用性についても別の議論があります。
「見た目は良い。だけど役に立たない」
近年、ロサンゼルス近辺の自治体はヤシの木の「補植」をやめつつあります。つまり、古くなって倒れてしまった、あるいは伐採されたヤシの木を、同じ種類で植え替えることをしないのです。代わりに、より環境に適した「在来種」や「日陰を作れる樹種」を選んで植える方針へと移行しています。
こうした動きは、ロサンゼルスの名門大学USCが主導する「ShadeLA(ロサンゼルスに日陰を増やす)」プロジェクトとも合致しています。2028年のオリンピック開幕までに、街路樹やシェルターなどによる日陰を増やし、市民や観光客を猛暑から守ろうというものです。
ロサンゼルス市、地元鉄道会社、そしてオリンピック実行委員会などの組織がプロジェクトに参加しています。

実際のところ、ヤシの木は見た目こそゴージャスですが、その下には影がほとんどできません。夏場の路面温度を下げる効果はほとんどゼロです。
ヤシの木の代わりに枝葉の広い広葉樹を植えると、通行人に日陰を提供し、ヒートアイランド現象を和らげるのに役立ちます。
気候変動による地球温暖化の問題が深刻化するなか、木陰を増やして涼もうというのは悠長に聞こえなくはありません。しかし、何もしないよりはずっと良いと私は思います。

変わりつつある「ロサンゼルスっぽい」風景
今のところ変化のスピードはごく穏やかなものですが、ロサンゼルスの景観は変わりつつあります。ヤシの木はゆっくりと、しかし確実に減少しています。10年後になるのか、100年後になるのかは分かりませんが、サンタモニカの海沿いやビバリーヒルズの高級住宅地などからヤシの木が完全に姿を消すかもしれません。
この変化を寂しいと感じる人はいるでしょう。それよりは「より持続可能で快適な都市への進化」だとポジティブに捉えたいと個人的には考えています。
これからロサンゼルスを訪ねる人は、そこにあるヤシの木の写真を撮っておくと、将来は貴重な記録になるかもしれませんね。