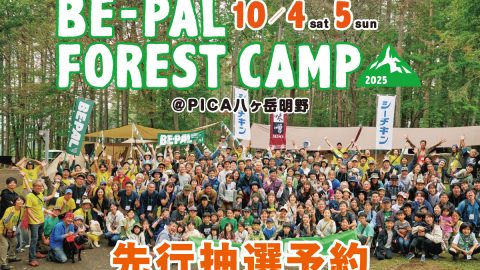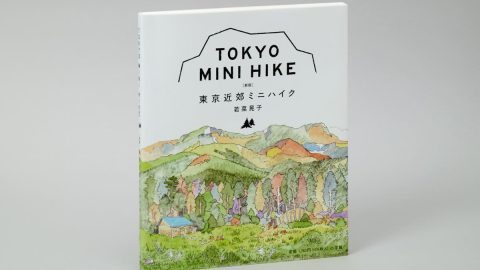その代表格ともいえるのが「マツムシ」と「スズムシ」です。
どちらも風情ある音色で親しまれていますが、実は見た目や鳴き方には大きな違いがあります。
本記事では、マツムシとスズムシの違いや、名前の由来、コオロギとの見分け方までをわかりやすく解説します。
虫の声をもっと楽しむために、ぜひ知っておきたい基礎知識です。
マツムシとスズムシは秋に鳴く虫

マツムシとスズムシは声で鳴いていない?
一見、その音を聞くと、マツムシやスズムシの「声」が聞こえているように感じますが、実際には口で鳴いているわけではありません。
これらの虫は翅(はね)をこすり合わせることで音を出しています。これを摩擦音とも言われる「擦音(さつおん)」と呼び、オスだけがこの音を発します。翅には細かいギザギザがあり、そこをこすることであの独特な音が生まれるのです。その仕組みを知れば知るほど、秋の虫の音がさらに興味深く感じられるはずです。
虫が鳴くのはコミュニケーション
虫たちの鳴き声は、求愛や縄張りを示すための重要な手段です。特にマツムシやスズムシのような秋の虫は、オスがメスにアピールするために独特のリズムで鳴きます。
音の高さやテンポは種によって異なり、それぞれが「自分はこの種類だよ」と知らせるサインになっているのです。周囲に他のオスがいれば、その鳴き声と競い合うようにして、より目立つ存在になろうとする行動も見られます。
マツムシとスズムシの違い
マツムシはスズムシだった
実は、かつてスズムシと呼ばれていたのは現在のマツムシでした。平安時代などの古典文学で登場する「鈴虫」は、今でいうマツムシを指している場合が多いのです。マツムシのやわらかく澄んだ音色は、風流を重んじる時代の人々に好まれていたのでしょう。
また、文学や和歌の中では、繊細で美しい音を奏でる虫としてしばしば登場し、日本文化に深く根付いていることがわかります。
スズムシはマツムシだった
逆に、現在スズムシと呼ばれる虫は、かつて「マツムシ」と混同されていたことがあります。江戸時代以降に鳴き声や形状で区別されるようになり、ようやく名前が整理されてきた背景があります。
このような呼称の変遷も、日本人と虫との深いつながりを感じさせる興味深い話です。名前が時代によって移り変わった例として、自然観察をより奥深いものにしてくれます。
マツムシの見た目と鳴き声

マツムシはやや小型で、淡い褐色の体が一般的ですが、なかには緑がかった褐色~黄褐色の体のものも存在しで、透明感のある翅を持っています。体長はおよそ15〜20mm程度で、翅の縁が丸みを帯びているのが特徴です。
鳴き声は「チンチロリン、チンチロリン」と鐘の音のような澄んだ音色。鳴く時間帯は夕方から夜にかけてで、控えめながらも風情ある響きが特徴です。草むらや林縁など、やや自然が残る場所でよく聞かれます。
スズムシの見た目と鳴き声

スズムシは黒っぽく、ややずんぐりとした体型が特徴です。体長は20mmほどで、長い触角とつやのある黒い体が目を引きます。
鳴き声は「リーン、リーン」と高く鋭い音で、音量も比較的大きめ。こちらもオスだけが鳴き、飼育されている個体は、自然下よりも長時間鳴き続けることが多い傾向があります。環境によって鳴き方に差が出る点も興味深い特徴です。
都市部でも飼育を通じて身近に聞くことができる秋の音色です。スズムシは飼いやすく、昆虫飼育としても人気のある種なのです。
コオロギとの違い

コオロギの見た目
コウロギはマツムシやスズムシに比べて体ががっしりしており、翅が短めの種も多く見られます。色は黒~濃い褐色で、触角が長いのも特徴です。
コオロギの鳴き声
鳴き声は「リリリリ…」「ギーッチョン」など種によってさまざまですが、どれもはっきりとしたリズムがあり、草むらなどで盛んに聞かれます。種類も多く、鳴き声のバリエーションが豊かなので、聞き分けの楽しさも魅力のひとつです。
マツムシとスズムシは秋の風物詩!違いを理解しよう!
マツムシもスズムシも、魅力的な鳴き声を持つ秋の代表的な虫です。古くから日本人に親しまれてきた彼らの音色には、風情や季節感がたっぷり詰まっています。
鳴き声や見た目の違いを知ることで、秋の夜長がより豊かに感じられるはずです。自然のコンサートに耳を傾けながら、それぞれの虫の個性を楽しんでみましょう。自然のコンサートに耳を傾けながら、それぞれの虫の個性を楽しんでみましょう。虫たちの音色は、季節の移ろいを感じる大切なサインとして、私たちの生活に秋の訪れを知らせてくれるのです。