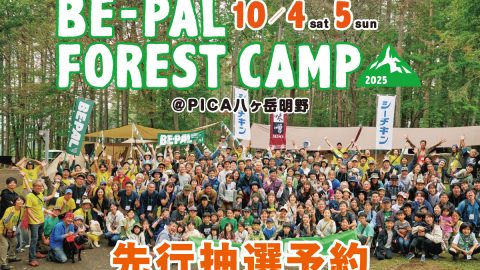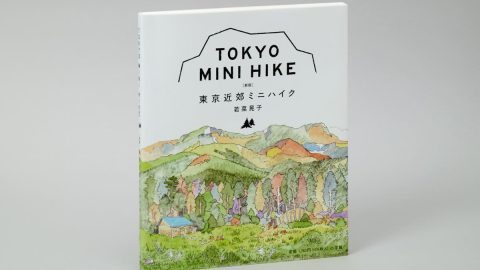(出典)photoAC
ハナムグリってどんな虫?
まずは、ハナムグリがどのような虫なのか、その特徴を見ていきましょう。また、似た種類との判別方法も紹介します。
コガネムシ科の昆虫
ハナムグリは、コガネムシ科に属する昆虫です。コガネムシ科には、カナブンやカブトムシも属しています。
体長は約15〜20mmで、北海道から沖縄まで日本全国で見られます。花の蜜や花粉を求めて日中にも活発に飛び回るため、夜行性が多いコガネムシ科では異色の存在です。
見た目で目を引くのは、緑または黄緑色の前羽です。多くのハナムグリは背面に白い斑点が見られ、この模様が種の目印の一つとなっています。
前羽を開かずに飛ぶのが特徴
ハナムグリの大きな特徴は、前羽を閉じたまま飛ぶ点です。体の側面から後羽を広げ、一般的にイメージされる虫の飛ぶ様子とは異なる飛び方をします。
なぜこのような飛び方をするのか、詳しいことは分かっていません。いくつか仮説は提唱されており、例えばハチに擬態するため、天敵から身を守るためなどの説があります。
前羽を閉じて飛行する虫は他にもいますが、その多くが昼行性で、前羽を開いて飛ぶ虫よりも早く飛ぶといわれています。まだ研究途上であるものの、ハナムグリなりの生存戦略が関係しているのでしょう。
カナブンやコガネムシとの見分け方
似た仲間との判別は、羽の模様や全身のフォルムに注目すると簡単です。他の二者と異なる点は、多くのハナムグリが羽に白い水玉模様があることです。体は、比較的四角形に近い傾向があります。
カナブンは、全体的に四角形に近いフォルムをしており、頭部と羽の境目が逆三角形になっているのが特徴です。
対して、コガネムシの体は丸っこく、光沢があります。羽の付け根は半円型で、体毛はうっすらとありますが、斑点はないのでハナムグリと判別が可能です。
ハナムグリは害虫?それとも益虫?

ハナムグリが来ると、害があるのではないかと気になる人もいるかもしれませんが、害虫ではないので心配はいりません。ここでは、ハナムグリの自然界での役割や、注意すべきコガネムシによる被害を解説します。
ハナムグリは害虫ではない
ハナムグリは、花壇の害虫とは一線を画した『園芸のパートナー』ともいえる存在です。幼虫は腐葉土を食べて育つので、腐葉土の分解が進み、土壌を肥沃にしてくれます。
成虫になると花の蜜を吸って生活しますが、その際に体に付着した花粉を運んでくるので、受粉を助ける役割も果たします。
ハナムグリは植物自体を食べることはなく、人間にとっての害は特にないため、見つけても駆除する必要はありません。
注意すべきはコガネムシ
コガネムシは注意が必要です。コガネムシの成虫は、植物の葉を餌としています。
葉脈を残すように食い荒らすので見た目が悪くなり、ガーデニングが台無しになってしまう可能性があります。
さらに気を付けるべきは、コガネムシの幼虫です。幼虫は植物の根を食べるため、植物がうまく育たなくなり、最悪の場合枯れてしまうでしょう。
幼虫は土の中で冬を越すため、1年を通して被害に注意しなければなりません。もし、土の中で幼虫が大量発生すると、植物が全滅する恐れもあります。
コガネムシを見つけたときの対処法

庭や菜園でコガネムシを見つけたら、どのように対処すればよいのでしょうか。最後に、幼虫と成虫それぞれの対処法を紹介します。
成虫は数匹なら手で捕まえる
成虫を退治する方法は、手で捕まえるか薬剤を使うかの大きく2種類です。数匹であれば、手で捕まえるのが最も簡単です。
コガネムシは、危険を感じると苦味や独特の臭いがある体液を分泌するため、捕まえる際は軍手を装着しましょう。
大量発生して手に負えないときは、薬剤を使うのもおすすめです。地上にいる成虫には、水溶性で葉に吹きかけるタイプが適しています。
成虫が大量発生している場合は、土の中に卵を産み付けている可能性もあるため、土にまく薬剤も使いながら被害を防ぎましょう。
まとめ
ハナムグリはコガネムシの仲間であり、前羽を閉じたまま飛ぶのが特徴です。体にはうっすらと毛が生えており、背面の白い斑点が目印となります。
幼虫は土を肥沃にし、成虫は受粉を助けてくれる、花壇の緑を支える小さな助っ人です。見かけても、そっとしておいてあげましょう。