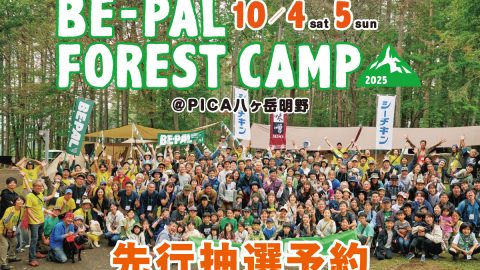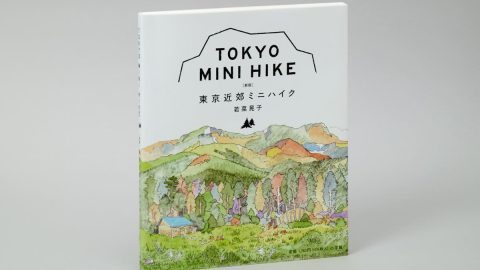(出典)photoAC
キリギリスの食性と向いている餌

まずは、キリギリスがどのようなものを食べて暮らしているかを知りましょう。野生のキリギリスの食性と、飼育時におすすめの餌を解説します。
野生のキリギリスの食性
キリギリスは雑食性で、葉っぱや小さな虫を主に食べます。卵からかえった後しばらくは、花粉や花びら、草などを食べていますが、大きくなるとタンパク質を補うために、アブラムシや他の虫の幼虫なども食べるようになります。
キリギリスは下顎の力が強く、餌に勢いよくかじりつく様子は見ものです。成虫は主に小型の昆虫を捕食しますが、まれにセミやカマキリ、アマガエルなど自分より大きい獲物を捕食するケースもあります。
なお、植物はイネ科やマメ科を好む傾向にあります。
小さな昆虫や野菜類がおすすめ
植物性と動物性の餌をバランスよく与えることが、キリギリスを健康に育てるコツです。野菜はキュウリやナス、ニンジンなど何でも食べます。
特にタマネギが好物で、よく食べてくれます。手に入るなら、クズの葉をあげてもよいでしょう。
動物性のタンパク質を確保するには、削り節や煮干し、ミルワームなどをあげるのがおすすめです。犬を飼っているなら、ドッグフードでも代用できます。面倒でなければ、生きた昆虫を捕まえて与えると喜ぶでしょう。
昆虫ゼリーや魚肉ソーセージも食べるので、いくつか与えてみて食いつきのよい餌を探すのも面白いかもしれません。
キリギリスの飼育方法
キリギリスは自宅で飼育できますが、いくつかの注意点があります。飼育環境のつくり方や虫かごの置く場所、累代飼育をする際の心構えを解説します。
飼育環境のつくり方
飼育ケースについては、一般的なもので問題ありません。キリギリスは通常、葉の上で生活するため土は必要ありませんが、代わりに砂や新聞紙を敷くとよいでしょう。これらの床材は、足を痛めさせないためにも重要です。
また、捕まえた場所に生えている草や落ち葉などを持ち帰り、ケースに入れてあげるとキリギリスが安心して暮らせます。枯れた草は、小まめに取り替えてあげましょう。
水分は、野菜から摂取できるため特にあげる必要はありませんが、湿らせた脱脂綿や水苔を容器に入れて、ケースの床に置くと安心です。特に暑い季節は常設してあげるとよいでしょう。清潔に保つため、2~3日に1回は交換しましょう。
飼育ケースは日光の当たる場所に置いてあげる
キリギリスは日光を好む昆虫なので、ケースは日当たりのよい場所に置いてあげるようにしましょう。ただし、ケース内の温度が上がりすぎるとよくないため、風通しを確保するなど適温を保つ工夫は必要です。
日当たりがよいときは、盛んに鳴く様子も確認できます。一方、雨の日は部屋が薄暗くあまり鳴かなくなりますが、部屋の明かりをつけると鳴きやすくなります。
とはいえ、キリギリスは基本的には昼行性の昆虫です。盛んに鳴くのは朝から夕方にかけての時間帯で、夜は休んでいるケースがほとんどです。
累代飼育は難しい
累代飼育とは、昆虫を繁殖させて何代にもわたって飼育することです。キリギリスの累代飼育は不可能ではありませんが、難易度は高めです。
卵が無事にかえるには、土の湿り具合や気温を自然の環境に近づける必要があります。キリギリスの卵がかえるまでには1年のケースもありますが2~3年かかるのが通常で、中には4年後にかえる卵もあります。その間、ケース内の温度・湿度を適切に管理するのは容易ではありません。
例えば、土を湿らせすぎると、卵が腐ったり窒息したりする可能性があります。また、冬にはケースを外に出して、寒さを感じさせるようにしなくてはなりません。キリギリスの累代飼育には、根気強さが求められます。
キリギリスの特徴・生態
ここでは、キリギリスの観察に役立つ特徴や生態を解説します。また、鳴き声の特徴やバッタとの見分け方もチェックしましょう。
日本に生息しているのは大きく2種類
日本に生息するキリギリスの仲間は、60種類以上確認されています。その中で、かつて単に『キリギリス』と呼ばれていた種が、近畿地方より東に生息する『ヒガシキリギリス』と、西に分布する『ニシキリギリス』という二つの異なる種として、近年区別されるようになりました。
両者の違いは、主に体のサイズや色にあります。ヒガシキリギリスの方が小柄で、羽も短めです。ヒガシキリギリスの体色は褐色の印象が強く、前羽にある黒い斑点がニシキリギリスよりも多いのが特徴です。
ニシキリギリスは、ヒガシキリギリスよりも体色が緑みががっている傾向にあります。前羽の黒い斑点は持たないか、一列程度の個体が大半です。
鳴き声の特徴
キリギリスの鳴き声は、「ギィーチョン!」という感じに聞こえます。鳴き声が機織(はたおり)の音に似ていることから、『機織虫』『ハタオリ』との別名もあります。
ただし、正確にはキリギリスは鳴いているのではありません。弦楽器のように、羽をこすり合わせて音を出しています。これを意識して聞くと、確かに何かを引っかいているような音に聞こえてくるはずです。
昔はキリギリスの鳴き声を風流に感じる人が多く、江戸時代から1980年代までは店頭で盛んに販売されていたといわれます。キリギリスを飼うのは、昔ながらの日本人の繊細な情緒に触れることにもつながるといえるでしょう。
バッタとの見分け方
キリギリスとバッタは色・形が似ているので、見分けが難しいと感じる人もいるでしょう。英語ではキリギリス単体を表す『katydid』という単語もありますが、バッタなどと一緒に『Grasshopper』と呼び、区別をしないケースもあります。
しかし、両者を見分けるポイントはいくつかあります。見た目の大きな違いは、触角の長さです。キリギリスは体よりも触角の方が長く、バッタと見分ける際の大きな手がかりとなります。
見た目では分かりにくいものの、耳の位置にも違いがあります。キリギリスは前脚、バッタは胸部です。キリギリスは鳴き声でコミュニケーションを取るため、音を効率的に知覚できる位置に耳が進化したと考えられています。
おすすめのキリギリスの捕まえ方
これからキリギリスを捕まえに行く人に向けて、おすすめの捕まえ方を紹介します。かまれてけがをしないよう、注意点も押さえましょう。
タマネギを使った「キリギリス釣り」
キリギリスを捕まえるおすすめの方法は、大好物のタマネギを使った『キリギリス釣り』です。
やり方はとても簡単で、輪切りにしたタマネギにたこ糸を付け、キリギリスがいそうな草むらに垂らすだけです。糸の反対側を、割り箸のような細い棒に結んで釣竿代わりにすると、やりやすいでしょう。
キリギリスが食いついたらゆっくりと引き上げ、食事に夢中になっているところを捕獲します。キリギリス釣りは、昔から子どもの遊びとして知られています。ぜひ、子どもと一緒に挑戦してみましょう。
かまれないように注意する
キリギリスを捕まえる際は、かまれないよう注意が必要です。肉食を好むキリギリスはかむ力が強く、ときには体の大きいカマキリを攻撃できるほどの力を持ちます。
かまれるとけがをする可能性があるため、捕まえるときは軍手を装着し、背中の方を持つよう心がけましょう。特にクビキリギスと呼ばれる種類は、かまれると出血を伴うこともあり危険です。
心配なときは手で捕まえようとせず、釣りに使ったタマネギごと虫かごに入れてもよいでしょう。
キリギリスを飼う上で知っておきたいこと

飼育に挑戦するに当たり、押さえておきたい知識を紹介します。キリギリスに快適に過ごしてもらいつつ、観察や鳴き声鑑賞を思う存分楽しみましょう。
成虫の寿命は約2カ月
キリギリスの成虫の寿命は、約2カ月程度しかありません。春ごろに卵から出た幼虫は、脱皮を繰り返しながら成虫になります。
夏ごろには繁殖活動を行い、冬が来る前に寿命を迎えるライフサイクルです。このため、キリギリスを飼い始める時期は、梅雨明けごろがよいでしょう。
成虫になって間もないこの時期に飼い始めれば、夏休みが終わるまで生き続けてくれる見込みがあります。自由研究の題材として考えている場合は、夏休み前から準備を始めましょう。
鳴くのはオスだけ
キリギリスの鳴き声は、求愛のために出すものであり、鳴くのはオスのみです。キリギリスの鳴いている様子を観察したいなら、オスを捕まえる必要があります。
キリギリスのオスとメスを見分けるには、お尻の先にある産卵管の有無を確認しましょう。産卵管とは、卵を産むための管であり、メスだけに付いています。
キリギリスのお尻に針のような管が伸びていればメス、特に何も付いていなければオスです。
共食いに注意する
キリギリスは共食いをする可能性があるので、複数匹飼うときはケースを分けるのが無難です。スペースの都合でケースを分けられない場合は、十分な量の餌を与え、取り合いを防ぎましょう。
また、ケース内に小枝や草を十分に入れ、隠れられるスペースを与えるのもポイントです。アクリル板や木の板などで、仕切りを設けるのもよいでしょう。
繁殖のためにオスとメスを一緒に飼育する場合でも、共食いのリスクはあるため、繁殖はある程度慣れてから試みるのがおすすめです。
まとめ
キリギリスは、植物も動物も食べる雑食性の昆虫です。野生では、主に花や草、他の昆虫を食べて暮らしています。飼育時に与える餌としては、タマネギや小さな昆虫がおすすめです。
成長や繁殖には、動物性のタンパク質が欠かせないため、野菜だけに偏らないよう配慮する必要があります。ドッグフードやミルワームなど、手に入れやすい餌もあるので活用しましょう。
キリギリスの鳴き声は、古くから夏や秋の風物詩として好まれてきました。飼育・観察を通して、昔の人々の暮らしに思いを馳せてみるのも、心に残る体験となるでしょう。