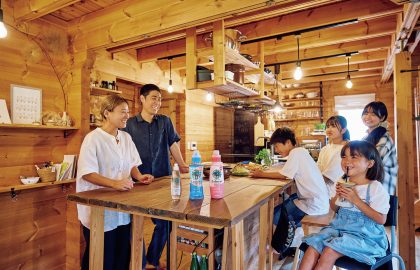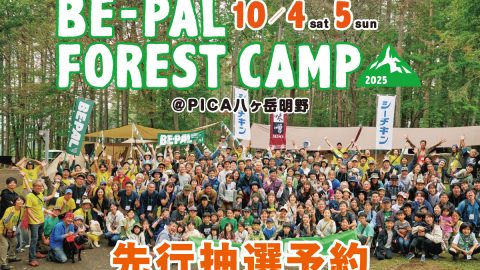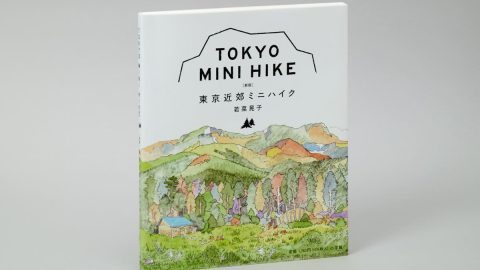(出典)photoAC
オオカマキリの特徴や生態
まずは、オオカマキリの見た目の特徴や、活動時期などの生態を見てきましょう。また、カマキリの名前の由来も併せて紹介します。
体長約7~10cmの大型のカマキリ
オオカマキリは、日本のカマキリの中で最大級の大きさを誇ります。成虫の体長は約7~10cmで、メスの方が大きめです。
体の色は緑または褐色で、いずれも天敵や獲物から身を隠すのに都合のよい保護色です。全国の草地・やぶ地に分布し、特に日当たりのよい草むらを好む傾向にあります。
カマキリは、大きな鎌のような前脚を使って獲物を捕食します。名前の由来は『鎌で切る』という説もありますが、『キリ』の部分はキリギリスに似た姿から付けられたとの説が有力です。
成虫は7月から多く観察できる
成虫のオオカマキリを観察できるのは、7月下旬〜10月ごろまでの期間です。4月ごろに卵からかえった幼虫は、6~7回脱皮して、7~8月には成虫になります。
晩夏には繁殖行動が活発化し、メスは冬が来る前に産卵を終えます。交尾の際に、オスがメスに食べられてしまうこともありますが、理由は分かっていません。
また、オオカマキリは日中に活動します。昼時の草むらをのぞくと、迫力ある捕食シーンを見られるかもしれません。
オオカマキリの一生
オオカマキリは幼虫の頃から、強い捕食者として自然界に君臨していると思う人もいるかもしれません。
しかし、無事に成虫になれるのは、過酷な生存競争を生き抜いた選ばれし個体のみです。そんなオオカマキリの一生を、順を追って解説します。
卵の状態で冬を越す
オオカマキリのメスは、主に木の枝や草の茎に、卵鞘(らんしょう)と呼ばれる塊を産み付けます。卵鞘の中には、100~300個の卵が入っています。
卵鞘は、蜂の巣のような形をしており、スポンジに似たフワフワとした質感が特徴です。色は、冬の枯れた植物にまぎれやすい茶褐色です。
卵鞘の中で、卵は寒さや衝撃から守られながら、冬を越します。暖かくなると卵が一斉にかえり、オオカマキリの一生がスタートします。
成虫になれるのは数匹だけ
卵からかえった幼虫は、アブラムシやショウジョウバエなどを捕食しながら脱皮を繰り返し、成虫を目指します。しかし、トカゲ・イタチなどの天敵に食べられたり、共食いしたりして、その大半が命を落としてしまいます。
結果として、成虫になれるのは数百匹中わずか2~3匹のみの時もあります。生存競争の激しさが、オオカマキリの厳しい自然環境を物語っています。
なお、成虫になる前にさなぎの状態を挟む昆虫を『完全変態』というのに対し、さなぎにはならず、脱皮を繰り返しながら成虫の形へ近づく昆虫を『不完全変態』と呼びます。カマキリは不完全変態で、幼虫と成虫の形はあまり変わりません。
成虫は秋まで活動する
肉食のカマキリは、バッタやチョウなどの昆虫だけでなく、カエルやヘビなど自分より大きな獲物を捕らえることもあるそうです。動くものを食べ物と認識するため、時には小鳥を食べることもあるといわれます。
繁殖期には、オスがメスを見つけると、背後から飛びついて交尾を開始します。交尾中にメスがオスの頭部を食べることもありますが、腹部の機能は腹部の神経がつかさどっているため、そのまま交尾が可能です。
交尾後のメスは、産卵のために餌を探し続け、秋が深まる10月ごろまで動き回ります。冬越しはせず、霜が降りる頃には、ほとんどの個体が短い一生を終えます。
オオカマキリの観察・飼育のポイント
オオカマキリをじっくりと観察したい人や、飼ってみたい人に向けて、観察や飼育のポイントを解説します。意識して観察してみると、意外な発見があるかもしれません。
自然での見つけ方と観察のポイント
オオカマキリは近所の草むらにいるので、気軽に観察しに行けます。カマキリは獲物を見つけると、草むらや花の陰に隠れ、鎌が届く距離に獲物が近づくまでじっと待ちます。
獲物が間合いに入ると一気に鎌で挟んで捕らえますが、それはわずか0.1~0.4秒の出来事です。食事の後は、前脚を舐めるようにして手入れをするきれい好きの一面もあります。
カマキリの目は『複眼』と呼ばれる複雑な構造となっており、どの角度から見ても目が合っているように見えます。これは『偽瞳孔』と呼ばれ、目が黒く見えるのも特徴の一つです。
飼育環境と餌の与え方
オオカマキリの飼育は、環境を整えて餌をあげるだけでよく、それほど難しくありません。まずは通気性のよい虫かごを用意し、底に湿らせた土と小枝・葉を配置して、自然に近い環境を再現してあげましょう。
餌は、生きたコオロギやショウジョウバエなど、動くものがベターです。捕まえるのが難しい場合は、魚肉ソーセージや刺身でも代用できます。無糖のヨーグルトを食べる個体もいます。
カマキリは、動いているものを餌として認識するので、肉や刺身を与える際は目の前で動かしてあげると食べてくれるでしょう。
まとめ
夏から秋にかけて活発に行動するオオカマキリは、夏休みの観察対象としてぴったりです。
オオカマキリは、カマキリの中でも大型の種類で、それゆえ捕食シーンは見応えがあります。鎌の手入れや目の色の変化など、オオカマキリの観察ポイントはさまざまです。
そんなオオカマキリも、成虫まで成長できる個体はほんの一握りで、厳しい生存競争に勝ち抜かなければならない運命にあります。こうした背景を知れば、飼育する際もより愛着が湧くことでしょう。