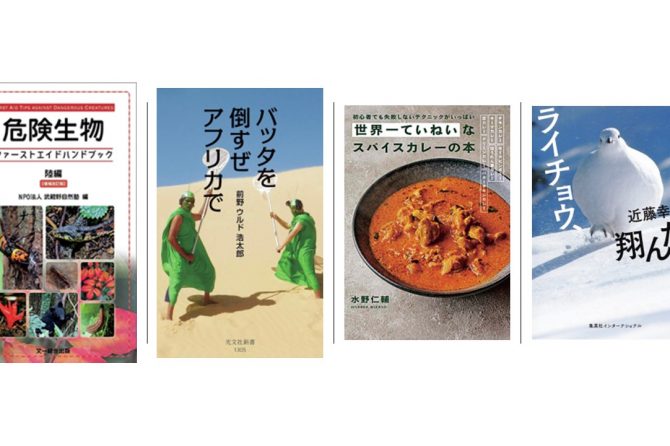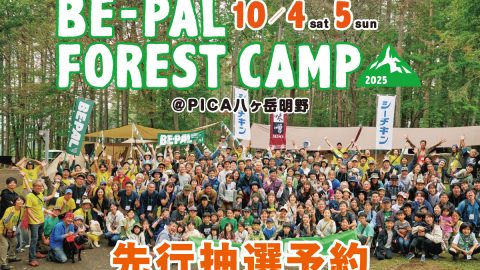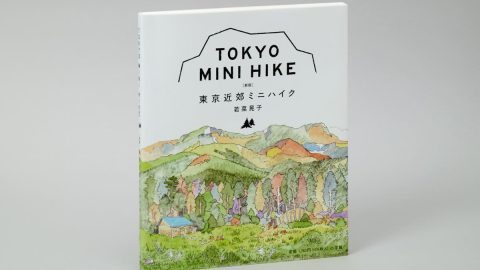(出典)photoAC
【種類別】バッタが好む食べ物

バッタといっても、種類によって好きな食べ物や飼い方のポイントはさまざまです。まずは、身近なバッタたちの種類ごとに、どんな食べ物を好むのかを詳しく紹介します。
トノサマバッタ
トノサマバッタは、日本全国の川原や明るい草地などに広く生息しています。成虫の体長はメスで約4〜6cm、オスで約3.5〜4cmと、日本で見かけるバッタの中では大型です。
体色は緑や茶色が見られ、力強く跳ねる姿が魅力です。ススキ・エノコログサ(ねこじゃらし)・オヒシバといった、イネ科の植物の葉を中心に摂食しています。
イネ科の植物が手に入らない場合には、キャベツ・レタス・キュウリといった市販の野菜でも代用は可能です。しかし、あくまで一時的な補助食であり、自然に近い食事の方が健康的です。
ショウリョウバッタ
ショウリョウバッタは、成虫になるとメスが約7.5〜8cm、オスが約4〜5cmと、日本のバッタの中でも特に大型です。
体の色は緑色や茶色のものが混在し、明るい草地で活発に活動する様子がよく観察できます。イネ科の植物を好み、エノコログサ・オヒシバ・ススキなどの柔らかい葉を主食にしています。
トノサマバッタと同じく、野菜類も餌の代わりになりますが、できるだけ野生の草を与える方が長生きするでしょう。特に幼虫や若い個体には、噛みやすくて柔らかいイネ科の新芽がおすすめです。
オンブバッタ
オンブバッタは、草地や畑、さらには都市部の空き地や庭園まで、幅広い場所に生息している身近なバッタです。名前の由来通り、成虫になるとオスがメスの背中に乗った『おんぶ姿』をよく見かけます。
非常に幅広い植物を好むのが特徴で、イネ科・カヤツリグサ科といった細い葉の草だけでなく、ヨモギやシュンギクなどのキク科、シソやバジルなどのシソ科、ナスやジャガイモなどのナス科の植物の葉も食べます。
家庭菜園や花壇で育てている植物を食べる場合もあるため、飼育の際はさまざまな種類の葉を用意して、その中から特に好むものを見つけてあげるとよいでしょう。
フキバッタ
フキバッタは、低地から山地まで、森林の地表面や林縁と呼ばれる森林の端の辺りに多く生息しています。羽が発達しておらず、飛べない点が大きな特徴です。
移動範囲が狭いため、地域ごとに姿や模様に多様性があり、同じ種類だと分からないケースも多く見られます。
名前の通り、フキの葉を特に好んで食べます。柔らかく広い葉が好きで、クズやフジバカマの葉も好物です。
フキバッタを飼育する際は、自然環境に生えているフキやクズなどを採取して与えるとよいでしょう。その他、入手しやすい餌としては、ヨモギ・オオバコ・シュンギクなどが挙げられます。
クルマバッタ
クルマバッタは、郊外の草原などに生息しており、都市部ではあまり見かけません。成虫の体長はメスが5.5~6.5cm、オスが3.5~4.5cmほどで、トノサマバッタと同じくらいか、やや小さめです。
後羽の黒い模様が、飛ぶと車輪のように見えることが、クルマバッタの名前の由来です。クルマバッタは、トノサマバッタやショウリョウバッタと同じく、イネ科の植物を好みます。
飼育の際には、捕まえた場所で生えていた草の葉を中心に用意してあげるとストレスが少なく、健康的に育ちやすいでしょう。
食べ物と水分の与え方

バッタを飼育するにあたって、まず押さえておきたいことは食事の管理と水分補給です。新鮮な餌を長持ちさせる方法や複数飼いで気を付けたい点、水分の与え方など、世話のポイントをまとめました。
餌を水に挿して鮮度を保つ
バッタの健康を守るためには、餌となる草を新鮮な状態に保つことが大切です。採集した草は、よく洗ってから水を入れた瓶やコップに挿し、そのまま飼育ケースの中に設置します。
こうすることで草が乾燥してしおれるのを防ぎ、バッタが好むみずみずしい葉を長持ちさせられます。特に夏の暑い時期は草が傷みやすいので、できれば毎日チェックして新鮮な餌に入れ替えるとよいでしょう。
バッタの好きな草が入手できないときは、野菜で補うこともできます。ただし、市販の野菜を使う場合は、農薬が付着していないかどうかを必ず確認し、念のため流水でよく洗うようにしましょう。
共食いを防ぐためにはタンパク質も必要
複数のトノサマバッタを同じケースで飼育すると、共食いの恐れがあります。トノサマバッタは完全な草食性ではなく、わずかに肉食性も持ち合わせており、タンパク源として仲間を食べてしまうのです。
共食い防止には、広いケースを用意してバッタが密集しないようにするほか、金魚の餌やドッグフード、煮干しなどタンパク質を摂取できる食べ物を少量与えると効果的です。このとき、ケースの床に直接置かず、小さな皿に入れてあげると掃除・交換が楽になります。
ただし、共食いを完全に防ぐことは難しいため、基本的には同じケースで複数を飼育するのは避ける方がよいでしょう。
霧吹きを使って水分を与える
バッタは通常、食べ物から水分を取ります。このため、わざわざ水を用意する必要はありませんが、乾燥しやすい季節や飼育ケース内が乾燥している場合は、霧吹きで水分を与えると安心です。
草やケースの壁、床に軽く水を吹きかけることで、バッタが舐めて水分補給できるだけでなく、草の鮮度も保たれます。
湿度が低い環境では、1日に1回程度霧吹きをして、ケース内の乾燥を防ぐことをおすすめします。
バッタの飼育環境

元気に長生きしてもらうには、適切な飼育環境を準備することが不可欠です。ケースのサイズ選びから快適に過ごせる工夫、さらには繁殖の準備まで、バッタにとって安全・安心な空間づくりのコツを分かりやすく解説します。
十分な大きさの飼育ケースを用意
フキバッタのような種を除き、バッタはジャンプする昆虫なので、飼育ケースが狭すぎると壁・フタにぶつかり、ケガやストレスの原因となってしまいます。
大きめの昆虫飼育用ケースや水槽を使い、十分な広さと高さを確保しましょう。最適なサイズは、バッタの種類や一度に何匹飼うのかによっても変わります。
特にトノサマバッタはジャンプ力が非常に高いため、できるだけ大きな飼育ケースを選ぶとよいでしょう。
餌・水分・身を隠す草や枝を入れる
ケース内には、バッタの餌となる新鮮な草をたっぷり入れてあげます。草は食べ物としてだけでなく、バッタが身を隠す場所としても重要な役割を果たします。
実際に生活している環境に近い方が、ストレスを感じにくいと考えられるため、安心して過ごせるように環境を再現してあげるとよいでしょう。
水分補給には先述の通り、草やケースの壁に霧吹きをすると効果的です。水を含ませたスポンジや綿を、水入れの代わりに置く方法もあります。
繁殖させる場合は土や砂も必要
バッタを繁殖させたい場合は、飼育ケース内に園芸用土を敷いてあげましょう。メスのバッタは、地面におしりを差し込んで卵を産む習性があるため、ある程度の深さがある柔らかい土や砂の層が必要です。
深さは5~10cm程度あると、卵を産みやすくなります。浅すぎると産卵できなかったり、卵が乾燥しやすくなったりするので注意しましょう。
また、産卵後は土が常に少し湿った状態を保つことが、卵のふ化や幼虫の成長にとっても大切です。
バッタを上手に飼うコツ

頑張って捕まえたバッタは、できるだけ大切に育てたいものです。バッタを傷つけにくい持ち方や清掃作業時の脱走防止の工夫、ケースを置く場所など、知っておきたい実践的なポイントを紹介します。
バッタの脚を持ってはいけない
バッタを捕まえたり飼育ケースから移動させたりするときは、脚をつかまないようにしましょう。バッタの脚はとても取れやすいため、うっかり脚を持つと脱落してしまい、バッタに大きなダメージを与えてしまいます。
安全に持つためには、頭と胸の境目あたりの固い部分をつまむようにします。力加減に不安がある場合は、手のひらでそっと包み込むようにして持ち上げると、バッタが傷つきにくく安心です。
清掃時は袋を利用して脱走を防ぐ
飼育ケースの掃除や餌の交換をする際は、バッタが逃げ出さないよう注意しましょう。ケースのフタを開けると、バッタが勢いよくジャンプして脱走することがあります。
その対策として、飼育ケース全体を大きめのビニール袋で覆って作業したり、ケースと袋をつなげて、掃除の間だけ一時的にバッタを袋の中へ移しておいたりすると安心です。
複数のバッタを飼育している場合は、掃除や餌の交換用に、もう一つ予備のケースを用意しておくと便利です。ひと手間かけることで、スムーズに毎日の世話ができるようになるでしょう。
直射日光の当たらない場所に置く
バッタを飼育するケースは、直射日光の当たらない場所に置くことが大切です。ケース内に強い日差しが差し込むと温度が急上昇し、バッタが弱ってしまいます。
基本は風通しのよい日陰や、室内であれば、明るいけれど直射日光が入らない場所が向いています。理想的な飼育温度は約25~30℃とされているので、夏場は熱がこもりすぎないよう配慮しましょう。
日の光自体はバッタの健康や成長のために必要ですが、日中に軽く間接光が当たるくらいで十分です。
まとめ

バッタの飼育は、自然の営みを身近に感じられる楽しい体験です。種類ごとの好みを理解し、新鮮な食べ物や適切な環境を用意することで、生き生きとしたバッタの姿を観察できます。
バッタを飼うのが初めてでも、餌の管理や水分補給など、ちょっとした工夫やコツを押さえれば、飼育はそう難しくありません。
安全な持ち方や、飼育ケース内の環境づくりの基本をしっかり守ることで、バッタを長く健康に育てられます。飼育が楽しいと感じたら、繁殖までチャレンジしてみてはいかがでしょうか。