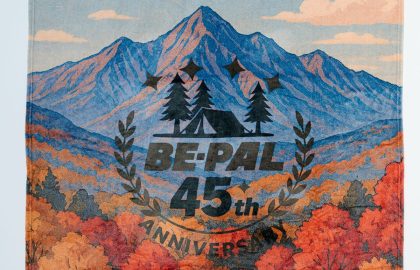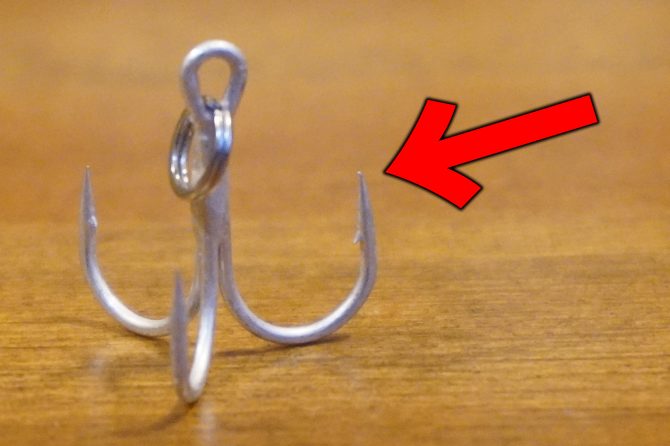今回は東京都中央区の日本橋周辺をめぐる「椙森・小網・茶の木GREEN WAY」です。
- Text
4th ルート:椙森・小網・茶の木GREEN WAY
今回は、江戸の中心である日本橋のすぐそば、人形町周辺に点在する寺社仏閣をめぐります。名付けて「椙森・小網・茶の木GREEN WAY」です。
もともと日本橋周辺には、ぐるっと円状に「日本橋七福神」をめぐるコースがあります。ネットで検索すれば七福神を効率よく歩くルートなども簡単に分かりますが、それでは面白くありません。自分なりのルートを立案するため、どこからスタートし、どういう順番で歩を進めるか、事前に地図を見ながら頭を悩ませました。
人形町というと、下町情緒が感じられる町並みをイメージしがちです。でも、住所でいえば「東京都中央区」だし、それなりにビルが建ち並んでいます。なので、ただ漫然と七福神をめぐるだけだと、「GREEN WAY」でもなんでもなく、単なる街歩きになりかねません…。
ということで、地図をにらみながら熟考した後、ターミナス(=トレイルの起点となるアクセスポイント)に定めたのは、小伝馬町駅です。ここから周辺の七福神をまいりつつ、水天宮前駅を目指します。
いままで何度も小伝馬町駅に降り立っています。でも、何かの用事に向かう途中に通り過ぎるだけでした。今回、ふと「小伝馬」って変わった名前だなと気になり、調べてみました。
小伝馬町
小伝馬町の由来は、江戸時代の「伝馬(でんま)」。伝馬とは、江戸時代の宿場制度において、公用の人や荷物を運ぶために、宿場ごとに人馬を交代で利用する制度のこと。あるいは、そのために常備された馬を指す名称だそうです。
伝馬を仕切っていたのが伝馬役で、地名は伝馬役が住んでいたことから付けられたといいます。ちなみに、多くの馬を準備していた場所を「大伝馬町」、それよりも少ない方が「小伝馬町」と名付けられたそうです。
小伝馬町駅の4番出口を出てすぐの場所に、小伝馬町にまつわる3つの史跡が案内されています。草花に覆われているのでうっかり通り過ぎてしまうかもしれませんが、その案内板には、「石町時の鐘(こくちょうときのかね)」、「伝馬町牢獄屋敷跡」、「吉田松陰先生終焉の地」と記されていました。

石町時の鐘
江戸城下の人々に時刻を知らせていた鐘で、もともとは二代将軍・秀忠の時代に本石町(現在の日本橋室町四丁目付近)に設置されたといわれています。「石町は江戸を寝せたり起こしたり」などと川柳に詠まれるほど、江戸の人々の生活に欠かせない存在だったそう。残念ながら1710年に起こった火災で鐘楼などが焼失。現在の鐘は1711年につくられたもので、近くの十思(じっし)公園で見ることができます。
伝馬町牢獄屋敷跡
小伝馬町には刑が確定するまで囚人の身柄を拘束しておくための「伝馬町牢屋敷」がありました。平賀源内や吉田松陰らが最期を迎えた場所としても知られています。その敷地の広さはおよそ8,600平方メートルで、約5200畳です。そんな枚数の畳を目にしたことがないのでイメージしにくいですが、とにかく江戸最大規模の牢屋敷だったそうです。上記の鐘と同じく、近くの十思公園に「江戸伝馬町処刑場跡の碑」などが残されています。
吉田松陰先生終焉の地
幕末の長州藩士・吉田松陰は、兵学、洋学に通じており、松下村塾(私塾)で教えていました。「松下村塾」は、木戸孝允、前原一誠、高杉晋作、久坂玄瑞、伊東博文、品川弥次郎ら、明治維新を成し遂げた多くの偉人を輩出しました。松陰は安政の大獄に連座し、上記の牢屋敷に投獄されます。そして、安政6年(1859)に処刑されました。こちらも十思公園内に松陰の辞世の句が刻まれた石碑があります。
なんとトレイルヘッドに着いた時点で、ものすごい情報量です。一瞬、もう十分だなと満足しかけましたが、まだ出発前でした。
気を取り直して、まずは新日本橋駅方向に歩いていきます。ビル街ですが、わずかながら紙店など古くからの個人商店も残っています。
さらに、細い路地に進んでいきます。路上には案内板がないので分かりませんが、手元の地図上には「えびす通り」「旧日光街道」などと表示が出ています。人形町エリアは、史跡がたくさんあります。いちいち細かい道まで表示板を設置したら、街中が看板だらけになってしまうのかもしれません。
などと、どうでもいいことを考えながら歩いていると、GREEN WAYのルートらしく街路樹が目立ち始めました。そんな街路樹の一角に、今回の第一のポイントである椙森(すぎのもり)神社が見えてきました。
椙森神社
藤原秀郷が平将門の乱鎮定のため戦勝祈願し、戦後に白銀の狐像を奉納したといわれています。1466年(文正元年)太田道灌が雨乞いに霊験があったとして、山城国稲荷山五社大神を勧請して祀ったとか。
江戸時代には江戸三森神社(椙森、柳森、烏森)の一つとして数えられ、庶民だけでなく諸大名の崇敬を集めるようになったそうです。社殿は残念ながら関東大震災で焼失し、1931年(昭和6年)に鉄筋入り耐震構造で再建されました。
ちなみに、烏森神社は僕の過去の連載「TOKYO山頂ガイド」File.1の愛宕山の回でも少し触れています。

富塚の碑
江戸時代に行われていた富くじをしのんで、1919年(大正8年)に建立された碑。現在のものは昭和28年(1953年)に再建されたもので、宝くじ祈願の絵馬も多く、「サマージャンボ当たれ」と書かれているものも見かけました。
恵比寿大神
椙森神社には恵比寿大神がまつられています。恵比寿は、現在では七福神で唯一の日本古来の神です(他はインドか中国の由来)。
実は、恵比寿という神は複数あるそうで、イザナギ、イザナミの子である蛭子命(ひるこのみこと)、もしくは大国主命(大黒さん)の子である事代主神(ことしろぬしのかみ)とされることが多いそうです。
また、恵比寿は海神とも呼ばれます。恵比寿の本来の神格は人々の前にときたま現れる外来物に対する信仰であり、海の向こうからやってくる海神だとか。漁業神、寄り神(漂着物の神)の他に、水の神としての信仰も存在するそうです。
椙森神社を出て、再びビル街を進むと日本橋保険センターが見えてきます。入り口にある不思議な像を見つつビルを抜けると、開園してから日が浅いと思われる緑豊かな中央区立堀留児童公園がありました。園内では親子連れが楽しそうに遊んでいて、隣接してカフェもあります。
ビル街を抜けた先に現れた憩いの空間に心が和み、思わず真新しいベンチでひと休みしてしまいました。東京の都心であっても、人心地つけるスポットは意外とあります。こうした気持ちのいい空間で、先を急がずにゆったりするのも「東京GREEN WAY」ならではの歩き方といえるかもしれません。

休憩を終え、堀留児童公園を出ようとすると何やら案内板が設置されていました。この堀留児童公園のあたりは、以前は東堀留川が流れていたそうです。
東堀留川の江戸桜通りより上流は関東大震災のがれきによって、1928年(昭和3年)に埋め立てられます。さらに、下流の東堀留川も戦後の残土処理などのために埋立てが始まり、1949年(昭和24年)には川そのものが消滅しました。現在の児童公園の南側に水路があるのですが、これは東堀留川の歴史を継承できるようにと設置されたそうです。

堀留児童公園を出ると、しばらくビル街の裏路地を通っていきます。やがて路地を抜けると小網児童公園が現れました。公園の筋向いの道に入ると、すごい行列ができています。しかも、次々と人がやってきて、警備員の方が列に並ぶように指示しています。そうです、ここが今回のGREEN WAYの2番目のポイント、小網神社です。
小網神社
もともと恵心僧都源信(えしんそうずげんしん・僧侶)が編んだ草庵がありました。1466年(文正元年)、疫病が流行ったときに、この草庵に稲穂を持った老人が訪れ、数日間泊まります。その夜、庵主は恵心僧都の夢を見たそうで、「この老人を稲荷神として崇めれば、疫病は退散する。」というお告げを聞いたとか。翌朝、この老人の姿は消えていたそうです。
さっそく稲荷神をまつる神社を建てたところ、疫病も収まったそうです。領主の太田道灌もこの話を聞き土地を寄付し、参詣したそうです。
1923年(大正12年)の関東大震災で社殿を焼失し、現在の社殿である神楽殿は、1929年(昭和4年)、大正期の明治神宮造営の工匠長・内藤駒三郎宮大工一門によって再建されたそうです。「昇り龍」「降り龍」などの彫刻が施されており、大変貴重な建築だそうです。

それにしても、なぜ小網神社は参拝者が多いのでしょうか。関東大震災のときに社殿そのものは罹災しましたが、神職が神体を携えて避難して難を逃れました。第二次世界大戦の際には、奇跡的に空襲の被害に遭わずに済みました。そうした経緯から「強運厄除の神さま」といわれているそうです。そして、こうしたことがYouTubeなどで紹介され、日本人だけでなく外国人の参拝客も増えているのだとか。
弁財天と福禄寿
小網神社は東京銭洗弁天としても知られています。まつられているのは、弁天財と福禄寿です。もともと弁天財は、同じ境内にある萬福寿寺にまつられていましたが、神仏分離令で分離。お寺が廃止となり、再び小網神社に祀られたとか。
福禄寿とは、道教で強く希求される3種の願い=三徳を具現化したものだそうです。三徳とは、幸福(血のつながった子に恵まれること)、封禄(財産のこと)、長寿(単なる長生きではなく健康を伴う長寿)です。
小網神社を出て、歩を進めていきます。日本橋小学校の角を曲がり、1本目の道路を過ぎると、つるっとした黒いクジラの像を発見。人形町で、何でクジラ…?
鯨と海と人形町
江戸時代、この一帯には、江戸歌舞伎の「市村座」「中村座」のほか、人形浄瑠璃の小屋などが集まっていました。また、それらの人形を作る人形師や雛人形、手遊物などを商う店もたくさん立ち並んでいたところから、1933年(昭和8年)に正式に人形町という地名になりました
で、あやつり人形のバネは今でもクジラのヒゲが使われているそうです。あやつり人形の精妙な首の動きは、弾力に富んだクジラのヒゲでなければ出せないとか。つまり、人形(町)とクジラには密接な関係があったのです。

クジラの像を過ぎ、またまたビル街を進んでいくと、茶ノ木神社がありました。緑豊かで、日差しをさえぎる木陰があってほっとします。そんな雰囲気なのに、不思議と周りのビル街に溶け込んでいます。小さいながらも風格ある神社です。
茶の木神社
創建は江戸時代で、この地にあった下総国佐倉藩の中屋敷の屋敷神としてまつられていたのが起源。神社の周りに茶の木が植えられていたことから、「お茶ノ木様」と呼ばれるようになったとか。
佐倉藩中屋敷やその周辺は、長らく火災の難を逃れていたことから、いつしか「火伏せの神」としての尊崇を集めるようになったといいます。町人が大名屋敷に立ち入ることは禁止されていましたが、佐倉藩は特例として年1回、初午の日に参拝を許可したそうです。

布袋尊
茶の木神社にまつられているのは、布袋尊です。布袋は、唐代末から五代時代にかけて明州(現在の中国浙江省寧波市)に実在したといわれている仏僧。大きな袋を背負った太鼓腹の僧侶です。
日本では鎌倉時代に禅画の題材として布袋が描かれ、庶民には福の神の一種として信仰を集めるようになったとか。当時の人々にとって肥満体は裕福で寛容なイメージで、そこから福の神となったのかもしれませんね。(個人の意見です)。
茶の木神社と水天宮前駅は目と鼻の先。ということで、今回の「椙森・小網・茶の木GREEN WAY」は、ここでフィニッシュです。
はい、日本橋七福神のうち、三社三神しか参っていません。七福神を1日で一気にめぐらなければいけないなんて決まりはないし、そうしないとご利益が得られない、なんてこともないはずです。あくまでも自分のペース、自分のルートでめぐり歩けばいいと思います。
今回めぐった三社はそれぞれに違った味わいがあり、個人的に大満足です。斉藤流の「日本橋三福神めぐり」、ぜひ歩いてみてください。…といいつつ、次回は日本橋七福神の「残り」をめぐります。
■今回歩いたルートのデータ
|距離約1.5km
|累積標高差約5m
今回のコースを歩いた様子は動画でもご覧いただけます。
●椙森・小網・茶の木GREEN WAY