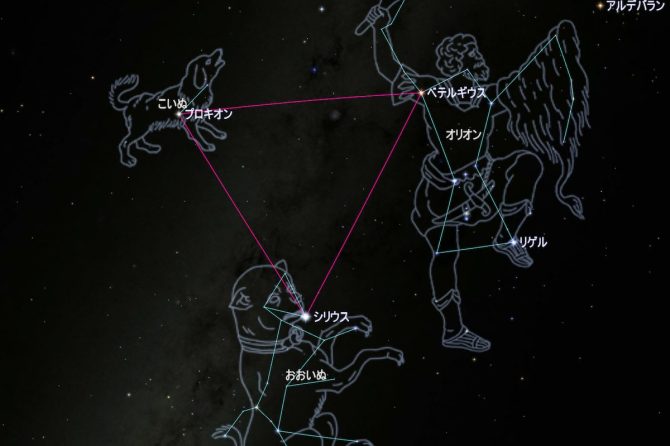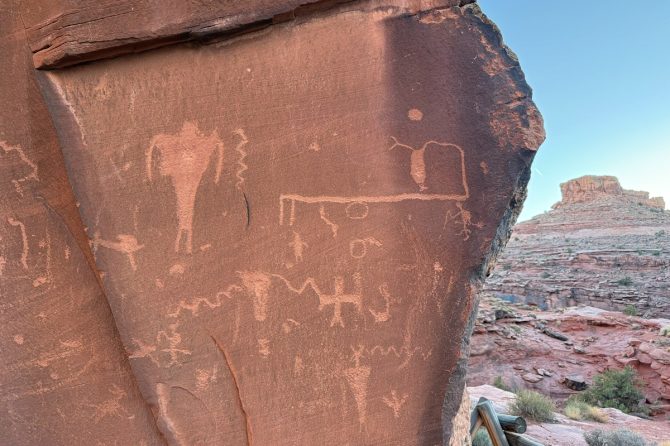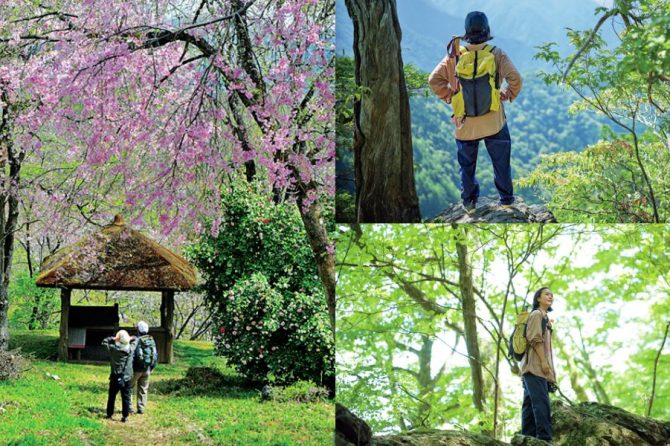- Text

日本のミライを明るくする! 園児野生化計画 vol.32
未知の生き物をさわるときは、大人も子どもも関係なく躊躇するもの。
彼らの言葉を借りるなら
「見た目がキモい」「噛まれそう」「どんな動きをするかわからない」
という3点から「怖い→さわりたくない」となるようだ。
様子を見てみると、本当はさわりたいのに怖いからさわれないという子どもも多い。
では、どうしたらさわるきっかけが出来るのか?
これをハセベ式「生き物をさわる学」で順を追って紹介しよう。
1:見せてあげる

この生き物の生態を話して、かつ怖い動きを”少しだけ”封じた状態で持って見せてあげる。
少しだけというのがミソで、動きがあるから面白い、興味が持てるといった要素を完全になくさないためだ。
2:ちょんとさわらせてあげる

生き物を押さえてあげた状態で、子どもが好きなタイミングで生き物をちょんとさわってみる。
この時に、さわりやすいところをちゃんと露出してあげることと、さわれるタイミングをじっと待ってあげることがポイントだ。
3:持たせてあげる

生き物との壁が少し低くなったところで、子どもに持たせてあげよう。
この時にただ持ち方を教えるのではなく、どう持つと生き物に襲われない、噛まれない、変な動きをしないか、死なないかをちゃんと話してあげること。
そうすることで、子どもは安心して生き物を持つことができるのだ。
4:お友達の手経由で他の子どもが持つ

ここまで来たらもう大丈夫。
自分と同じ目線の子どもが持っていることで、他のお友達もなぜか生き物をさわったり持ったりすることが出来るようになる。
さらには、「私も、僕もさわりたい!」と新しい挑戦者がでてくるところも面白い。
ここからはもう子ども達の世界をいかに邪魔しないかがポイントだ。
気になる部分をじっくり見るも良し。
生き物にちょっとしたちょっかいを出すも良し。
未知の生き物と子ども達との関係づくりをじっくりと見守ってあげよう。