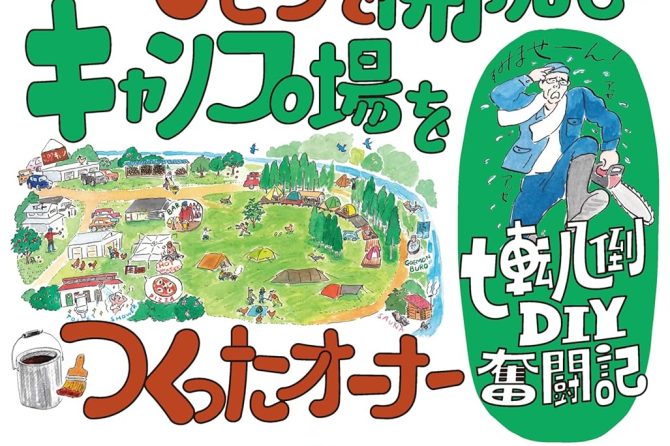- Text
テロワールの追求が世界に誇れる日本ワインづくりへの道

サントリー登美の丘ワイナリーは、甲府盆地や富士山が一望できるロケーションで、100年以上もぶどうをつくり続けています。
土からつくり上げ、丁寧にぶどうを育て、瓶詰まで、一貫したワインづくりを行なっています。世界的にも人気のある和食には、やはり日本ワインがよく合います。そんな日本ワインのさらなる進化を目指し、「FROM FARM醸造棟」という新たな施設が稼働しました。
そして見学ツアーも、良いワインが育つ原点であるぶどう畑から、今回コースに新たに加わったぶどうが醸される醸造棟、ワインが静かに眠る熟成庫を巡るかたちにリニューアルされました。もちろん、ツアーの前後に絶景とともにワインを愉しむワインショップや絶景の富士見テラスに立ち寄ることもできます。
「テロワールの追求が、世界に肩を並べる日本ワインを実現するための道だと考えています。」(登美の丘ワイナリーチーフワインメーカー篠田健太郎さん)
テロワールとは、ぶどうを育てる畑の環境のことで、土の性質のほか、気温変化や日照時間、降雨量など、すべてが含まれています。
登美の丘ワイナリーでは、複雑な地形が生み出す土壌の特徴を見極め、約50区画に細分化し、各区画に最適なぶどうの品種を植え付けています。現在は、12品種のぶどうを栽培しています。ワインは、ビールなどのように水を使用しないため、ぶどうによって味が大きく左右されます。筆者が訪れた9月上旬の時点では、天候に恵まれ、良いぶどうが育っているとのことでした。
リニューアルした見学ツアーに出発

今回新しくなった見学ツアーは、予約制で、80分の「FROM FARM登美の丘ワイナリーツアー」と、120分の「FROM FARM登美の丘ワイナリーツアー〈プレミアム〉」のコースがあり、見学後にはワインのテイスティングタイムもあります。
筆者が体験したのは、120分のプレミアムコースの一部、栽培・醸造・熟成の一貫したつくりのこだわりを体感するパートです。ワイナリー内は、バス移動です。まずは、全体を見渡すことができる眺望台に向かいました。ぶどう畑が広がり、甲府盆地の絶景が広がります。

ぶどう畑では、「棚仕立て」、「垣根仕立て」で栽培されています。ワイン用のぶどうを見る機会も少ないのですが、「垣根仕立て」の栽培を見るのは初めてでした。品種や環境によって栽培方法を変え、1本の枝に一房から二房を残し、摘果することで、ワインに最適なぶどうに育つそうです。

登美の丘ワイナリーでは、下草をはやしたままの元の自然を生かした草生栽培をすることで、大雨などで土が流されないようにするなど、50年、100年先を考えた栽培方法を行なっています。
「ぶどうのライバルになって競争し、共生しています。」と、案内してくれた鈴木さんが教えてくれました。

ぶどうの棚の下とはいえ、日差しはあるため、帽子があると安心です。うっかり忘れてしまったら、麦わら帽子を貸してもらえます。つばも広く、参加者のみなさんに好評でした。足元は、歩きやすい靴を履いていくのがおすすめです。

ぶどう畑から醸造棟へは、バス移動です。途中で珍しいスイッチバックの道があります。現代のガソリン車ならパワーがあり急こう配も上ることができますが、昔はスイッチバックをするしかなかったとのことで、歴史を伝えるためにも1か所だけ残しているそう。珍しい体験ができます。そして、新たにできた「FROM FARM醸造棟」です。

ワイナリーの約50区画ごとに醸造するため、小型のタンクを導入しています。タンク単独で温度制御ができ、今シーズンから稼働します。

タンクで熟成するワインもありますが、やはり樽が並んでいると、ワインが静かにそのときを待っているという雰囲気が漂います。こちらにも小型サイズの樽もあり、樽、タンクのそれぞれの個性あるワインの原酒をアッサンブラージュし、おいしいワインができあがります。
4種のワインをテイスティング

筆者が試飲したのは、SUNTORY FROM FARM「登美の丘 甲州 2023」「登美 甲州 2023」「登美の丘 赤 2022」「登美 赤 2021」の4種類です。「登美」は、赤、甲州ともに「シンボルシリーズ」という世界が感動する品質を目指して醸造されたシリーズのワインです。

香りや味は好みがありますが、興味深かったのは、赤ワインに使用されている「プティ・ヴェルド」という品種です。フルボディの赤ワインに使われるのですが、カベルネ・ソーヴィニヨンよりも多く、約50%も配合されています。
しかも、欧州のものに比べて、渋みが少なく感じました。それが、テロワールの違いだそうで、プティ・ヴェルド100%のワインも試飲してみたのですが、味のタイプはフルボディと表記されていましたが、口当たりがよく、余韻もやさしく感じました。この「FARM 登美の丘 プティ・ヴェルド 2021」(13,200円 消費税込み)を、訪れた思い出に購入するのもおすすめです。
今回、リニューアルした見学ツアーでも、見学のあとに登美の丘ワイナリーでつくられたワインのテイスティングがあります。ワインの種類は、参加する時期によって変更することもあるため、ホームページでチェックしてみてください。

気候変動に対応できるよう、ぶどうの成熟期をより冷涼な晩秋に移行させるため「副梢栽培」を山梨大学と共同研究するなど、未来にも目を向けたワインづくりを行なっています。
「もうすぐ新酒の季節です。収穫感謝祭もあります。天候に恵まれ、良い出来なので楽しみにしてもらいたいです。」(宮下さん)
テイスティングやワインショップは予約なしでも大丈夫ですが、せっかくなら見学ツアーに参加し、ワイナリーについて知識を深めて味わうと、ワインがもっとおいしく感じられる気がしました。
サントリー登美の丘ワイナリー
https://www.suntory.co.jp/factory/tominooka/