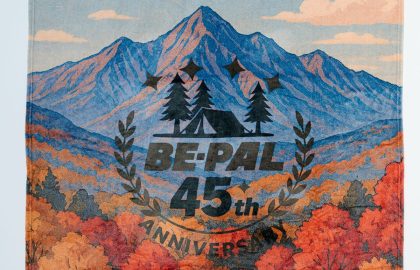日本の家庭で親しまれている果物といえば「みかん」。 もちろん我が家も秋冬になるとよく購入するんですが、皮の剝きやすさと、スッキリした後味のせいか、いつの間にか1日に4~5個も食べていて、知らないうちに家計を圧迫していたりするんですよね。
そんなみかんですが、上質な実を育てるには「摘果(てっか)」と呼ばれる間引き作業が必要だそうです。そして近年はサステナビリティの観点から、かつては行き場のなかった摘果みかん(青みかん)を利活用する動きが盛んになっているのだとか。
お恥ずかしいことに私はみかんに摘果が必要なこと自体を知らなかったのですが、先日、摘果みかんのアップサイクルを行っている方から、摘果を体験できるイベントのお誘いがあったので、6歳の娘と参加してきました。
おいしいみかんの栽培には「摘果」が必須

体験の舞台は、横浜市金沢区の丘の上にある「柴シーサイドファーム」のみかん農園。朝から強烈な日差しが容赦なく照りつけるなか、総勢70人ほどの参加者が集まったそう。
このイベントを主催するのは、横浜産の素材を使ったドレッシングを手がけるアマンダリーナ合同会社代表の奥井奈都美さん。なぜドレッシングを作る会社がミカンの摘果体験を企画しているのかというと、同社のドレッシングはここの農園で摘果された若いみかん(青みかん)を原料にしているからです。

農園を管理する小山さんに聞いたところ、ここには約50本の温州みかんが植えられていて、この規模のみかんを栽培する農園は横浜市でも珍しいとのこと。秋になると市場への出荷のほか、一般のお客さんがミカン狩りも楽しめるそうです。

摘果をする理由は、木に実がなりすぎると養分が分散し、甘みが薄くなったり小ぶりになったりするうえ、翌年の実付きも悪くなるから。しかし、摘果作業はすべて手作業で行うしかないので、とくに炎天下では大変な作業です。
どのみかんも美味しそうなのですが……
朝のブリーフィングを終え、いざ摘果!…と娘と意気込んだものの、どのみかんも鮮やかな深緑色でツヤツヤ。何を基準に摘めば良いのか分からずまごついていると、ベテラン参加者と思しき方が詳しく教えてくれました。

「傷が付いているものや、枝の奥になっていて日当たりが悪いもの、枝が重さで垂れ下がっているもの、鈴なりになっているものは優先的に摘んで大丈夫です。あと『天成り』っていって上向きの実も味が落ちやすいから摘んでください。あっそうそう、実の大小は関係ないので遠慮せず」


ほうほうなるほど、と周囲を見回すと、他の参加者の皆さんは結構なハイペースで次々と青みかんをもいでいて、カゴの中はあっという間にいっぱいに。




みかんの木は、葉で作られた養分によって実がなります。したがって葉の数に対してあまり多くの実がなっていると養分が不足します。理想は「葉っぱ20枚に対して実がひとつ」らしく、この基準で摘果すると全体の2割ほどの量になるそうです。
先述の小山さん曰く、今年は例年以上に豊作だそうで、作業1時間ほどでなんと20ケース分の青みかんが集まりました。

青みかんで、おいしく食べる、洗う、育てる!
このように、美味しいミカンを栽培するには摘果作業が必要不可欠ですが、じつは少し前まで摘果された大量の青ミカンは、市場に流れることはなく、未活用のまま廃棄されていたとのこと。
アマンダリーナの奥井さんは、そうした課題を解決するため、約10年前から、この青みかんを買い取り、藤沢の工場でドレッシングに加工して販売することで、食品ロスを減らしつつ、地産地消の促進につなげる事業を行っています。

この日に摘果されたミカンは大きさごとに選別され、様々なものへ加工されます。果肉は搾汁してドレッシングやジュースに。果皮は胡椒や洗剤などに加工されます。また、洗剤の製造過程で出る残渣は畑へ堆肥として再利用されるなど、いわゆるサーキュラーエコノミーが実現されています。


お土産として小ぶりの青みかんを沢山いただいたのですが、レモンの代わりに飲み物や料理に搾ってみると、フレッシュな酸味が抜群の美味しさ。
個人的にはこのままでジュースにして飲みたいぐらい。このところは猛暑の外出でフラフラになって家に帰ってきたときは、すぐに冷蔵庫の青みかんをカットし、直接口に絞ってビタミンをチャージするのが習慣になっております。

高品質を保つために摘み取られ、廃棄されていた青ミカンが、新しい価値を付加されて生まれ変わる。これからの時代に求められる素晴らしい取り組みでした。