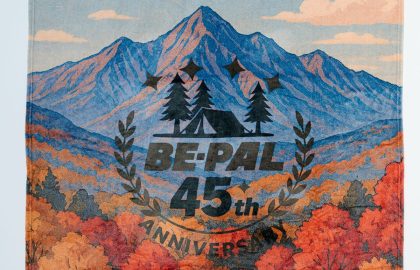大阪府の北摂地域の箕面市に1996年に創業した「箕面ビール」。地ビール低迷期に模索したブルワリーの在り方は「おいしいビールをつくり、地域の魅力を伝える」こと。これぞ地ビールの原点。2代目の大下香緖里代表にインタビューした。
箕面の山のおさるをトレードマークに
箕面ビールの前身は酒販店。先代の父が1996年、突然、ビールを造ると言い出した。ビールといえば大手メーカーが造るラガービールのことだった時代、日本にもヨーロッパのようにいろんなビールがあればいいと思っていた父は、1994年の地ビール解禁でビール参入を決めた。97年に醸造を開始。日本のクラフトビールの初期メンバーといってもいい。
現代表の大下香緖里さんは創業時からブルワリーに入って父の片腕として醸造長を務めた。地ビール人気は間もなく下火になったが箕面ビールは生き残った。
しかし2012年、不幸が襲う。父が急逝したのだ。業界は苦しい状況が続いていたが、香緖里さんは箕面ビールを引き継いだ。「父ならきっと『前進あるのみ』と言ったと思います」と語る。

2010年代前半は「地ビール」低迷期であると同時に「クラフトビール」黎明期でもあった。各地でちらほらとクラフトビールのイベントが開かれ、大下さんも積極的に参加。しかし地方のイベントに出店するようになって大下さんは気がついた。
「“箕面”を読んでもらえない……」
「みのお」である。飲んでもらう前に読んでもらえないことに愕然とした。
それまでは関西の卸中心に販売していたため、ネーミングやブランディングにそれほど注力してこなかった。しかし、これからは地元以外の人にも知ってもらいたい、飲んでもらいたい。「箕面」を読んでもらうにはどうしたら? 大下さんの挑戦はそこから始まった。
それは地域の魅力の見直しに他ならなかった。箕面ってどんな所? 何があるの? 初めて地元を振り返った。
箕面の山には猿がいる。天然記念物のニホンザルだ。以前は山道を歩いていれば遭遇。人慣れしすぎた猿が人里まで下りてきて、接触トラブルが起きるほどだった。
大下さんも子どものころ、箕面大滝へ向かう山道や麓の住宅街でよく猿を見かけたという。「けっこうコワイ顔をしていたんですよね」。2010年に「箕面市サル餌やり禁止条例」が制定され、最近では山道で見かけることも減ったそうだ。
この猿に箕面ビールのトレードマークになってもらった。よその人からはこう尋ねられる。「なんで猿なんですか?」——そこから話が広がり、箕面ビールの話も広がっていく。
ランやハイクが人気の箕面山。登って下りてビールを飲んで
箕面ビールのブルワリーと、直営のビアパブWAREHOUSEは平地の住宅街にあるが、そこから北へ30分も歩けば山の麓に出る。1時間も歩くと北摂山系に連なる箕面山、箕面大滝とハイキングが楽しめる。
箕面山は標高355メートルの低山。大阪市内からも気軽に行けるとあって東京の高尾山的な存在だ。単に似ているだけではない。箕面山と高尾山はともに1967年に明治百年を記念して国定公園に指定され、全長1,748kmに及ぶ「東海自然歩道」で結ばれている。

自然に恵まれた箕面にはランやトレイルラン、マウンテンバイクなどのチームがいくつもあるそうだ。こうしたチームの面々が箕面ビールのビアパブWAREHOUSEによく集まる。

「ビールを飲むついでに街を歩いてもらったり、山歩きしてもらったりしてくれるといいなと思っています。逆に、山を登るついで、ランやハイクのついでにWAREHOUSEに寄ってビールを飲んでもらえたら」と大下さん。
たとえば東京のランチームが箕面のランチームといっしょに走る企画では、メンバーはWAREHOUSEに集合してスタートしていった。走り終えた後はもちろんWAREHOUSEで盛大にビールを飲んで帰っていく。
箕面市もアクティビティの魅力発信には力を入れているようで、アウトドアイベントがたびたび開かれ、箕面ビールもちょくちょく参加している。昨年、北大阪急行が箕面萱野駅まで延伸し、大阪都心部へのアクセスがよくなったこともあり、箕面の注目度が高まっている。そうした街の魅力づくりの一端に箕面ビールとビアパブWAREHOUSEがある。

ワールド・ビア・カップ金賞が名産の柚子復活にひと役買った!
地元の農産物を取り入れたビール造りに、大下さんは早くから取り組んで来た。その代表的なビールが、ベルジャンホワイトの「ゆずホ和イト」だ。ベルジャンホワイトは副原料にオレンジピールを使うのが特徴だが、「ゆずホ和イト」はオレンジピールの代わりに柚子の皮を使う。
かつて「箕面の柚子」はこの地の名産だった。しかし、生産農家の高齢化や人手不足に歯止めがかからず徐々に衰退。山の傾斜地になる柚子の収穫作業は厳しい。収穫されない柚子の実は地面に落ちたまま。それをなんとか活用したいと、大下さんが農家と話し合い、ブルワリーのスタッフ自らが収穫して使わせてもらうことにしたのが2009年頃のこと。
今でこそ柚子を使ったビールは珍しくないが、当時、冬期限定でリリースされた「ゆずホ和イト」は他では味わえない画期的なビールだった。
これが2012年、世界最大のビールコンペティション「ワールド・ビア・カップ(WBC)」のフルーツ・ウィート・ビール部門で金賞を受賞した。ビールアワードは国内外にいろいろあるが、中でもWBCは別格である。

「その頃から地元で柚子が見直されるようになりました。市も産品のPRに力を入れるようになり、『滝ノ道ゆずる』というゆるキャラも生まれたんですよ」と大下さん。
クラフトビールが地元の名産復活にひと役買ったのだ。「滝ノ道ゆずる」は今も健在である。
さて、箕面の山の向こうにも地域の魅力はある。大下さんは兵庫県の県境に近い豊能郡能勢町で麦畑を借りて、試験的に麦の栽培を始めた。この地域も農家の高齢化は進み、休耕地は増える一方だ。少しでも空いている畑を活用できないか。箕面ビールのフラッグシップのひとつ「STOUT」の原料であるローストバーレイ(精麦せず、焙煎した麦)の一部を、自家栽培した麦に代えられないかと考えたのだ。
ただ、近年の猛暑は麦にも多大な影響を与えているようで収量が伸びない。麦の栽培は想像していた以上に厳しい。
収量が少ないと焙煎することも難しい。箕面ビールのブルワリーに焙煎機はない。茶葉の焙煎会社に頼んで麦を焙煎してもらったところ、やはり茶葉と麦では勝手が違うようで、実用に向けて試行錯誤が続いている。
大下さんはホップ生産にもトライしたこともあるが、やはり暑さのため難航したという。もともと麦やホップは北海道や東北など冷涼な地が栽培適性地だ。それでも麦やホップづくりにトライしてきたのは、地域の魅力発信につながると思うからだ。
地域の魅力探しは続く。能勢町の酒蔵、秋鹿酒造とコラボしたビールも造り続けている。秋鹿酒造は酒米の栽培から日本酒の製造まで一貫して行っている蔵元だ。その手作りの麹米を分けてもらいビールの副原料に。
麹の酵素の力を活かすために、仕込み工程ではなく発酵工程で投入する。ほんのり米の風味が香るビールは「猿山鹿男」と名づけられ、スタイル名も「ジャパニーズ・ライス・ブリュット」とオリジナルに。モルトとホップと米麹の奏でる独特な香りは、日本のクラフトビールならではの特徴だろう。
30年前に夢見た地ビールの姿がここにある
箕面ビールのラインナップでもうひとつ紹介したいのが、フーダーという樽で熟成させる「BATON」シリーズだ。

箕面ビールは「バレルエイジド」(樽で熟成させたビール)を早くから手がけてきたブルワリーでもある。埼玉県秩父のウイスキー蒸溜所イチローズモルトと提携し、ウイスキーを熟成した樽で「バレルエイジド」を造ってきた。
ウイスキーの香り、樽の香り、樽に棲みついた様々な菌の作用により、ビールは複雑な熟成を遂げる。約1年、熟成させた後、瓶に詰めてリリースする。どんな味わいが生まれるか。それは樽ごとに異なり、開けてみるかでわからない。
バレルエイジドをもっと本格的にたくさん造りたい。そこで問題になったのが、ウイスキー樽の保管スペースが足りないことだった。直径、高さともに1メートル近くあるバレルを数十個、温度や湿度管理しながら保管するには倉庫代も電気代もかさむ。
そこで大下さんが選んだのがフーダーという細長い樽だ。

フーダーはオーダーメイドで造られる。だから初めはまっさらなオーク樽だ。そこに通常のステンレスタンクで発酵させたビールを詰めて寝かせる。約1年後、瓶に詰め替える。そのとき少量の糖分を加えて、瓶内二次発酵を促す。樽の中で熟成したビールが、瓶の中でまた変わっていく。8ヶ月~約1年を経てようやくリリースされる。
じっくり時間をかけたBATONシリーズは現在8シリーズ目、「BATON 008」まで来ている。仕込むビールは毎回違う。これまでW-IPA、ピルスナー、セゾン、インペリアルスタウト、ベルジャンホワイト。また、場合によってはフルーツなどの副原料も投入する。
各々のビールに含まれる香りや酵母が樽に蓄積し、次のビールにバトンされる。そこから新たに生まれる香りがあるかもしれないし、近所に生息する菌が棲みつくこともあるだろう。フーダーの環境はビールを仕込むたびに変化し、瓶に詰め替えたあとも少しずつ熟成していく。何年も寝かせておける。栓を開けてみるまでわからないビールだ。スリリングでロマンに溢れたビールだ。
このように大下さんはさまざまなチャレンジをしながら箕面ビールを育ててきた。2025年夏、国内のブルワリーは1,000か所を越えると聞く。
こうした状況を大下さんは、「20年前のことを思うと考えられない状況ですよね。“流行り”と見る人もいるかもしれませんが、これだけクラフトビールが認知されるようになったのは有り難いことです。この中で、いかにして私たちのビールを選んでもらえるか。それは味しかないと私は思っています」と語る。
箕面の恵まれた自然をバックに、ランやトレイルなど地元に根づいたカルチャーを支える人たちと手を携え、近隣の農家や酒蔵ともコラボする。製造開始から来年で29年。
地域の魅力を発信することを使命としたブルワリー自身が、地域の特産品のひとつに数えられるようになっている。30年前に生まれた「地ビール」が目指したのはこういうことだったのではないかと思う。
●箕面ビール 大阪府箕面市牧落3-14-18(WAREHOUSE)
https://www.minoh-beer.jp