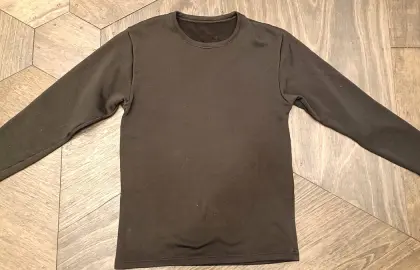日本を代表する独立峰、富士山。今年こそ登ろうと思っていても、日程調整に手間取っているうちに山小屋の予約がとれなくなり泣く泣くあきらめている人もいるのでは。
けれども富士山の魅力は山頂だけではない。
富士山が世界文化遺産に登録されて今年で12周年。古来より信仰の対象であり、芸術の源泉であることが認められ認定されたわけで、遙拝所や水行の地など山麓〜中腹には見どころ満載なのだから。

もっとも、周辺住民であってもこうした富士山の歴史を知らない人は多いそう。そのため富士宮市では夏休み期間中に市内在住・在勤者対象の「世界遺産富士山を体感!トレッキングツアー」を開催している。
このツアーに潜入し、富士山の歴史と登頂以外の楽しみ方を教えてもらった。

コースは、富士山を鎮めるために祀った「富士山本宮浅間大社」からはじまり、大宮・村山口登山道のスタート地点「村山浅間神社」、登山道途中の「中宮八幡堂」、そして富士山五合目から宝永火口までの「大宮・村山口登山道トレッキング」と1日で効率よく富士山の歴史をたどるというもの。この日の参加者は大人だけだったが、歩行時間は3.5時間ほどで8歳くらいから参加可能だ。

ガイドは富士山ネイチャーツアーズの岩崎さん。富士下山家を名乗り「富士山のおもしろさは五合目より下にその7割がある」が持論の名物ガイドだ。
■富士山の端っこが見つかる富士山本宮浅間大社

富士山本宮浅間大社は、富士山の噴火を鎮めるために浅間大神を祀ったのが起源。もともとは各地を転々としていたそうだが、9世紀になって大量の湧き水が出る池のほとりに遷座したという。

それが境内奥にある湧玉池。
かつてはここで登山前の水垢離を行っていた場所だ。
岩崎さんによると「溶岩は穴だらけで雨水が地下へどんどんしみこみ、その下にある水を通さない泥の層に沿って流れついたのがこの湧玉池。溶岩がここで終わっているわけで、富士山の端っことも言える。ここからが富士山なんです」
■苔からわかる富士山の歴史

次に訪れたのは村山浅間神社。
噴火が沈静化した12世紀ごろになると人々はより富士山に近づいて修行するようになり、14世紀には修験道が成立。標高500mの村山浅間神社から6合目にあたる標高2500mまで続く。

富士山は草山(里山)・木山(森林)・焼山という3つの概念に分かれていて、焼山は神仏の世界。草山=俗界、木山=俗界と神仏の世界の過渡部分と考えられているそうで、村山口は草山と木山の境目とされている。入り口こそ植林された杉林だが少し進むと自然林になるのもこの概念通りでおもしろい。
なお、ここからはじまる登山道は有志が整備しつつあるが崩落など危険な場所もある。全行程を歩くなら、岩崎さんらガイドとともに歩くほうが安心だ。

登山道の途中、ここより先は徒歩のみで登ることを許された中宮八幡堂や、女人禁制だった時代の名残である女人堂のあたりを散策。
道の両側には溶岩の上に苔癬類がびっしり生え、まさに緑の絨毯だ。溶岩に沿ってこんもり苔が点在して独特の景色を生んでいる。


途中、片側は苔の森、反対側は土が見えている場所が。
「苔が生えるのは溶岩や倒木だけ。土の上には生えません。つまりここで溶岩流が止まった証拠」と岩崎さん。この境目は修験道の目印になったと考えられているとか。



立ち入る人がそれほど多くないので苔の状態は上々。目をこらすといろいろな種類の苔が生えているとわかる。
中宮八幡堂そばに祀られている水神様も苔の絨毯に囲まれているが、その一部に井戸の跡が見られる。
近くに沢はあるが普段は枯れており「水が貴重で、少しいったところには笹で身を清めた笹垢離があります。このあたりは修験道を歩き始め、ちょうどツラくなってくる場所。ここで水を得られるようにしていたようです」(岩崎さん)
■足もとの石ころは地球の記憶
昼食後、宝永火口へ。
通常、富士宮口の五合目駐車場から宝永火口まではなだらかな遊歩道を進むが、ツアーでは遊歩道脇の表示に従って大宮・村山口登山道へ逸れる。

地図を見ると、富士山スカイラインはつづら折りになっているが、大宮・村山口登山道はほぼ一直線に頂上に向かっているとわかる。五合目から先もほぼまっすぐ登るイメージだ。
とはいえ今回歩いた五合目からであれば新六合目の宝永山荘までは、ときおり立ち止まって植物や石の解説を聞きながらのゆっくりペースで1時間弱。ただ歩くだけであれば30分ほどだろう。

ここから先の場所で注目すべきは石。
登山道途中の石室跡では「明治時代の写真を見るとこの三合目あたりは木がありません。だから石で小屋を建てたと考えられているんです」(岩崎さん)
今ではこのあたりにダケカンバやカラマツなどが生えているわけで「富士山の南斜面ではこの40年で1年に1mほどカラマツが北上していると言われています。木は動かないと言われているけれど、(宝永大噴火から)300年かけて木が登山しているんですね」という言葉も印象的だ。


地面に目を向けると赤みがかった石もあれば黒っぽい石もある。
黒っぽくて重い石は300年前の噴火で20km上空まで飛ばされ、細かく砕け遠くまで飛ばされずに近くへ落ちたと考えられるそう。
「石は地球の記憶。地面を見て、なんだか違和感がある石を見つけたらよく観察してみてください」(岩崎さん)


300年前の噴火によって荒地になったものの、オンタデやイタドリのように地中深くに伸びる根をもつ植物がパッチを作っている。パッチができると他の植物の種がひっかかりやすくなるので、300年後には多様な植物に覆われた草原になっているかも。確認できないのが残念だ。
見慣れている富士山も、ミクロな視点で観察すると土地の成り立ちや歴史が垣間見え、より神々しく感じる。
富士山周辺にはほかにも水行の地である白糸の滝、遙拝所など歴史的な地が点在している。大宮・村山口登山道制覇とは違ってアプローチしやすい観光地も多く、いつもとは違う視点を意識しながら巡ることで富士山の別の顔が見えてくる。
知的好奇心を刺激する草山・木山を抱く。これぞ富士山の懐の深さだ。