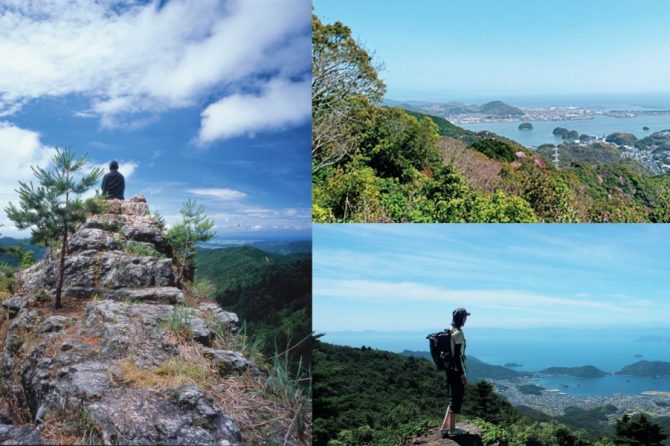今回は東京都中央区の人形町周辺をめぐる「末廣・笠間・暗渠GREEN WAY」です。
- Text
6th ルート:末廣・笠間・暗渠GREEN WAY
前回紹介した「浜町(川)緑道」は、「日本漢方医学復興の地 記念碑」のそばで終わっていました。しかし、ここが暗渠〜緑道に生まれ変わる前、浜町川は東京都千代田区岩本町まで流れていたといいます。
気になって地図を見ると、記念碑から先も暗渠らしき細い道が続いています。ということで、浜町川の痕跡らしきラインを歩くのが、今回の「末廣・笠間・暗渠GREEN WAY」です。
といいつつ、前々回から人形町周辺に点在する寺社仏閣の「日本橋七福神」をめぐっていて、まだ「二福神」残っています。なので、浜町川の暗渠の前に、先に神社を回ります。
日本漢方医学復興の地 記念碑から3分ほど歩くと、末廣神社がありました。
末廣神社
末廣神社の創建などの詳細は不明ながら、1596年(慶長元年)には鎮座していたという記録が残っているそうです。1615年(元和元年)には徳川家康公の命により、山本院實(実)行(やまもといんじつぎょう)を駿河の国よりこの地に呼び寄せて奉仕させました。
そして、1617年(元和3年)に庄司甚右衛門らが幕府から許可を得て、未開の沼地だった周辺地域を開拓し、江戸町一、二丁目・京町一、二丁目を定めます。これが江戸で初めての遊郭「葭原(吉原)」となり、町が活気づくにつれ、人々は神社を篤く信仰したそうです。
1656年(明暦2年)、幕府は江戸市街拡張のため、葭原の移転を言い渡します。翌年、「明暦の大火」により葭原は焼失。同年、遊郭は現在の浅草へと移転し「新吉原」が誕生しました。葭原移転後も末廣神社周辺の町の賑やかさは変わらず、周辺には幕府に仕える役人の住宅も多かったことから、狛犬や玉垣、幕、調度品などが多く奉納されたそうです。

毘沙門天
末廣神社にまつられているのは、毘沙門天(びしゃもんてん)。仏教における天部の仏神で、持国天、増長天、広目天と共に四天王の一尊に数えられる武神だそうです。別名、多聞天、北方天とも。
毘沙門天は、中央アジアや中国など日本以外の広い地域でも、独尊として信仰の対象となっています。日本では、五穀豊穣、商売繁盛、家内安全、長命長寿、立身出世といった、現世利益を授ける七福神の一柱として信仰されています。
末廣神社から浜町(川)緑道方向に戻り、墨田川方面に歩いていくと、日本橋七福神めぐりの最後となる笠間稲荷神社がひっそりと佇んでいました。
笠間稲荷神社
こちらのルーツは、旧笠間藩主・牧野氏の邸内社。牧野成貞は、まだ将軍になっていない庶子(しょし・本妻以外の子)のころの徳川綱吉に仕えます。その後、綱吉は将軍となり、成貞は常陸国内の大名に。さらに「御側御用人」となり、綱吉の最側近となりました。綱吉から下屋敷として21,269坪という広大な敷地を拝領し、築山に稲荷神・山王神・八幡神をまつります。
成貞没後、1747年(延享4)に長男の貞通が幕府の命によって京都所司代から常陸笠間に移ります。そして、笠間藩主として茨城の笠間稲荷神社(別称 胡桃下稲荷神社)を祈願所とするようになります。
笠間藩主である牧野家の祈願所となった笠間稲荷を、第8代藩主貞直が1859年(安政6年)に分祀して江戸下屋敷内の稲荷社に合祀。その場所が現在の笠間稲荷神社 東京別社の鎮座地です。

寿老人
笠間稲荷神社にまつられているのは、寿老人(じゅろうじん)。道教の神仙(仙人・仙女・神など)です。中国の伝説上の人物でもあり、南極老人星(カノープス)の化身とされているそうです。
酒を好み頭の長い長寿の神とされている寿老人。不死の霊薬を含んでいる瓢箪を運び、長寿と自然との調和のシンボルである牡鹿を従え、手には長寿のシンボルである不老長寿の桃を持っています。
福禄寿は寿老人と同一神と考えられ、七福神から外されることもあるそうです。その場合は猩猩(しょうじょう=中国の古典書物に記された動物)が入るといわれています。
笠間稲荷神社の境内を出て、浜町川の暗渠になっていそうな久松児童公園に向かいます。久松自児童公園があるのは、浜町(川)緑道から、ワンブロック北に進んだ場所。地図を見ると、この先に暗渠らしき道が続くような感じです。
日本橋七福神を全制覇したことで、どこ一区切りついた気分になりました。ということで、かつて流れていたであろう浜町川(の暗渠)に沿って、どこまで進めるだろうかと期待を胸に歩き進めることにしました。
ところで、ここまできちんと説明せずに「暗渠」という言葉を使ってきました。僕自身、「地下に埋められた川や水路」ぐらいの認識しかなかったので、あらためて暗渠とは何か、調べてみました。
まず、専門的な総称としては、溝渠(こうきょ)という言葉があります。溝渠とは、主に給排水を目的として造られる水路で、小規模な溝状のもののこと。この溝渠の形状や状態などによって、開渠(かいきょ=上部が解放された水路。明渠=めいきょとも呼ばれる)、道路脇にある側溝(そっこう)などがあります。
暗渠は開渠の逆で、覆いをしたり地下に埋設したりして、外から見えないようにした溝渠のことです。暗渠は覆われているから、その上に緑道などを整備できるんですね。なるほど。
で、浜町川の暗渠と思われる久松児童公園を過ぎると、道がどこに続いているのか分からず、キョロキョロすることに。すると、目の前に「六さん」という一見派手な赤い看板が見えました。
調べると「六さん」は町中華の老舗でした。特にランチタイムは常連客で混み、行列ができることもあるそうです。

よく見ると「六さん」の脇にひっそりと暗渠らしき細い道というか路地が延びていました。

道は、古いビルの合間を縫うように続いています。南側から進むと、どんどん道幅が狭くなっていく感じです。
料理店の勝手口があったり、自転車がたくさん停めてある場所があったり、一服している人がいたり…。香港などの東南アジアの裏路地のような雰囲気です。現在はビルに囲われていることもあって、かつて川が流れていた様子が全く想像できません。
暗渠ルートから一本西側の道に出ると、行列ができている店がありました。「ビーバーブレッド」というパン屋さんです。オリジナルのパンのほか、有名レストランとコラボした商品なども話題を集め、遠方から足を運ぶ人もいるほどの人気店になっているようです。

再び、暗渠の路地というか、路地の暗渠というか、ともかく細い裏通りを進みます。ロープが張られて進めない場所があり、迂回すると、すぐ脇に竹森神社がありました。
竹森神社
江戸時代、この付近には竹やぶが多く「竹職人の町」などともいわれたそうです。その竹やぶにちなんで「竹森神社」と呼ばれるようになったとか。
神体は伏見稲荷からもらいうけたもの。数多い稲荷神社の中でも由緒深いものとされているそうです。

なお、竹森神社は「江戸七森」と呼ばれる神社のひとつです。前々回、恵比寿さまがまつられた椙森(すぎのもり)神社を紹介しましたが、江戸七森は以下の神社です。
- 椙森:堀留
- 烏森(からすもり):新橋
- 初音森(はつねのもり):馬喰町
- 柳森:柳原土手
- あずまの森:向島
- 笹森(ささのもり):谷中
- 竹森 :小伝馬町
さて、浜町川の暗渠の路地は、情緒あふれる裏通りから、自転車やバイクの侵入を防ぐためのガードが付けられた道に変わっていきます。禁煙や駐輪禁止を呼びかける看板が目立ち、味も素っ気もない殺風景な道です。
まるで行く手を阻むような雰囲気ですが、通り抜けられないわけではありません。プロハイカーである僕は、行ける道があるなら進みます。トレイルで藪漕ぎするように、都会の藪(?)を進んでいくと、やがて靖国通りの手前あたりに出たのでした。

路地の終わりから少し北に行くと、神田川に当たります。かつての浜町川は、ここで終わっていました。ということで、僕の浜町川の暗渠をたどるGREEN WAYも、ここでおしまい。ターミナス(=トレイルの起点や終点となるアクセスポイント)の岩本町駅A4番出口へ向かいました。

前々回のFile4から今回のFile6まで、日本橋の北側をめぐってきました。正直に白状すると、当初は日本橋七福神をめぐりながら下町情緒を感じる散策が楽しめればいいか、などと安易に考えていました。
でも、前回のFile5で浜町(川)緑道とめぐり合い、この連載の初心というか意義を思い起こしました。そもそも僕は、「東京GREEN WAY」の連載を通じて、今まで味わったことのない街歩きの面白さを感じてみたい、と思っていたのでした。
はたして、浜町川が流れていたであろう暗渠ルートは、これまで歩いたことのある東京のどの道とも違っていました。東南アジア的な雰囲気だと先述しましたが、街の片隅を通る裏道を進みながら自分が小伝馬町近辺にいることを忘れ、ただただ楽しい気分にひたっていました。あらためて東京は懐が深いし、まだまだ未知の歩き方があることを思い知ったルートでした。
なお、File4からFile6までで紹介したルートを区切らずにスルーハイクで一気に歩くのもオススメです。小伝馬町駅〜水天宮前駅〜岩本町駅を結んだ、いわば「浜町川七福神GREEN WAY」の総距離は約2.5km。30〜40分で歩ける道のりですが、日本橋七福神にお参りするなどして、のんびり歩いてみてください。
自分のことを棚に上げて書きますが、裏道の暗渠ルートを歩くと日本橋周辺=下町情緒などという安易な先入観を軽々と覆す楽しさが感じられるはずです。
■今回歩いたルートのデータ
|距離約1.9km
|累積標高差約4m
今回のコースを歩いた様子は動画でもご覧いただけます。
●末廣・笠間・暗渠GREEN WAY