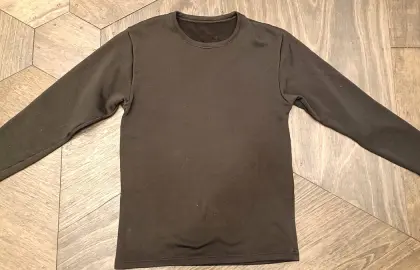冒頭の写真はヨツバヒヨドリに止まって辺りを警戒するノビタキのオス。
絶景すぎる夏の霧ヶ峰とビーナスライン

筆者が初めて霧ヶ峰を訪れたのは1990年代の初め頃。大学のゼミの合宿の下見の時に霧ヶ峰を貫いて走る「ビーナスライン」を友人とバイクで走りました。どこまでもなだらかに続く緑の丘の絶景に感激して、ヘルメットの中でずっとニヤけ顔でいたことを思い出します。
白樺湖と美ヶ原を結ぶ観光道路・ビーナスラインは、標高1600m~2000mの高原を眺めながらドライブが楽しめる道として人気があり、車もバイクも風景を味わうようにのんびりと走っています。実は霧ヶ峰も美ヶ原も日本百名山に数えられる名峰ですが、樹木が少なく、広大な草原が広がる風景が特徴です。
主役は「顔黒」のノビタキとそのファミリー

7月中旬の霧ヶ峰は、そんな高原を鮮やかな橙色で彩るニッコウキスゲやコバイケイソウの真っ白な花が見頃を迎えています。こうした高原の花々や植物には野鳥の餌となる昆虫が集まるためノビタキやホオアカ、アオジなどが多数繁殖していて、関東や関西などから多くの野鳥愛好家が集まる人気の探鳥地になっています。
特に個体数が多いのはノビタキです。日本では夏鳥として知られ、全長は約13センチ。オスは頭と上面の翼が黒いのが特徴です。『昆虫記』を著したファーブルが、幼い頃にノビタキの巣を捕って教会の司祭に諭されたエピソードを覚えている方もいるのではないでしょうか。
ノビタキはジョウビタキやルリビタキなどと同じく体重が軽いので、小さな花や葉の先端にちょこんと止まることができ、そんな姿がカメラマンの格好の被写体になっています。

運が良ければニッコウキスゲの花の上で、ノビタキの給餌の場面に遭遇するかもしれません。親鳥を今か今かと待つ幼鳥を見つけたら、遠くから静かにその瞬間を待ってみましょう。給餌の他に、水浴び後の羽繕いや幼鳥同士のじゃれ合いなど、見ていて飽きません。

ニッコウキスゲの群落がおもに見られるのは、おもに車山肩と富士見台というポイント。7月の上旬から中旬にかけてビーナスライン沿いの駐車場からなだらかな丘を歩いて上がるとすぐに絶景が展開します。
シカの食害から高山植物を守るため電気柵が設けられていますから、遊歩道沿いに敷設されている電線に触れないよう注意しましょう。


ヤナギランとノビタキとのコラボも楽しめる八島湿原

霧ヶ峰エリアを代表する探鳥地といえば、八島湿原もおすすめです。長い年月を経て泥炭層が蓄積して形成された高層湿原で、木道が整備された平坦な遊歩道を歩けば、約90分で湿原を一周することができます。
木道を歩いていると「ジャッ、ジャッ」とノビタキの声が聞こえてきます。繁殖期は4月下旬から9月まで。初秋にはレンゲショウマやシシウド、ワレモコウなど、可憐な植物とのコラボも楽しめます。10月には南方の東南アジアなどへ向けて旅立ちます。


特にヤナギランの群落が点在する湿原の南西部は林縁部にも隣接していて、ノビタキやホオアカなどの草原性の野鳥の他にカッコウやアオジ、ノスリなども見られます。ちなみに、湿原一帯もシカの侵入を防ぐ柵や通電している電気柵が設けられています。

ニッコウキスゲやヤナギランなどの花が見頃となる7月~8月の霧ヶ峰高原の道路は混雑します。車山肩や八島ヶ原湿原の駐車場は朝8時には満車になる程です。
そんな時期は夜半から早朝に到着できるように出発し、トイレもある駐車場で夜明けを待つのもおすすめです。朝食や昼の行動食は霧ヶ峰の最寄りの諏訪インター付近のコンビニ等で用意しておくとよいでしょう。
名古屋方面から特急「しなの」で塩尻駅まで2時間、中央本線に乗り換え上諏訪駅まで約20分。
上諏訪駅からは、白樺湖・車山高原・霧ヶ峰線路線バス(アルピコ交通)を利用し約40分、車山肩下車。
車の場合は、中央道諏訪インターチェンジから県道40号線、霧ヶ峰インターチェンジ経由で車山肩へ。諏訪インターから約30分。