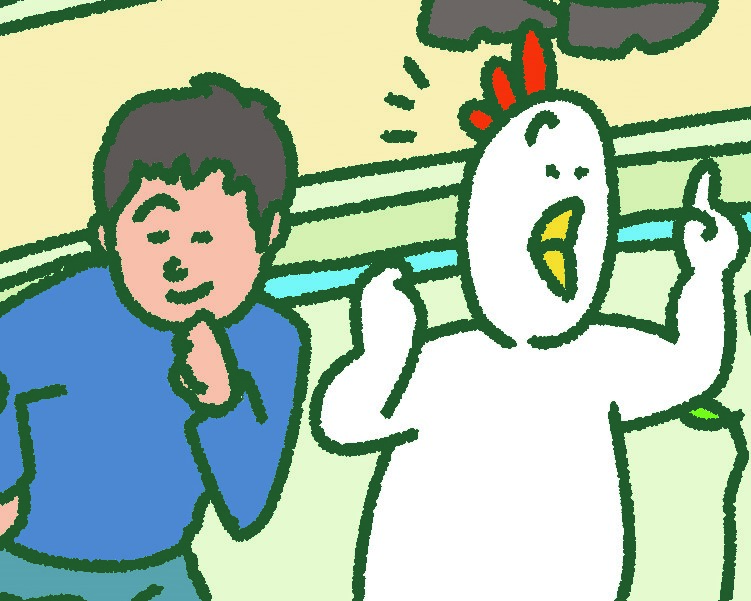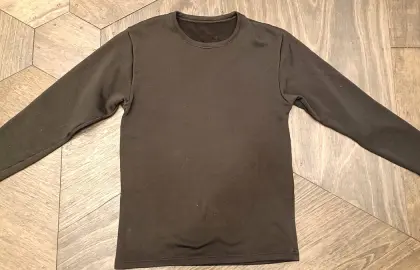ツユクサは雑草と薬草のはざまに位置している
ツユクサの基本情報と特徴

ツユクサは、ツユクサ科に属する雑草で、鮮やかな青色の花を咲かせます。
ひと口に青色と言っても、花をよく観察すると、ラピスラズリのような瑠璃色、夏の空を連想させる青色や、淡い青色というように、個体によって違いがあります。
ツユクサの開花期は5月~9月頃までと長いので、ツユクサを探す時には花を目印にすると見つけやすいです。
ツユクサの分布と発生時期

ツユクサは、沖縄から北海道まで日本全国で見ることができます。畑や空き地、道端などに生えており、街中でもコンクリートの隙間や排水溝から顔を出しています。
4月頃から芽を出しはじめ、草丈は20㎝~50㎝くらいになります。
日本人とツユクサ
ツユクサは、今から1200年以上も前の和歌をまとめた「万葉集」にも登場するほど、日本人にはなじみの深い雑草です。当時の人々は、ツユクサをどんな想いで見ていたのでしょうか。
ちなみに、万葉集の中ではツユクサではなく、月草と記載されています。現在のツユクサという名前は、月草(つきくさ)から変化したようですが、他にもホタルグサ、ボウシバナ、アオバナなどの呼び名があります。
また、多くの歴史小説を書いた作家の司馬遼太郎さんは、庭に生えるツユクサを楽しみにしていたそうです。
かつては貴重な青色の絵の具として使われていた

ツユクサの花のような色の万年筆インクがあったらと思って探したら、露草という名前のインクが市販されていました。
もちろん、インクの原料に本物のツユクサは使われていないのですが、昔はツユクサの小さな花を集めて絵の具を作っていました。
しかも、ツユクサの変種で、大きな花を咲かせるアオバナ(オオボウシバナ)をわざわざ畑で育てており、滋賀県の草津市が産地として有名でした。現在でも、草津市の花はアオバナになっています。
いくらアオバナの花が大きいと言ってもハイビスカスのような大きさではないので、手作業で1つ1つ花を摘み取る作業はとても大変だったようです。
しかも、摘み取った花から得られる色素はごくわずかで、和紙に吸わせては乾かすという工程を何度も繰り返し、青花紙(あおばながみ)というものを作っていました。そして、この青花紙を水に浸したものが、絵の具として友禅染めの下絵に使われていました。
除草するのも活用するのも7月がオススメ
ツユクサには農作物の成長を邪魔してしまう厄介な部分と、薬草や野菜の代用としてわれわれの暮らしの役に立つという両面性があります。
雑草としてのツユクサ:繁殖力・除草の必要性

ツユクサの厄介な部分は、繁殖力です。特に農地に発生すると、作物の成長に必要な栄養分を奪ってしまうので、除草する必要があります。
除草剤を散布するのが一般的ですが、鎌や草払い機で刈り取る方法もあります。刈り取りは、ツユクサが種子を付ける前の7月頃に行うと効果的です。条件にもよりますが、ツユクサの種子は土の中で20年以上も生きているので、新しい種子をできるだけ減らすことが重要です。
また、費用と手間はかかりますが、防草シートで土を覆ってしまうという手段もあります。
薬草・野草としてのツユクサ:効果と食べ方
ツユクサは薬草として、解熱や利尿の効果があるとされています。
茎先のやわらかい部分は食べることができ、江戸時代の書物にも紹介されています。また、食糧不足が深刻だった戦時中には、昭和天皇がツユクサを食べていたそうです。
ツユクサの食べ方は、おひたし、酢の物、卵とじ、そして定番の天ぷらなど様々な調理方法がありますが、美しい青色を利用した和のスイーツを紹介します。
ツユクサ色の琥珀糖を作ってみよう!

雑草を美味しく食べる方法を詳しく紹介しているMichikusaさんの「道草を食む」という本に、ツユクサの琥珀糖(こはくとう)が掲載されています。
材料は、ツユクサの花びら150個分、砂糖、寒天の粉、水だけです。水と粉寒天を加えたものを火にかけてから砂糖を入れ、その後でツユクサの花から絞った汁を加えます。
著者のMichikusaさんによると、ツユクサから絞った汁を寒天に混ぜる際には、寒天の温度をできるだけ下げておくと、ツユクサのきれいな青色が残るそうです。その後、寒天を冷蔵庫で1時間ほど冷やして完成です。
ツユクサの仲間たち
ここでは、ツユクサと同じツユクサ科の雑草を3種類紹介したいと思います。
イボクサ


イボクサの語源は、イボクサの汁を付けるとイボが取れることから名付けられたという説がありますが、実際に効果があるかは不明で、薬草としては使用されていません。花は薄紫色で、中心よりも輪郭の色が濃くなっています。
イボクサは湿地を好む雑草なので田んぼによく生えていますが、稲の成長の邪魔になるために、水田の有害雑草になっています。
トキワツユクサ


別名をノハカタカラクサ(野博多唐草)といい、白い花を咲かせます。元々は、鑑賞用として海外から持ち込まれましたが、野外に広がり雑草化しました。
以前に、トキワツユクサを押し花にするために1週間ほど乾燥させたことがあったのですが、それでも枯れないくらい乾燥に強い雑草です。また、茎を切って水の入ったコップに挿しておくと根が生えてきます。
ムラサキツユクサ


ツユクサよりも大型で、草丈は30から60センチくらいになります。鑑賞用にも栽培されているので、庭の片隅で見かけることがあります。青や紫色の花を咲かせます。
雑草と薬草の境界を知ると植物の見え方が変わる
雑草には役に立つ部分と、厄介者の部分が共存しています。
現代では、雑草の厄介者の部分が目立ちますが、雑草を普段の生活の中に取り込むことで、昔の人の生活の知恵に触れたり、雑草の新たな一面を知ることができます。
ただ、雑草の中には有毒な個体もあるので、知識が無いままに食べるなどしてしまうと危険なので注意してください。なので、図鑑で調べたり、薬草や植物に詳しい人に教わりながら、雑草と向き合ってみてはどうでしょうか?