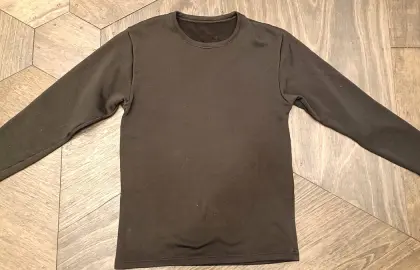(出典)photoAC
トンボの食べ物はいったい何?

トンボの食べ物は、幼虫(ヤゴ)期と成虫期で異なります。まずは、それぞれの時期の食べ物を見ていきましょう。
幼虫(ヤゴ)の食べ物は水中の小さな生き物
ヤゴは肉食性で、以下のような水中にいる小さな生き物を食べて大きくなります。
- ミズムシ
- ボウフラ
- アカムシ
- イトミミズ
- オタマジャクシ
- 仲間のヤゴ
小さいうちはミズムシやボウフラを、少し大きくなるとアカムシやイトミミズのように、成長の度合いに応じて食べ物のサイズも大きくなっていくのが特徴です。
さらに大きくなると、メダカやオタマジャクシを食べることもあります。時には、仲間のヤゴを食べる『共食い』も見られます。
成虫の食べ物は小さな昆虫
成虫の食べ物は、主に空を飛び回る昆虫です。
- ハエ
- 蚊
- カゲロウ
- ガ
- アブ
空を俊敏に移動できるトンボは、ハエやガなどを空中で捕えるのが得意です。一方で、クモやバッタなど、飛ばない虫を食べることも分かっています。
成虫のトンボは、昆虫の中でも屈指の強さを誇り、自分と同じくらいの大きさの昆虫も捕食対象です。日本最大級のオニヤンマは、スズメバチを捕食するケースもあります。
また、トンボは肉食性なので、野菜や樹液は基本的に食べません。
トンボは飼える?飼育方法と注意点
ヤゴは比較的飼育しやすく、成虫も難易度は上がりますが飼育は可能です。ヤゴと成虫に分けて、それぞれの飼育環境の作り方や餌をあげるときのポイントを解説します。
ヤゴの飼育方法と餌のやり方
ヤゴの飼育環境を作るには、以下のアイテムを用意しましょう。
- 飼育ケース(ふたは不要)
- 割り箸または木の棒
- 水
- 落ち葉・小石・水草
飼育ケースがなければ、ペットボトルを横に寝かせ、水平に切ったものでも代用できます。ケースには4cm程度を目安に、ヤゴの体がすっぽり入るくらいの水を入れましょう。
割り箸や木の棒は、ヤゴの隠れ家になるだけでなく、羽化するときにつかまるために必要です。
餌のイトミミズやアカムシは、熱帯魚店や釣り用具店で購入できます。水が腐らないよう、餌の食べ残しは小まめに掃除しましょう。
成虫の飼育方法と餌のやり方
前提として、トンボの成虫の飼育難易度は高めです。成虫は飛び回って生活しており、狭いケースの中で飼育するのは生活スタイルに合っていないためです。それでも飼育したい場合は、以下の環境を用意してあげましょう。
- 大きくて密閉性のある虫かご
- 止まり木
基本的に餌は生きているものを与えるため、トンボはもとより餌が逃げないように密閉性のあるケースである必要があります。餌は先述の虫を捕まえてくるか、難しい場合は市販のミルワームやサシ虫などを与えましょう。
ずっと狭いところで飼い続けると、羽を傷つけてしまう恐れがあるため、1日1回は自由に飛び回らせるか、観察が終わったら逃がしてあげるのが親切です。
餌は生きたままあげるのが基本
ヤゴでも成虫のトンボでも、餌は生きたままあげるのが基本です。トンボは、動くものを餌と認識するため、死んだ虫を与えても食べようとしません。
どうしても生きている虫を与えるのが難しければ、餌を動かして生きているかのように見せましょう。トンボに近づけてやると、食いついてくれる場合があります。
トンボは大食いのため、餌は十分に与える必要があります。少し多めに与えてみて、食べ残すようであれば量を調節するなど、適切な分量を確かめてみましょう。
トンボの一生と成長の過程

ここでは、トンボの一生を、羽化までとそれ以降に分けて解説します。トンボ観察の事前知識としても、きちんと押さえておくのがおすすめです。
卵~羽化まで
一部を除いて、ほとんどの種類のトンボは秋に卵が産まれ、卵のまま冬を越します。春になると、卵からヤゴがかえります。
ヤゴは水中で成長しながら、9~13回程度脱皮を繰り返しますが、成虫になるまでの期間は種類によって大きく異なるのが特徴です。早いと約1カ月、長いと最長8年程度幼虫期を過ごす種類もあります。
十分に成長すると、水からはい上がり羽化を始めます。羽化の仕方には、直立型と倒垂型(とうすいがた)の2種類があり、種類によって型が決まっています。
成虫期~産卵
成虫になると、約3カ月地上で生活します。しかし、途中で鳥などの天敵に食べられてしまう個体もいるため、どのトンボも3カ月生きられるわけではありません。
種類によって異なりますが、主に8〜11月ごろにかけて活動し、11月ごろになると産卵して寿命を終えます。トンボは、交尾中も飛行を続けるのが特徴です。
産卵の方法は種類によりさまざまで、飛びながら水面に尻尾を打ち付けたり、飛行中に卵をばらまいたり、植物に止まって産み付けたりなどが知られています。
日本にいる代表的なトンボ

最後に、日本にいる代表的なトンボを3種類紹介します。自然の多い場所では、よく見られる種類ばかりです。秋の風物詩としても知られる、トンボについての理解を深めましょう。
オニヤンマ
オニヤンマは、日本最大級の大きさを誇る種類です。鬼のような顔と、黄色と黒の体色が『鬼のふんどし』をイメージさせることから名付けられたといわれています。
トンボの中でもヤゴの期間が長いことで知られ、成虫になるまでの期間は約3~5年間です。しかし、成虫の期間は約1~2カ月とはかなく、太く短い成虫期を過ごします。
持ち前の顎の力で、トンボの中でも大型の餌を捕食するのも特徴で、かまれると出血の可能性もあるので注意が必要です。そんな強さを誇るオニヤンマですが、東京都では絶滅危惧II類に分類されています。
アキアカネ
童謡『赤とんぼ』で知られ、多くの人になじみのある種類です。夏場は標高の高い場所で過ごし、秋になると平地に降りてくるため、都市部に住んでいる人にとっては秋に見かける機会が多いでしょう。
トンボの中でも季節による移動距離が長いため、体力を蓄えるために多くの昆虫を食べます。作物の害虫も食べてくれることから、益虫としても愛されています。
しかし、昨今は殺虫剤の使用により、急激に個体数を減らしている状況です。『赤とんぼ』の風景を守るためにも、農法の工夫による保護が期待されます。
ギンヤンマ
ギンヤンマは、子どもに人気の種類の一つです。腹の裏に、銀白色の模様があることが名前の由来です。頭と胸は黄緑色、腹は茶褐色で、胸と腹の境目の色がオスとメスで異なります。
オスは明るい青色であるのに対し、メスは黄緑色をしているため、オスとメスの見分けもしやすくなっています。成虫の活動時期は、4~11月ごろと比較的長めです。
日本全土で観察できる身近な存在ですが、昨今は外来魚によって個体数を減らしています。長野県と高知県では準絶滅危惧種に指定されており、保護が求められます。
まとめ

トンボは肉食性の昆虫で、幼虫のヤゴは水中のボウフラやミズムシ、成虫は蚊やハエなど小さな昆虫を捕食します。ヤゴは比較的飼育しやすく、水槽や餌の準備があれば家庭でも飼育が可能です。
一方で、空を飛び回る成虫の飼育の難易度は高めで、観察目的での一時的な飼育に向いています。ヤゴも成虫も、餌は生きた状態で与えるのがベターです。
日本では、オニヤンマ・アキアカネ・ギンヤンマなどが有名な種類です。トンボの生態や特徴を知り、自由研究や趣味での飼育などに役立てましょう。