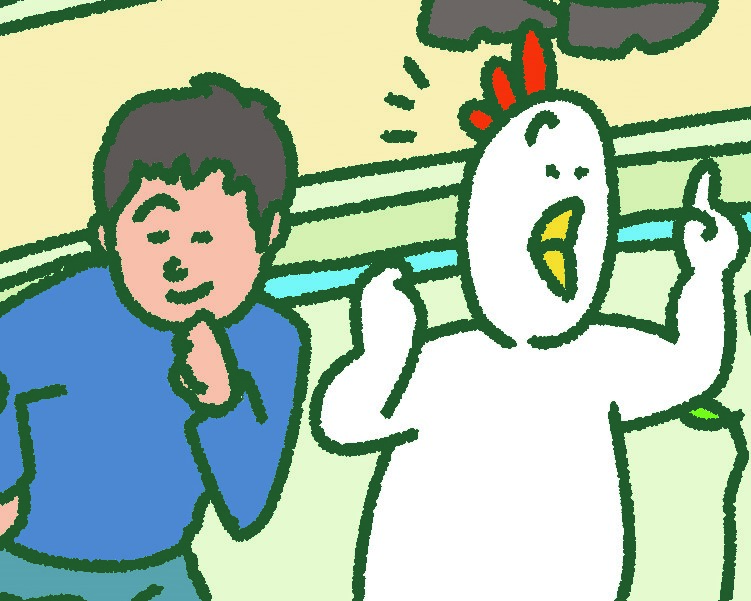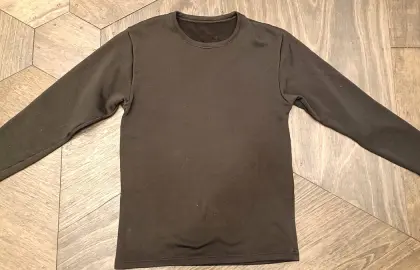冒頭の写真はハマヒルガオです。
海辺の自然散策の魅力|海辺で出会う雑草の世界へ

海辺の植物は雑草?
雑草の定義は複数ありますが、その中に「人の生活圏に非意図的に進入した植物」を雑草とするというものがあります。
海辺は農地や道路、住宅地と比べるとなじみの薄い場所ですが、一応、人の生活圏の一部なので、ここでは海辺に暮らす植物を雑草と呼ぶことにします。
ちなみに、海辺の植物を海浜植物と呼ぶこともあります。また、海の中の話になりますが、コンブやワカメのような海藻は、英語でシーウィード(Seaweed)、つまり海の雑草ということになります。
海辺の自然環境が育む多様な雑草
植物にとって、海辺はとても特殊な場所です。それは、常に潮風にさらされるためです。多くの植物にとって塩は有害で、塩のせいで野菜が枯れることもあります。
また、砂浜は乾燥しやすい上に、裸足で歩くとやけどしそうになるくらい高温になります。いくら強いと言われる雑草でも、このような環境に耐えられる種類は限られています。
海辺に生える雑草の特徴

海辺の雑草は、一見すると他の雑草と似たような見た目をしていますが、葉を指で触ると分厚い構造をしていることが分かります。これは、葉に水を蓄えているためです。
また、葉の乾燥や強い光を防ぐために、葉の表面がツヤツヤ(日焼け止めみたいなものです)しています。その他にも、強風で倒れないように、横に這うように伸びたり、砂の表面が乾燥しても大丈夫なように深い根を張り巡らせています。
海辺の雑草を観察する楽しみとは
海辺の雑草は、生育可能な個体が限られているので、覚えるのがとても簡単です。農地や空き地の雑草の数と比べると、各段に少なくなっています。
そして、海辺の雑草をよく観察すれば、ぶ厚い葉や、砂に埋もれながらも横に広がる様子など、農地や街中に生えている雑草とは異なる姿に触れることができます。
花が目印になる海辺の雑草
ここでは、きれいな花を咲かせる雑草を紹介します。花を目印に探してみてください。
ハマヒルガオ


ヒルガオ科のハマヒルガオはピンク色の花を咲かせますが、中には白い花を咲かせるシロバナハマヒルガオも存在します。
また、同じヒルガオ科のアサガオはフェンスや木などに絡まりながら上に伸びていきますが、ハマヒルガオは横にはうようにして成長します。
ハマエンドウ

マメ科のハマエンドウは、紫色の花を咲かせます。こちらも、ハマヒルガオと同じように、横に広がっていきます。
海辺でよく見る雑草ですが、以前、海から100キロも離れた内陸の河川敷で見つけたことがあります。これは、昔、海から来た船によって持ち込まれたハマエンドウの種子が定着したことに由来するようです。
コマツヨイグサ

北アメリカ原産で、明治時代頃に日本にやってきた外来種です。月見草(メマツヨイグサ)の仲間で、同じ黄色い花を咲かせます。
ただ、月見草は草丈が100センチくらいになりますが、コマツヨイグサは他の海辺の雑草と同じように、横に広がっていきます。
食べられる海辺の雑草
海辺の雑草の中には食べられる雑草も存在します。大きくなると硬くなるので、茎や葉が硬くなる前が食用に適しています。
ハマボウフウ


ハマボウフウ(浜防風)は開花前の5月頃、軟らかい茎や葉を食べることができます。刺身のつまとして使われることが多く、その他の調理方法は、おひたしや酢の物、天ぷらがあります。また、ハマボウフウの根は解熱や鎮痛薬として使用されています。
ただ、ハマボウフウは自生地が減少していて、自治体によっては絶滅危惧種に指定されているので、過度な採取はしないようにしてください。
どうしても食べてみたい方は栽培されているハマボウフウがあるので、そちらを購入するのがおすすめです。
オカヒジキ

オカヒジキは葉に弾力があり、多肉植物のような見た目をしています。シャキシャキした食感が特徴で、おひたしや和え物、酢の物などにして食べることができます。ゆで過ぎると独特の食感が消えてしまうので、火を通し過ぎないのがコツです。4~6月頃のものが食用に適しています。
ハマボウフウと同じく栽培されたものが流通しているので、海辺まで行かなくても入手することができます。オカヒジキの種子は販売されているので、畑で育ててみてはどうでしょうか?
その他の海辺の雑草
ちょっと地味な雑草も紹介します。
ハマアカザ


農地や空き地でよく見るシロザによく似ていますが、ハマアカザの葉はシロザより厚みがあります。また、シロザは2メートル近く育ちますが、ハマアカザは50センチ前後までしか大きくなりません。
また、シロザは問題になるほどたくさん生えてきますが、ハマアカザは一部の自治体で絶滅危惧種に指定されています。
コウボウムギ

コウボウムギは、筆の代用として使われたことからフデクサ(筆草)という別名があります。
また、弘法大師(空海)が筆を浜に投げ捨てたものが草になったとする伝承もあり、日本人とは昔から関わりの深い雑草です。そして、種子は麦と似ています。
海辺の雑草と自然環境との関わり
海辺に生えている雑草には、重要な役割があります。
砂浜・海岸の植生が果たす役割

防風林というと松を思い出すかもしれませんが、海辺の雑草も、横にはうように伸びたり、深い根を張ることで砂を固定し、飛散することを抑えています。
江戸時代に、栗田定之丞(くりたさだのじょう)という久保田藩(秋田県)の武士が砂浜の植林を行ったのですが、中々上手くいきませんでした。そこで、砂浜にムシロをかぶって寝るほど執念深く観察を続けた結果、壊れたワラジの陰に生えた雑草を見つけました。
そして、この雑草がヒントとなり、いきなり松を植えるのではなく、最初に砂浜にたばねたワラを埋め込み、小さな木を順番に植えていき、最後に松を植えるという手法を見出し、大規模な植林に成功しました。
絶滅危惧種と保全の重要性
最近では、海流が変化したせいか砂浜が減少しており、海辺に生育する雑草の中には絶滅危惧種に指定されているものがあります。
このため、砂浜を歩く際には足元の雑草をできるだけ踏まないようにしたり、砂浜での焚火や車を乗り入れることは避けるようにしてください。
さいごに
海辺の雑草は、人間の生活の邪魔をしている訳ではないので、我々も雑草達の生活を邪魔しないような関わり方をしていきたいですね。
そのためにも、砂浜に埋もれながら育つ海辺の雑草をよく観察してみてください!きっと、けなげに育つ雑草達に愛着がわいてくるはずです。