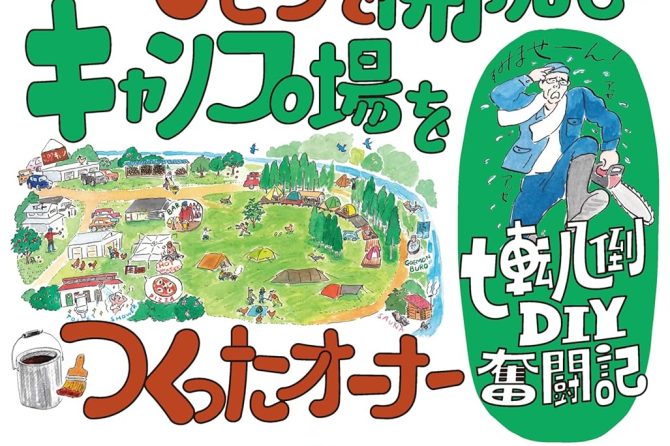広島県尾道市の「しまなみブルワリー」は、オープンからまだ1年半の新しいブルワリーだが、ラガー好きには知られた存在。究極のラガーを求めて立ち上げたオーナーでありヘッドブルワーの松岡風人(かざと)さんにインタビューした。
ピルスナーに魅せられた男が満を持して設立
2023年3月に醸造開始した「しまなみブルワリー」。代表の松岡風人さんは、設立前の14年間、山梨県の八ヶ岳ブルワリーでビールを造ってきた。
2020年に世界的なビールコンペティション「ワールド・ビア・アワード」で、自身が手がけた3つのラガーが金賞を受賞したのを機に、独立に向けて準備を始めた。
松岡さんは子どものころから動物や昆虫など、とにかく生き物が好きだったと言う。獣医を目指して東京農業大学を受験したが、入学したのは醸造科学科。「父の勧めで受けたんですよ」と言うから人生、何がどう転ぶかわからない。東京農大は日本で唯一、醸造学を学べる大学で、酒造りがカリキュラムに入っている。
「醸造は微生物が行なうもの。もともと生物好きなので微生物にも興味がありました。いろいろなものを分解する微生物はゴミの分解にも欠かせない存在。将来の地球環境を思うと微生物の研究は面白い」。そんなふうに考えて、松岡さんは醸造学の道に進んだ。

酒蔵や醤油蔵の子弟の多い学科で醸造を学ぶうち、ビールの道に選んだのは、単純に「ビールが好きだから」だった。
就職先には老舗のビールメーカーも考えたが、「大手だとビール造りのすべての工程に関われないかもしれない」と思ったのだそうだ。一から十まで、ビール造りのすべてを身につけたかった。
2007年、松岡さんは山梨県の八ヶ岳ブルワリーの門を叩いた。当時の醸造長は、キリンビールで「一番搾り」や「ハートランド」の開発に携わってきた山田一巳氏。松岡さんは学生時代に山田氏の書いたビール職人の本を読んで感銘を受け、尊敬していた。醸造所の人員募集はなかったが、それでも八ヶ岳ブルワリーの母体のレストランでアルバイトとして働き始めた。
清里には縁もゆかりもなかったため「ここでやっていけるかちょっと迷った」と言う松岡さんだが、ラガー造りを身につけたい、その思いが勝って山田醸造長に“弟子入り”。徹底的にラガーづくりを教わった。
「酵母は生き物なので、毎日会話しろ」という山田氏の教えを受け継ぐ。もとより醸造学を学んできだ松岡さん、「ぼくはビールは生物だと思っています。だからビールと対話しながら造っています」と話す。
ビールは大きく分けてラガーとエールがある。発酵に使う酵母の違いで熟成工程が異なり、ラガーは1か月半以上、エールは2〜3週間の熟成で出来上がる。日本の大手ビールメーカーの造るビールの多くがラガーである。これに対して、日本のクラフトビールブルワリーの造るビールの多くがエールである。
理由のひとつはコストの問題だ。ラガーはエールより熟成期間が2倍以上、つまり製造コストも2倍になる。しかし、2倍の値段で売れるわけではない。小さなブルワリーでは扱いにくいわけだ。
そもそも、ラガーを造るには高い技術が求められる。松岡さんはその難しさと魅力を次のように語る。
「低温でじっくりと発酵させていくので、かなり忍耐強さが求められます。人間のペースでやってしまうと、すぐにダメになる。だからビールは酵母ファースト。酵母と対話しながら造ります。たくさんの工程がありますが、そのひとつでも踏みはずすとダメになるので緊張感もあります。
ラガーは面白い。繊細な味なので失敗するとすぐわかる。だからスキルを証明するにはうまいラガーを造るのが一番。うまいラガーは自分の名刺代わりになります」
アイスクリームのスムージーみたいなビール?
独立するにあたり、主力は当然ラガーと決めていた。八ヶ岳ブルワリーに在籍した14年間で、ラガーのほか、ペールエールやヴァイツェンなど、ひととおりのビールスタイルは身につけていた。それでも「やっぱりラガーがいちばん面白い」。その考えに変わりはなかった。
しまなみブルワリーは2023年3月、クラウドファンディングを利用してビール醸造を始めたが、この時のラインナップが独特だ。
まず「ファーストラガー」と「ストライクピルスナー」。それからアイスクリームを使った「スムージーサワーエール」を2種。前者の2つはラガーの王道ピルスナーだが、スムージーサワーエールとは何ものだろうか?


スムージーサワーエールとは、アイスクリームに果物のピューレを加えたスムージーなサワーエール。この「しまなみキャット」は現在、麦芽と糖類で醸造した発泡酒をベースにした「ハード・アイスクリーム・セルツァー」というスタイルに進化している。レモンやグレープなど使用するフルーツを変えてさまざまなフレーバーを展開中だ。
クラフトビールだから「ハードセルツァー」の可能性は無限大!
ところで、「ハードセルツァー」というジャンルをご存知だろうか。甘みの少ない炭酸アルコールともいうべきお酒で、5年ほど前にアメリカで大ヒットした。日本にも数年前に上陸し、国産もあるのだが、あまり広がってはいない。
しまなみブルワリーは、ビール造りのスキルを生かして、アイスクリームを使ったハードセルツァーを開発した。なめらかでフルーティーで、お酒と知らなければゴクゴク飲んでしまいそうなおいしさ、爽やかさ。おそらく、日本でも世界でも知られていないスタイル。新ジャンルと言っていいお酒だ。
それにしてもなぜ「しまなみキャット」のようなスムージーなお酒を製造しているのかというと、「当初からラガー1本では経営的に厳しいかもしれないという懸念があった」(松岡さん)からだ。
実際、醸造を開始してひと夏を越えたころ、「やっぱりラガーが主力だと、そこそこキツイかな」という状況。レモンサワーテイストのハードセルツァーの開発に取りかかった。
そうして生まれた「しまなみ超レモンサワー」は、レモンの酸味と酵母由来の自然なアルコール感のあるハードセルツァーだ。既存のそれとも、缶チューハイとも違う味わい深さがある。価格が大手製品とはだいぶ違うので単純な比較はできないが、大手の論理に組み込まれないクラフトビールブルワリーだからこそできた味ではないか。
現在、「しまなみ超レモンサワー」はブルワリーの主力製品のひとつに成長している。
「ラガーだけ造っていると玄人好みのブルワリーと思われて、あまり広がらないんですよ。クラフトビールは、今まで馴染みがなかったお客さんにこそ好きになってもらいたい。ビールの技術を使ったアイスクリームのビールやレモンサワーが、うちのラガーを知るきっかけになればいいなと思っています」
ラガーとハードセルセルツァーの2本柱であることが、しまなみブルワリーの強み。ラガーを追究するために、ラガー以外のクラフトビールも追究する。ビール造りのスキルがあるからできることだ。
「ハードセルツァーの可能性は無限大」だと松岡さんは言う。こうして新しいお酒が、クラフトビールのブルワリーから生まれてくる。
広島が誇るブルワリーを目指して
地元の広島でビール造りをしたいというのは、松岡さんがビールの道に入った当初からの考えていたことだった。
「まずは広島を代表するブルワリーになりたいと思っています。広島の人に自慢してもらえるようなビールを造りたいし、そういうブルワリーでありたい。そのためにも醸造量を増やしていかないといけないですね」という松岡さんの言葉からは広島の先にある世界を見据えている様子がうかがえる。
現在、醸造設備の増設を計画している。現在のタンク容量は3000リットル。ラガーは熟成にタンクを1ヶ月半ほど占領するので、3000リットルではぜんぜん需要に追いつかないという。尾道という観光地に立地しているが、まだタップルームはない。醸造量が少ないために、タップルームで提供できるビールが確保できないからだ。
ただ、ブルワリーの近所にある老舗の酒屋、向酒店が、ラガーやレモンサワーを扱ってくれている。樽生も提供しているというから、まるでタップルーム代わりの酒屋さんだ。サイクリングコースで知られる「しまなみ海道」の入り口もブルワリーから近い。サイクリングのゴールに向酒店を目指すというのもアリではないか。
国内のブルワリーがこの春、900か所を越えた。今後、長続きするブルワリーは自ずと限られてくると思う。すでに飽和状態に見えるクラフトビール界だが、ラガー主力のブルワリーがどのように生き残っていくのか。日本でどんなラガーが生まれるのか。しまなみブルワリーに注目していたい。

●しまなみブルワリー 広島県尾道市久保1丁目6-15-2
https://shop.shimanami-brewery.com