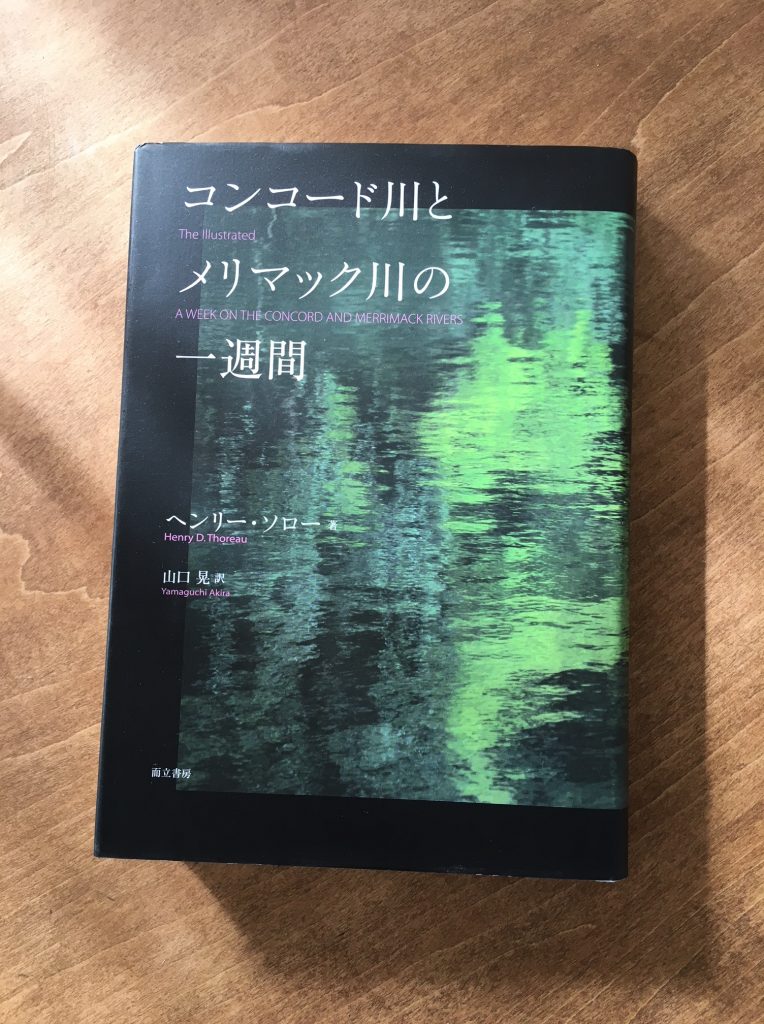アウトドア好きにとって、ソローの『ウォールデン 森の生活』は必読の古典です。
しかし、この本、読むと必ず眠くなる!
1980年代のアウトドア雑誌『BE-PAL』の書評欄には、ソローの『森の生活』を評して、とにかく眠くなる、言っていることはわかるんだけど、とにかくやたらめったら理屈っぽいん、どうしても眠くなるんだよナァ……、てな評が書かれていたように記憶しております。
かくいうb*p編集部員のわたくしも、『ウォールデン 森の生活』には20代のころ3度ほどチャレンジして、すべて第1章「経済」の途中で挫折しました。いや、ほんとに眠くなるったら、ありゃしないんです。
なんですが、その後、十数年がたったうららかな秋の日に、とある大先輩(フライフィッシャーマン)とコーヒーをのみながら雑談をしているときに、何かの話題のついでに、ふとソローの話が出てきたのでした。
その人は、なんともいいい笑顔でぽつり、つぶやいたのです。「若いころに読んだ、ソローの考え方には、けっこう影響を受けたんだよね」と。好きなことをやって生きていくことについて、そのすばらしさと、大変さについて、その人はとつとつと語ってくれました。テーブルの上には、窓の外の木の影が揺れていました。そのとき、ふと思ったのです。ああ、ついに時期が来たのだと。『ウォールデン 森の生活』を、いよいよおれも読まなくてはならないぞ、と。
じつは、その後も何度か読み直そうと試みたことがあって、ほろ酔いのときに適当に開いたページに書かれていたエピソードが心に残っていました。貧乏人になぜ服を恵んでやらないのか、という内容で、慈善事業よりも、自分ができることをやることが大事という、ソローの考え方が、毒味もある筆致で書かれていました。
それは、こんなふうに始まります。
《あなたが貧しい人を助けようというのなら、本当に欲しているものを与えるのが当然です。与える人の生き方を押し付けては助けになりません。あなたに与えるお金があっても、単に与えることが解決になるでしょうか。むしろあなたが自分で使うべきです。(中略)
私は、ウォールデン池の氷を切り出す、アイルランド人のむさくるしい労働者に同情したことがあります。ところが私はといえば、アイルランド人よりかすかにこぎれいで、当世風の衣服を着ていただけで、いつも寒くて震えが止まりませんでした。ある酷寒の日に、アイルランド人のひとりが池に落ちました。私の家に避難したその人は、三本のズボンと、たしかに汚れた二本の長靴下を身に着けていました。私はその人に上着を提供しようと申し出たのですが、断られました。その人は下着を重ね着していたので、十分だったのです。きれいな水に浸かることは、ちょうどよい水浴だったでしょう。私は、少しは自分に目を向けたほうが良さそう、と思い直しました。その人のために古着屋を買い占めるより、自分のために一枚のフランネルのシャツを買うほうが、よほど慈善になります。》(ヘンリー・D・ソロー著・今泉吉晴訳『ウォールデン 森の生活』)
一見、むさくるしい格好をしているアイルランド移民の労働者は、靴下や下着を重ね着するという方法で、じつに機能的に暖かさを保つための着こなしをしていました。真冬に氷を切り出すというハードな仕事をしているだけあって、ソローなんかよりもよっぽど、寒さ対策がしっかりできていたのです。
ソローが素敵なウールの上着を提供してくれたとしても、氷を切り出す仕事には、むしろ邪魔になったでしょう。
とはいえ、「人のために古着屋を買い占めるより、自分のために一枚のフランネルのシャツを買うほうが、よほど慈善になります」というのは、いったいどういうことなのか?
ここで、ソローは「社会の富」を持ち出します。
《私の隣人でも、一部の人たちは貧乏な人を台所で使って、それが思いやりだと言っています。でも、自分が台所で働くほうが、ずっと思いやりのある行為ではないでしょうか? 収入の十分の一を教会に払っていると自慢する人がいます。あなたがもしその考えなら、十分の九を教会に払ったほうがいいでしょう。けれどもそんなことをしたら、私たちの社会には富の十分の一しか回ってこないではありませんか。このようなお金の流れを、財産をたまたま持った人の思いのままに任せていいのでしょうか。》(ヘンリー・D・ソロー著・今泉吉晴訳『ウォールデン 森の生活』)
お金や仕事を恵んだり寄付したりするよりも、自分で働き、自分でしっかりお金を使ったほうが、社会に富が回って、全体が豊かになるのではないか。
このような考え方には、ソローが当時批判的に読んでいたアダム・スミス『諸国民の富』の影響が伺えるように思います。ソローは、スミスの「分業」論を批判しましたが、個々人がその能力の限り働き、エゴイスティックに、自己本位でお金を使ったほうが、結果的にみんなが豊かになる、という『諸国民の富』の考え方を共有していました。
とはいっても、ソローは、弱い人を助ける行為自体は大切だと考えます。
《なるほど、溺れるものがいれば、助けるのが当然で、自然です。でも、助けたのなら、すぐに靴の紐を結んだほうがいいでしょう。あなたはあなたの時間を作り、自由な仕事をするのです。(中略)まず、私たち自身が最初に、自然と同じように簡素に、純真に、元気はつらつと生き、表情を暗くする雲を打ち払い、自然の活力を十全に取り込もうではありませんか。貧しい人たちの監視人にとどまることなく、世界にとって価値ある人になるよう、励もうではありませんか。》(前掲書)
なるほど、へんくつだけど、おもしろそうな人ではありますよね。
博愛や慈善活動も大事だけれど、だからこそ、まずは自分のことを、というのがソローの考えなのだと私は理解しました。これはこれで筋が通っていると思いました。
で、意を決して、毎日すこしずつ寝る前に読み始めたわけです。
新訳の『ウォールデン 森の生活』はですます体で、読みやすかったです。たしかに、ときどき眠くはなるのですが、おかげで『ウォールデン 森の生活』を読む日々は、安眠の日々でもありました。
思想書、というふうに考えていましたが、読んでみると、淡々とした自然描写あり、お金や読書、人生の意味に関する深い話があり、湖の生態系についての自然科学的な洞察があり、傍線を引きたくなる圧倒的な名言がある、ジャンル分け不能な、まさに森のように深く豊穣な本でした。
読み継がれる160年前の古典『森の生活』
ソローは、いまもなお、世界中で読まれ続けています。『ウォールデン 森の生活』の翻訳は、最新訳の小学館文庫判(今泉吉晴・訳)のほか、岩波文庫、講談社学術文庫と3つの翻訳があり、いずれもロングセラーになっています。
本国アメリカでは、有名な映画にも登場しています。ロビン・ウィリアムスとイーサン・ホークが主演した1989年の映画『いまを生きる』では、ロビン・ウィリアムス扮する国語教師が学生時代に作った「デッド・ポエッツ・ソサエティ(死せる詩人の会)」の合い言葉が、ソローの『ウォールデン 森の生活』からの引用(私は生きることの真髄を心ゆくまで味わいたい)でした。
また、『ウォールデン 森の生活』は、150年以上前に刊行された古典というのにとどまらず、非常に現代的な読み方もできる本です。自然の中で最小限の生活道具とともに暮らし、独自の哲学をつむぎだした、その文武両道的な営みは、昨今の「ミニマリスト」の源流といっていいかもしれません。
2017年の初頭、文化人類学者で東京外語大学大学院教授の今福隆太氏が『ヘンリー・ソロー 野生の学舎』で読売文学賞(随筆・紀行部門)を受賞しました。旅する文化人類学者ならではのみずみずしい感性でソローを読み直し、ソローの可能性を拡張したエッセイ集です。非常にすばらしい本だと思います。
また、マイケル・サンデル教授の「ハーバード白熱教室」で話題になった政治哲学のジャンルでも、ソローは重要な思想的源流です。最近出版された神島裕子・立命館大学教授の『正義とは何か』(中公新書)には、リバタリアニズム(自由至上主義)の章でソローに触れており、他者の考え方に寛容なリベラルな、新しいリバタリアニズムの可能性について言及があります。ソローを、政治哲学の新しい可能性として読むと、どのような地平が開かれるのでしょうか。
ガンジー、キング牧師に力を与えた「市民的不服従」の思想
ソローは、『市民の反抗(市民社会への反抗)』という晩年の講演で、監獄にぶちこまれた1846年7月の経験について語っています。奴隷制とメキシコへの侵略戦争に反対する意図で、税金の不払いを続け、町の監獄に一晩だけ収監されたのです。ウォールデン湖畔の小屋で『森の生活』をはじめて1年がすぎたころのことでした。
ソローの家族や友人たちは、みな奴隷制やメキシコ戦争に反対しており、当時ソロー周辺で共有されていたリベラリズムのひとつのあらわれとして、この収監事件が起きたのです。
ちなみに、ソローのこの行為・考え方は、「市民的不服従」(Civil Disobedience)と呼ばれて後世に絶大な影響をおよぼしました。以下は、H.D.ソロー著『市民の反抗 他五編』(岩波文庫・品切れ)の翻訳者・飯田実氏による「市民的不服従」の要点です(巻末の「解説」から引用)。
■1:法律や政策が、個人の良心(より高い道徳的法則)と矛盾をきたすような場合には、前者(法律・政策)よりも後者(個人の良心・道徳的法則)が尊重されるべきである。
■2:政府がいちじるしく正義の観念にもとるような「暴政」に走った場合には、市民は納税拒否といった平和的な手段に訴えて政府に抵抗する権利を有する。
つまり、良心やより高次元の正義にかなっている場合に、法の施行者に反対の意図を表すために、あえて税金を払わないでよい。そのような市民のピースフルな意見表明行為が、ソローの「市民的不服従」なのでした。
「市民的不服従」の考え方は、抵抗運動や独立運動の精神的支柱になっていきました。マハトマ・ガンジーの独立運動や、第2次世界大戦時の反ナチのレジスタンス闘争、マーティン・ルーサー・キングの公民権運動、1960年代後半のベトナム反戦運動や、2011年のウォール街選挙運動などを支えたのもソローの「市民的不服従」でした。非暴力主義でイギリスからの独立を勝ち取ったガンジーは、肌身離さずソローの本を持ち歩いていたそうです。
ソローは、「個人の権利」をなによりも大切にした個人主義者でしたが、自分のことばかり考えていた孤独な人だったわけではありません。社会的正義など、より高次の目的のために戦う反骨者であり、奴隷制や侵略戦争に強く反対するリベラリストだったのです。
「山登り」が好きだったソローとエマソン
古典とは「可能性」です。今の視点で読み直し、過去と対話することで新しい知見が得られるというのが、古典の魅力だと思います。
b*p編集部員のわたくしも、ようやく『ウォールデン 森の生活』を読みおえて、いろいろと触発されたのですが、その感動をなかなか言葉にすることができずにいて、もんもんとしておりました。このまま終わりにしたくはありませんでした。
ソローとはどんな人だったのか?
『ウォールデン 森の生活』の現代的な意義とは何なのか?
それを知るために、2018年10月5日、東京・品川で開催された「日本ソロー学会」の全国大会に出かけました。
「日本ソロー学会」とは、1964年に前身の「ヘンリー・ソーロウ協会」として設立された、英米文学研究者による学会です。日本屈指の歴史を誇り、全国各地の120人以上の大学教授や研究者たちが、ソローの文学・思想をはじめとして、同時代の作家ラルフ・エマソン、ナサニエル・ホーソーン、ルイザ・メイ・オルコットなどの作家を研究対象として、アメリカの文化史を考察してきました。その学会の年に一度の全国大会にて、『ウォールデン 森の生活』の翻訳者・今泉吉晴先生が特別講演をするというのです。これはもう、なんとしても聴講しに行かなくては!
「日本ソロー学会2018年度全国大会」の会場は山手線大崎駅からほど近い立正大学の大会議室。今泉先生の講演の前に、さまざまなプログラムがありました。
まずは、ウィスコンシン大学大学院生・小椋道晃さんによる研究発表からスタート。「ソローとケルアックにおける〈私〉語りについて」という、なんとも気になるテーマです。ソローはアメリカ文学の祖であるとともに、ケルアックと同様に、新しい語り文体を生み出した革命家でした。
その後、東北文化学園大学・祓川信弘先生の「『マメ畑』と農書」についての研究発表、慶應義塾大学名誉教授・山本晶先生の「エマソンのホイットマンあて最初の書簡を邦訳紹介した白樺派の二人および関連する事実」という研究発表につづいて、シンポジウムが開催されました。
テーマは、「エマソン、ソローと登山」。
ソローと、ソローの師匠であるエマソンは、登山を好み、しばしば登山旅行をしていたようなのです。そうだったのか!
『ウォールデン 森の生活』にも、次のような一節があります。
《これまで私が持った家は、小さなボートとテントだけでした。私は夏にテントを持って小旅行に出かけました。そのテントは、今も私の屋根裏部屋に丸めてしまってあります。ボートは人の手から手へ渡り、時間の流れの彼方へ下ってしまいました。》(今泉吉晴訳『ウォールデン 森の生活』第2章「どこで、なんのために生きるか」)
ソローは、テントやカヌーといったアウトドア道具を使って、しばしば旅をしていましたようです。
さて、今回のシンポジウムでは、「山とソロー」「山とエマソン」について、文学研究者たちの発表と質疑応答が繰り広げられました。
まずは、成城大学の佐藤光重先生からの研究発表からスタート。テーマは、「暗い山と栄光の山 ――『コンコード川とメリマック川の一週間』における登山と死の欲動」でした。
『コンコード川とメリマック川の一週間』は、1949年に出版されたソローの処女著作です。この本の草稿は、ソローが『ウォールデン 森の生活』で描いた湖畔生活の2年2ヶ月間に執筆されました。
本が出版される10年前、1839年の夏に、ソローは兄のジョンとともにワシントン山(アジオコチョーク山)の山頂をめざして、小舟による川旅にでかけました。『コンコード川とメリマック川の一週間』という本にまとまっていますが、この旅には2週間かかっています。
じつはこのコンコード川とメリマック川を旅している時期に、兄のジョンとソローはひとりの女性(17歳)に恋をしていました。いわゆる三角関係です。
川旅から戻ったその日に、兄はその女性に会いに行き、その後、結婚を申し込みますが、いったんOKがでたものの、結局は断られます。その数ヶ月後に、今度はソローがその女性に結婚を申し込み、最終的に断られました。
3年後、1842年に兄ジョンが破傷風で亡くなります。ソローは、哀しみとともに、3年前の求婚事件で、結果的に兄を裏切ってしまったことに、贖罪のような気持ちを抱いたのではないかといわれています。
1845年7月4日からウォールデン湖畔の小屋で「森の生活」を始め、『コンコード川とメリマック川の一週間』の原稿を書き始めますが、小さな小屋での簡素な暮らしは、哀しみを癒し、兄ジョンへの罪の意識をあがなう贖罪の試みだったのかもしれません。
ソローの処女作『コンコード川とメリマック川の一週間』
さっそく本を購入し、読んでみました。ソローは、この本の「火曜日」の章で、山頂でご来光を見たときの話を書いています。
《私はかつて雲の上の、マサチューセッツ州サドルバック山の頂上から夜明を見たことがある。たまたま今はこの濃霧では事物を十分に観察できないので、そのときの話を詳しく語らせていただきたい。》
(ヘンリー・ソロー著・山口晃訳『コンコード川とメリマック川の一週間』而立書房より引用/以下同)
ソローの登山装備は、簡素で、いまでいう日帰りハイキング程度の道具仕立てだったようです。
《道ばたでラズベリーを摘み、時々農家でパンを買い、背負ったリュックには数冊の旅行書と服の着替え、そして手に杖を持っていた。(中略)(ノース・アダムズの)村で手に入れたいくらかの米、砂糖、ブリキ製のコップをリュックに入れ、午後は山に登り始めた。頂上は海抜三千六百フィートで道のり七、八マイルである。》(前掲書)
標高は約1100m、道のりは11~12㎞ほどでした。山道を行くと、長くて広い谷の真ん中を小川が流れていて水車が回っており、ソローはそのような風景を歩く心境を、まるで《天の門へ登ろうとする巡礼者の入っていく道のように思えた》と記しています。
途中、山に住んでいる快活な奥さんと言葉を交わしたりもしながら、一歩一歩山を登っていき、《木々がついに痩せこけた黄泉の国のような様子になり始めるところ》に出て、そして日が沈みもうとしている時間帯になって、ようやく頂上に着きます。
ソローはこの登山に、十分な水さえ持参していません。山頂で喉の渇きをいやすために、水場を探すのですが、泉の水が涸れかけていたため、黄昏の中で深さ2フィート(約60㎝)の井戸を掘り、火をおこし、焚き火で米の夕食をこしらえ、その場で木を削って作ったスプーンで食べるのでした。
「板」と「石」を使ったソロー流ビバーク術
当時はもちろん、寝袋なんて便利な道具はありません。おそらく夏場だったからでしょう。毛布すら持ってきていなかったようです。では、ソローはどうやって山頂でビバークしたのでしょうか?
頂上には、ウィリアムズタウン大学の学生たちが建てた、かなり大きな展望台の建物があり、そのなかに「板」をしいて、薪をひと山集め、焚き火を整えて、その脇で眠りました。身体の上にも「板」をのせ、そのうえに「石」をのせて眠ったというから、すごい。
思わず「重くなかったんかい!」とツッコミたくなります。
《抑えに大きめの石を乗せたので、快適に眠れた。冬の夜、自分たちがしているように、体の上にのせる戸を持っていない隣人たちはどうするのかと訊ねたアイルランドの子供のことを私は思い出していた。この質問はまったく意想外なことではないと私は思う。戸があれば、たった一枚の毛布だけでもしっかり身体に押しつけてくれ、人をどれほど快適にするか、それを試みたことのない人は思いもよらないのである》(前掲書)
朝目が覚めると、ソローは、建物の上に登り、いちばん高いところに座って日の出を待ちました。展望台の部材に、ここを訪れた大学生たちの名前が刻まれているのを見やりながら、ソローはひらめきます。
《もしそれぞれの大学が山の麓に配置されるなら、天分豊かな教授陣が存在する大学にひけをとらないだろう》と。(前掲書)
山は、名門大学に劣らない、究極の「学びの場」ではないか、というのです。なぜならば、私たちは《山頂を訪れるたびに、下界で手に入れた特殊な情報を一般化し、それをもっと普遍的な基準に従わせるだろう》からです。
そう、山は、「特殊な情報」を「一般化」「普遍化」する大学なのです。山は、下界において様々な情報源から学んだ知を咀嚼し、「自らの知」として消化吸収する学び舎なのでした。
たしかに、いまの時代も、山に登ると、なんとなく、頭の整理ができたような気がします。いろいろ頭を悩ませていた仕事の雑事が、山に登ってみると、しょーもないちっぽけなことだったなぁ、と気づくことも多いですよね。要は、学校なんか行くより、山に登ったほうが頭良くなるぞってことでしょうか。
やがて、だんだんと明るくなってくる光の中で、ソローは広大な靄(もや)のひろがりの中にいることに気づきます。一晩、山頂で夜を過ごしたことで、心の中は広々としていて、下界のちまちましたことは、もはや気にならない心境になっています。
《東方がしだいに明るくなってくるにつれて、夜の間に私がそれに向けて登って行った新しい世界、たぶん私の生きる将来の大地を、それは一層明瞭にしてくれた。(中略)そして七月の朝の――そこが七月であったとして――明るい大気を私は吸い込んでいた。眼下は見渡す限り、すべての方面が百マイルにわたって、雲の波立つ国であり、雲が覆い隠す陸地の世界を、雲の表面の多様な起伏で示していた。そこは私たちが夢の中で見ることができるような、楽園のあらゆる喜びが感じられる国であった。》(前掲書)
無限に広がる雪のように白い雲海、はるか地平線には霞んだ森が大平原に張り出しており、その中にうねる霞の形から見えます。その霞の形から、そこに川があることあること、それも原始的な川の蛇行のフォルムをうかがい知ることができたのでした。
山頂で日の出を見て、雲海を目にしたときの感動を伝えるソローの文章は、150年もの時をこえて、いまの時代の山が好きな私たちの心にもすっと吸い込まれるような気がします。かくいう私も、山に登るたびに、毎回新鮮な気持ちで思うのです。山上からの光景ってやつは、まるで夢のようであり、楽園のようであり、喜びそのものだなよなぁ、と。
もっとも短い道のりで、もっとも遠くまで旅する方法
さて、この本の「火曜日」の章にある以上のような描写は、川を舟でさかのぼっているときに、靄につつまれて視界がきかなくなった際の、回想シーンです。メリマック川の上流をめざす旅は続き、いよいよ「木曜日」の章で、ワシントン山(先住民の呼称:アジオコチョーク山)に登るのですが、こちらは山頂の描写がほとんどありません。その代わり、道中の文章に、ものすごい含蓄に富む名言が出てきます。
メリマック川の上流に舟を着けて、ソローと兄ジョンは川沿いに歩いてワシントン山(アジオコチョーク山)の山頂をめざします。霧雨の降る中ですが、ソローは雨を厭いません。しめった土や松の香り、滝の音、キノコ、カエル、トウヒの樹上から垂れ下がるサルオガセのような地衣類、ツグミなどを愉しみながら歩くのは、ソローにとって贅沢な時間でした。
雨のしなやかな音に包まれながら、道中、ソローは考えるのです。かつてこの森は探検家が訪れる辺境であったけれど、いまはもう人跡未踏の地ではない。探検家の時代は終わり、地球上から、辺境は消え失せてしまった、《どこに行っても地上には、すでに人がいる》と。
しかし、とソローは、いったん提示したそのような考え方を否定するかのように、考察を進めます。
《辺境は西にも東にも、北にも南にもなく、ひとりの人間が一つの事実に向き合うところなら――それは彼の近くにあるのだが――どこにでもある》。
辺境は、2次元的な地平にではなく、3次元、4次元的な空間に、あるいは胸の中にこそあるというのです。どこであれ、ミミズのように深く潜ることができれば、私たちは辺境に荒野に至ることができるのだと。
では、ミミズのように深く潜るためには、どうすればよいのでしょうか?
《旅をするもっとも安い方法、そしてもっとも短い道のりでもっとも遠くまで旅する方法は、ひしゃく、スプーン、釣り糸、先住民の食物、塩、砂糖を持って、徒歩で行くことである。小川か池にきたら、魚を釣り、それを料理する(中略)四ペンスで農家のパンを一個買い、道の次の小川でそれを湿らし、砂糖を少し入れる。(中略)二セントで牛乳を一クォート購入し、パンか冷たくなったプディングをその中に砕いていれ、皿からスプーンで食べてもよい。(中略)このようにして私は家の中で食事をとることなしに数百マイル旅をし、都合がつけば地面の上で眠った。》(前掲書)
「歩く」ことの大切さ
「歩く」いて旅をすることが大切だとソローは考えます。なるべく少ない道具で、食料などは道中で調達しながら、「もっとも短い道のりでもっとも遠くまで」旅をすることが大切だというのです。これってまさに、バックパッキングやULハイキングの核心、いや、すべてのアウトドア的な営みの真髄ではないでしょうか。いまの登山やハイキングから失われてしまった、本質的な歩き旅の魅力が、この文章には表されているように思えるのです。
しかし、ソローはたんに旅を礼賛しているわけではありません。旅は生産的な営みではない、旅ばかりしているようなやつはだめだ、とソローはいいます。《たくさんの旅をした者の晩年は非常に哀れを誘うことを私は見てきた》と。
《本当の誠実な旅は暇つぶしではなく、死と同じように、あるいは人生行路のすべてと同様に真剣である。(中略)坐って旅している人、ずっと坐って足をぶら下げている旅行者、こうした単なる怠惰の典型のことではなく、旅が足の活力源であり、最終的には死でもある人のことを私は言っているのである。そうした旅人は路上で生まれ直し、彼にとってもっとも重要な力である自然の力から旅券を得るにちがいない。ついには彼は(中略)生きたまま皮を剥がれるという経験をするだろう。痛みがしだいに深まり、内的に治癒するかもしれない。》(前掲書)
兄を亡くしたソローにとって、歩く旅は、生きたまま皮を剥がれ、新たに生まれ変わる、まさに再生の旅でした。
以上のように『一週間』という著作は、非常に含蓄のある思索、旅名言がちりばめられた本であるのですが、肝心のワシントン山(アジオコチョーク山)の山頂の描写はありません。小川がつくり出す小道を登り、水源を越えて、《最後は標識がなくても私たちはアジオコチョークの頂上に達することができた》と、至極さらりと終わっています。
ソローの登山と「死への欲動」
ちなみにソローは、ウォールデン湖での小屋暮らしの前後にも何度も登山旅行をしていて、1946年にもメイン州のカタ-ディン山に登っています(ちなみに、前述の「市民的不服従」の主旨で投獄されたのもこの年)。いまよりもずっと登山が大変だった時代です。なぜソローは、何度も山に登ったのでしょうか?
佐藤先生は、ソローの著作や日記、ソローの友人だったナサニエル・ホーソンなどの著作を読み解きながら、この時期のソローの登山描写に、フロイトのいう「死への欲動」(タナトス)が表されているのではないかと推察していきます。
メリマック川をさかのぼって、その上流、水源地点をたどり、さらにワシントン山の山頂に向かう旅。道中の描写はあるのですが、なぜか、この山頂についての記載がいっさいありません。
しかし、別の章(「火曜日」の章)には、ほかの山の山頂の描写があります。この山旅を描く筆致、思索は、ソローが兄の死を悲しむ「死の世界への旅」のようであり、山から下りて再び生きる喜びを見いだす「再生の旅」のように読めるのです。
先生のそんな話を聞きながら、たしかに、ぼくらも山登りしているときに、そんなことを感じることがあるかもしれないという気がしてきました。山上でもやにつつまれ視界が効かないときには、心の中そのものをあるいているような気分になりますし、激しい雷雨に襲われたときなんかには、たしかに「プチ死」と「プチ再生」を感じているかもしれません。
当時20代だったソローは、兄の死後、その悲しみを克服し、生きていくために、山に登っていたと思われます。山登りは、身体的な旅であるとともに、精神的な旅でした。ソローは、山を歩くことで、咆哮する魂を鎮め、哀しみを癒やし、再び生きていくパワーを得たのでした。
荒れはてた心を癒すために、人間は山を歩くことができる。喜びも悲しみもある人生に、山という楽しみがあってよかった。そんなことを思った、佐藤先生のお話でした。
自然とは「結晶化した善」だ
つづいて、九州大学名誉教授の小野和人先生が、より詳細に「ソローの登山歴」について発表されました。前述したように、1839年8月31日から9月13日にかけての『コンコード川とメリマック川の一週間』の旅で、ソローは9月6日にワシントン山(先住民の呼び名でアジオコチョーク山)に登りました。標高は6288フィート(1917m)。
ワシントン山は、1819年、クロウフォード・パスと呼ばれるアメリカ最古のハイキング道が開かれました。頂上付近は風が強く、いまも悪天候で有名な山です。
この山を皮切りに、ソローは記録が残っているだけでも、14回の登山旅行をしています。
1842年にはリチャード・フラ-とともにワチューセット山(611m)に3泊4日で登り、山頂でご来光を見ました。
1844年の夏にソローはニューハンプシャー州のモナドノック山(965m)に登り、山頂にキャンプ泊。月明かりの中で山頂付近を散策しています。
マサチューセッツ州のグレイロック山(1064m)や、東海岸を代表するロングトレイル「アパラチアン・トレイル」の北の起点であるカタディン山(1606m)などにも登山旅行をしています。
下山時に何度も転んでリュックサックを地面にたたきつけてしまったり、頂上からはるか下に見える湖に「飛び降りてしまいそうな気分」になったり、スプルースの木を用いてキャンプの寝床を作ったものの、焚き火の火が燃え移って、あわてて水に浸した木の枝で火を消したり、荷物の運搬人が山火事を起こしてしまったり、ソローは数々の登山エピソードを記録しました。
そうしたなかには、「自然とは結晶化した善だ」というようなソロー流の名言も書き残されています。
ソローは、当時のいかなるアメリカの作家よりも山を愛しました。なぜ、それほどまでに山が好きだったのでしょうか。
小野先生は、プリンストン大学名誉教授で作家・批評家のウィリアム・ハワースを引用しながら、ソローの登山描写は、前期はロマン主義的で、後期は客観的であると述べ、ソローにとって「山」とは、天と地、聖なる世界と俗なる世界の橋渡しをする「媒介者」だったのではないかと語りました。
ソローにとって山は、生きたまま「天」に至る道であり、ソローにとっての「天」とは、宗教的な「天」ではなく、「真の人生を生きること」だったのではないか。
山は、「真の人生を生きる」ための媒介者だったのではないか。
小野先生は、そうしたソローの登山志向・感覚は、日本古来の「修験道」の感覚に近いように思う、といいます。天界と人界を結びつけ、山歩きによって法力を身につけようとする行為。修験道のその行為もまた「真の人生を生きる」ための営みなのではないかと。
なぜぼくらは、あんなにキツイ思いをしながら山に登るのか。ずっと疑問に思っていたのですが、先生の話を聞いて、腑に落ちました。
なぜ、山に登るのか?
たぶん、「真の人生を生きる」ために、登るのです。
オバマ、トランプ両大統領が愛読する詩人思想家エマソン
最後に早稲田大学の江田孝臣先生による、ソローの師匠であるエマソンの詩「モナドノック」についての研究発表がありました。
この詩は、ソローも登った山、モナドノック山(965m)に登った経験がもとになっています。山頂で、日の出を待ちながら星空を見ている心境をもとに書いた詩だと考えられます。
当時のアメリカは鉄道が開通した直後の時期。ソロー、エマソンの故郷コンコードとボストンを結ぶ鉄道が開通したのは1844年。1845年には、コンコードとモナドノック山の最寄り駅を結ぶフィッチバーグ鉄道が開通して、登山が盛んになりました。
Thousand ministrels woke within me,
‘Our music’s in the hills;’
一千人の吟遊詩人が私の中で目覚めた。
「われらの音楽は山にあり」。
(小野和人先生訳)
と、この詩ははじまります。ストーリーは、だいたい次のような内容です。
1:都市の群衆に失望して山に登った詩人エマソンがモナドロック山に呼びかけ、山を讃える。山で出会う民に、独立と高貴なものを求めるが、ちまちました卑屈な人々を見いだして失望する。その後、山の民の中に温和さ、智恵、技術、辛抱強さなど良きものを見いだす。
2:そこで、モナドロック山が、語る。何千年もの未来に、「燃えさかる琴座」が到来するのを待っているのだと。より偉大なるもの、音楽と詩の時代の到来、吟遊詩人、を待っているのだと。
3:そして山は、都会からやってきたこぎれいなサラリーマンたちに、暴力的な宇宙の運動と荒々しい自然を見せつけて、街に追い返す。
この詩の重要なところで、「琴座の一等星ヴェガ(織り姫星)が、私(山)に近づいてくる」というフレーズがあります。先生によれば、1842年にオーストリアの天文学者・化学者クリスティアン・ドップラーが近づく星は青色を帯びるという理論(ドップラー効果)を発表しており、エマソンは当時最新のこの天文理論を知っていた可能性がある(その後の研究の結果、実際にヴェガが地球に近づいていることが確かめられました)。
エマソンが考える「人間がめざすべき道」は、恒星ヴェガのような、「詩と音楽に向かう人間の発展」でした。
エマソンの最初の著作『自然』の冒頭でも、星を見ることで人は真の孤独を得ることができ、そのことの重要性が述べられています。エマソンの星好きは、山登りと深い関係があると考えられます。
オバマ前大統領やトランプ大統領も愛読しているという、エマソンの『自己信頼』はアメリカ屈指の古典的名著ですが、自己の直感を信頼し、自己を超克して発展いくべしという『自己信頼』の考え方は、山の上で星を見ることから生まれたのかもしれません。
人は山に登り、星を見ることで、俗っぽい街の喧騒や群衆から離れて、胸がすーっとするような、ほんとうに大切な感覚を取り戻すことができるのかもしれません。
※『ウォールデン 森の生活』の翻訳者・今泉吉晴先生の特別講演編につづきます!
最も速い旅人は、足で歩く旅人である--「日本ソロー学会」今泉吉晴さん特別講義に行ってきました!
【関連記事】
◎シンプルライフのバイブル。ヘンリー・ソロー『森の生活』を読みなおそう!
◎『ウォールデン森の生活』訳者・今泉吉晴さんがすすめる「自然の名著」5冊!

ヘンリー・D・ソロー著 今泉吉晴訳
『ウォールデン 森の生活』
「人は一週間に一日働けば生きていけます」という名言で知られるシンプルライフの名著。ヘンリー・D・ソローは、一八〇〇年代の半ば、ウォールデンの森の家で自然と共に二年二か月間過ごし、自然や人間への洞察に満ちた日記を記し、本書を編みました。邦訳のうち、小学館発行の動物学者・今泉吉晴氏の訳書は、山小屋歴三十年という氏の自然の側からの視点で、読みやすく瑞々しい文章に結実。文庫ではさらに注釈を加え、豊富な写真と地図とでソローの足跡を辿れます。産業化が進み始めた時代、どのようにソローが自然の中を歩き、思索を深めたのか。今も私たちに、「どう生きるか」を示唆してくれます。