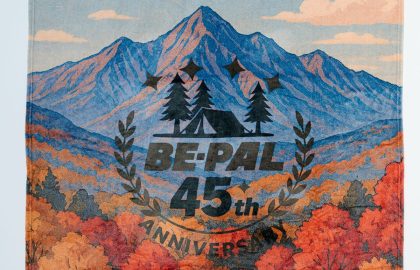- Text
低山から標高の高い山へ!違いと魅力をご紹介

登山を続けていると、北アルプスや南アルプスなど、日本を代表する標高の高い山が連なる山域への挑戦に憧れを抱く人も多いものです。360度に広がる稜線、草木も生えない岩峰の恐怖と神々しさ、山頂に至るまでに見る奥深い山の世界。挙げればキリがないほど、標高の高い山には低山とは異なる魅力があります。
憧れの高所の山に登ってみたい!でも登れるのか不安……。今回は、標高の高い山や、新しい山に挑戦したい方に向けて、低山との違いや、高山に挑む際のポイントをご紹介します。
低山と標高の高い山の違いと魅力
森林限界を越える

誰もが持つ標高の高い山のイメージのひとつに、人を寄せ付けない屹立した岩峰があります。高所では高木が育たなくなる高度(森林限界)を越えるため、岩肌が露出した山頂が連なるようになります。
ハイマツをはじめとした低木、高山植物は確認できますが、視界を遮るほどではなくなるため、森林限界を越えれば、森に囲まれた低山とは別世界の景色が広がります。これが標高の高い山の大きな魅力であり、歩いている間は絶景がずっと続くというご褒美タイムが待っています。
一方で、雨風を遮る植物がなくなるため、悪天候による影響を受けやすいです。
山に没入できる

標高の高い山は、一部のアクセスが良好な山を除き、山頂までの所要時間は低山より長いのが一般的です。麓から山頂までは日帰りで登って下山することは難しく、1泊以上かけて登頂・下山することになります。所要時間が長いということは、山頂だけでない多彩な山の世界に出会えるということ。
序盤の森林や渓谷、そこで出会う生物や、山に生きる山小屋の人々などに触れながら、ゆっくりと山の世界に没入していきます。この感覚がとても気持ちよく、山に夢中になっていく感覚は標高の高い山ならではです。
標高の高い山ならではの登山計画

目まぐるしく変わる環境、所要時間の長さは低山とは異なる高山のポイントです。初日の晴れが翌日以降も続くとは限らず、コースタイムどおりに行動できないことも珍しくありません。
日帰りが多い低山とは異なり、天気予報や現地情報はより詳細な情報を入手し、2日目以降の行動は余裕を持たせるか、移動距離を稼ぐためにハードにするかなど計画性が求められます。登山計画は慣れないと作るのが大変ですが、完成した計画はまるでひとつの作品のように美しく見えます。
標高の高い山に登るために必要なこと
体力をつける

高所を登るためには、長期間歩き続けられる体力が必要です。体力があれば、身体パフォーマンスを落とすことなく安定した状態で行動でき、怪我などの不具合を起こすリスクを減らすことができます。
低山であれば悪天候になっても、その日のうちに安全な麓に下山することも可能ですが、標高が高くなると難しくなります。標高の高い山に挑戦する際、体力に不安がある場合は、ランニングやスポーツジム、定期的な低山登山などで体力の向上に努めましょう。
また低山でトレーニングする場合は、標高の高い山に行くことを想定した装備で登ってみるのもおすすめです。
道具を見直す

標高の高い山は、前述のように低山とは環境が異なります。また宿泊を前提とすると、テントや寝袋などの必要な道具も増えていきます。荷物が増量しても安定した歩行が可能な登山靴に変えたり、新規でヘルメットを導入するなど、道具の増加に合わせて既存のアイテムを軽量なものに変更するなどの見直しを行いましょう。
必要な知識・技術を身につける

標高の高い山になると、悪天候時の対応やテントの設営などの基本的な知識や技術の習得が必要です。また、低山では体力に余裕を持って登れた方でも、高山では所要時間が長くなるため、疲れにくい歩き方などの技術を習得しておくと、当日の行動が楽になります。
登山計画を立てはじめたり、経験者に聞くと、必要な技術・知識が見えてきます。登山教室や書籍などを活用して、技術・知識を身につけておきましょう。
日帰りできる高所で挑戦してみる

先述した道具や技術・知識を準備しても、標高の高い山への挑戦は不安も大きいと思います。私の場合は、本格的な挑戦の前に、高所でも日帰りで登れる山を探したことがあります。
例えば、大弛峠から登る奥秩父の金峰山。日帰りで森林限界を越えた高所に登頂できる山で、スタート地点となる大弛峠駐車場のそばには大弛小屋があるので、日数に余裕があればテント泊の経験も可能です。こうした山で身につけた技術・知識を持って本格的に挑戦するのがおすすめです。
標高の高い山に挑戦して山の魅力を深めよう

いかがでしたか。標高の高い山は、低山とは異なる魅力が詰まっています。登頂まで遭遇する様々な出会い、長い時間を経てたどり着いた山頂などを経験することで、高所の登山を終えると登山者として大きく成長できます。ぜひ標高の高い山に登って、山の新しい魅力にぜひ触れてください。