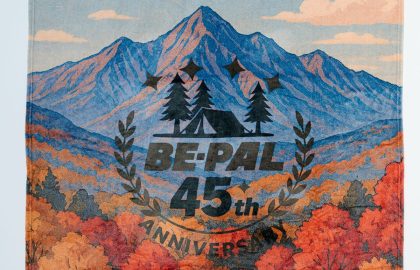夏を彩り、見る人の心を和ませ、時には特別な思い出を彩る素晴らしい役割も果たしています。
この記事では、ゆりの基本情報、月別の種類、生育時期、花言葉などを紹介します。
ゆりについて知りたい方や、これからゆりを育ててみたい方は、参考にしてみてください。
百合(ゆり)は夏に咲く代表的な花で、特に7月頃に見頃を迎えます。
6月上旬から8月下旬まで咲き続ける品種も多く、夏の花壇やガーデニングの主役として人気があります。
ゆりの基本情報
| 学名 | Lilium |
| 科・属名 | ユリ科・ユリ属 |
| 原産地 | 北半球 |
| 花の色 | 白、ピンク、黄色など |
| 草丈 | 30cm~2m(品種によって大きく異なる) |
| 英名 | Lily |
ゆりとは
ゆりはユリ科の球根植物で、白やピンク、黄色などの香りの強い大ぶりの花を咲かせます。
ゆりの花は、観賞用、食用、薬用、香水など、様々な用途に利用されています。
夏を彩り、見る人の心を和ませ、時には特別な思い出を彩る素晴らしい役割も果たしています。
ゆりの種類
北半球の温帯に130種分布し、アジア71種、北アメリカ37種、ヨーロッパ12種、ユーラシア大陸10種。そのうち日本には15種分布し、7種が日本特産種です。
多くは園芸種で、秋植え球根草として栽培されています。
植物学分類学上は、4つの系統に分けられます。
- テッポウユリ亜属(レウコリリオン系):花はテッポウユリ状のらっぱ形で、横または下向きに開く。テッポウユリ(イースターリリー)、ササユリ、オトメユリ、タモトユリ、ハカタユリ、マドンナリリー、リーガルリリー、タカサゴユリなど。
- ヤマユリ亜属(アルケリリオン系):花はさかずき状で花弁の中央部は広く、横または下向きに開く。ヤマユリ、サクユリなど。
- スカシユリ亜属(プセウドリリューム系):花は杯状で上向きに開き、花弁の先端部が広く、付け根部分は急に細くなって透ける。エゾスカシユリ、イワトユリ、スカシユリ類、ヒメユリ、フィラデルフィカム種など。
- カノコユリ亜属(マルタゴン系):花は花弁が強く反転して球状の花形となって下向きに開き、斑点が多い。カノコユリ、オニユリ、コオニユリ、タケシマユリ、クルマユリ、キカノコユリ、マルタゴン種など。
ゆりの生育時期
ゆりは寒冷地から温暖地までさまざまな気候の下に分布しますが、低温期は休眠し、暖かな季節にのみ生育、開花します。
ゆりは初心者にも育てやすい花で、鉢植えでも地植えでも気軽に育てられます。ほとんどの品種の掘り上げ、植え替えは、地上部の生育が終わる10月から11月。このころが定植の適期となります。
植え付け
植え付け適期は10~11月頃です。球根の発芽や花芽分化には低温が必要なため、秋に植え付けることで、冬の間に根をしっかり張らせることができます。
水はけと風通しの良い場所を選ぶとよいでしょう。深くまで耕された、腐植質のやや粘質の土壌が最適です。
植え替え・鉢替え
植え替え適期も、植え付け適期と同じく、地上部が枯れ始めた10~11月です。
ゆりは球根性の植物のため、葉が黄色くなって枯れ始めたら、球根を掘り上げて植え替えを行います。
鉢土が劣化しやすく、球根の成長を妨げるため、毎年の植え替えをおすすめします。
休眠期
11~3月頃は休眠期となります。生育に適さない冬などにおいて、ゆりは球根という形で休眠し、厳しい環境を乗り切ります。
ゆりの季節は夏

一般的に、ゆりの開花時期は6月上旬~8月下旬であり、7月中旬頃に見頃を迎えます。
品種によって初夏から開花するゆりは、暑い季節のフラワーギフトとしても人気があります。
主な開花期の目安は以下のように異なります。(※以下はあくまでも目安です。栽培方法、生育環境、地域などによって、開花期は前後する可能性があります)。
6月のゆり
- テッポウユリ(〜8月)
- ヒメサユリ
- スカシユリ
- カサブランカ(〜8月)
7月のゆり
- ササユリ
- ヤマユリ
8月のゆり
- オニユリ
- カノコユリ
ゆりの花言葉
ゆりは色ごとに花言葉がありますので紹介します。
※日本における花言葉を太字で示しています。
白色のゆり
花言葉は、「純潔」「無垢」「威厳」です。
美しい白色が純粋さや尊厳を連想させるため、ウェディングシーンでも人気があります。
ただし、白いユリを1本だけ贈る場合は「死者に捧げる花」という意味合いも持つため、注意が必要です。
オレンジ色のゆり
花言葉は、「愉快」「華麗」です。
友人や家族との特別な日やお祝いの際に贈ると、その場を華やかに演出してくれます。
ピンク色のゆり
花言葉は、「虚栄心」です。
海外では、「優しさ」、「温かさ」、「願望」、「繁栄」、「豊かさ」という意味も持ちます。
黄色のゆり
花言葉は、「陽気」です。
暖かみのある明るい黄色は、元気になってほしい方へのプレゼントにもおすすめです!
ゆりの由来、歴史

その豪華な花姿と強い芳香から「ユリの女王」の異名を持つ。
「ゆり(百合)」の名前の由来としては、説が以下のように分かれています。
- 花が風に揺れる様子を意味する「揺すり(ゆすり)」が転じたという説
- 球根が多くの鱗片で構成されている様子から「百枚の鱗片」を意味する「百合」という漢字が当てられた説
歴史的には、古くから日本で親しまれ、万葉集にも登場するほど古い歴史を持つ花です。
ただ、意外と知られていませんが、鑑賞目的になる前は、ゆりは食用として用いられるのが一般的でした。
江戸時代には庶民が庭先で育てるようになり、明治時代になるとゆりの花が海外で高値で取引されることを知り、栽培が盛んになりました。
栽培技術が確立された大正時代には、多くのゆりが栽培されるようになったようです。
また、海外では、純潔や威厳の象徴として、宗教的な意味合いを持つこともあります。
ゆりの季節は夏!美しさを愛でよう!

特徴や可憐な姿から、別名「オトメ(乙女)ユリ」とも呼ばれている。
ゆりは日本の気候に合っている品種が多く、初心者でも育てやすいことで知られています。
また、ゆりの花は見た目の美しさだけでなく、花言葉も素敵なことでも人気があります。
ゆりの歴史や花言葉を理解し、その美しさを愛でてみてはいかがでしょうか。