
ジオパークを舞台にした作品を執筆した、直木賞作家の伊与原 新さんに自身の経験を踏まえながら、地球の歴史を感じる旅の魅力を語ってもらった。
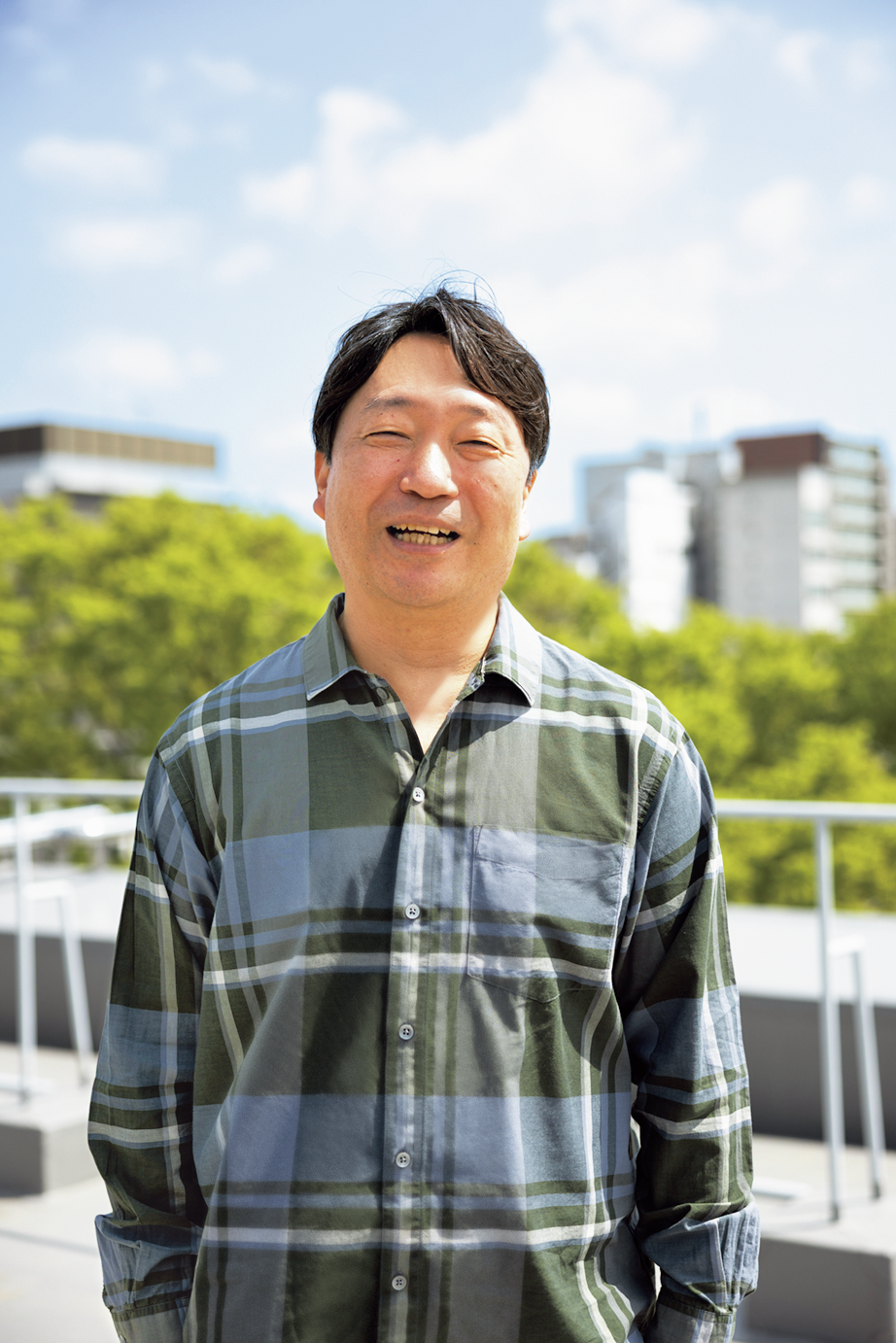
いよはら・しん 1972年大阪府生まれ。神戸大学理学部卒業後、東京大学大学院理学系研究科で地球惑星科学を専攻し、博士課程修了。2010年、『お台場アイランドベイビー』で横溝正史ミステリ大賞を受賞。
「時間のスケールに想像を巡らせてみてください」
天文、生物、地質といった科学をモチーフにミステリータッチで作品を紡ぎ続けている伊与原 新さん。直木賞受賞作『藍を継ぐ海』の中の一編、「夢化けの島」では、萩ジオパークを舞台に萩焼の土探しの謎を描いている。じつは伊与原さん、小説家になる前は地球惑星科学の博士号を持つ研究者だったのだ。
──研究者をめざしたのは?
高校の地学の先生に薦められた『新しい地球観』という本がきっかけでした。プレートテクトニクスを中心に地球の謎を解き明かしていく感じがミステリー小説のようでとてもおもしろかったんです。
──研究者時代は、立山黒部ジオパークによく行かれていたそうですね。
勤務先が富山大学だったので庭みたいなもので、とくに立山の室堂には毎年行きました。富山大の地球科学科では、1年生全員を室堂に連れていくんです。
室堂山のほうまで歩くと、氷河に削られた丸っこい大きな岩石が点々とあって、岩の表面には氷河が削った氷河擦痕が見られます。氷河が作った地形だということを念頭に置きながら見ると、「北アルプスすげえな、綺麗だな」だけじゃなく、景色はもっとおもしろくなります。
──そういった研究者時代のジオパーク体験が小説に生かされているわけですね。
科学の中でも地球科学や地質といった分野をネタに小説を書くことが多いのですが、そうしたときに日本の地方を舞台にするとほぼ確実にジオパークと関係が出てきます。4枚のプレートが接する日本の地質構造は独特で、その中でもとくに特徴的なところはだいたいジオパークになっていますので。
景色を楽しむだけではもったいない!
──一番印象に残っているジオパークはどこですか?
「夢化けの島」の取材で訪れた萩ジオパークが印象に残っています。土と焼き物の話を書こうと思ったときに、萩焼で使われる原料粘土の中になぜか見島という島でしかとれない粘土があると知り、興味を惹かれて見島に行きました。
見島は1200万年ぐらい前から溶岩が積み重なってできた火山島なのですが、島の周囲は断崖絶壁で火山のダイナミズムを感じられる素晴らしい島でした。
──伊与原博士流ジオパークの楽しみ方を教えてください。たとえば萩ジオパークでは?
ひとつは、下調べをしていくことです。見島に渡る途中に表面がぺたんと平らな島がぽつぽつあり、それが特徴的かつ美しい風景で萩ジオパークの見どころのひとつになっています。
じつはその一個一個が全部火山なのですが、海底にも同じような高まりがぽつぽつあって、そこにワカメが生え、サザエや魚がたくさん住んでいる。そういったことを知ってから行くと、「海が豊かだから昔から人間も多く住み着いたのか」といったように、ジオパークの素晴らしい景色の裏側に、地球の営みと人の営みが接している場所だということを感じられるんです。
ジオパークは景色を楽しむだけでもいいけれど、それだけではもったいないと私は思うんです。
──予習して行ったほうが、「なるほど」がたくさんあってよりおもしろくなるんですね。
もうひとつの楽しみ方は、時間のスケールに想像を巡らせること。たとえば伊豆半島ジオパーク。伊豆半島は日本列島の中でも異質で、独特な地形をしています。
もともと本州から離れた遠い海にあった火山島の群れで、100万年ぐらい前に本州にどかんとぶつかって伊豆半島になっていったからです。だから丹沢山地は、インドがぶつかってできたヒマラヤ山脈と同じような成り立ちなんです。
このように、時間のスケールに想像を巡らせてジオパークの景色を見てみてください。きっと日本列島がダイナミックに変動してきたことを感じられるはずです。

萩港から船で1時間強の見島。「一番の見どころは観音崎。溶岩がどのように溜まったのか、断面を見ることができます」(伊与原さん)
第172回 直木賞受賞作
『藍を継ぐ海』
新潮社刊

※構成/鍋田吉郎 撮影/五十嵐美弥 写真提供(見島)/日本ジオパークネットワーク https://geopark.jp/
(BE-PAL 2025年6月号より)





































