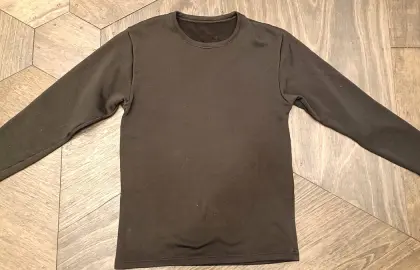新緑が眩しい季節、少し早起きをしてオオルリを探しに近くの林道に出かけてみましょう。
私が本格的に野鳥にのめり込むきっかけになったのは、多くの野鳥愛好家の御多分に洩れずカワセミとの出合いでした。漢字で翡翠(ヒスイ)と表記するカワセミは、日本の青い鳥の代表格です。
その際立つ青色の羽根から、かつては「清流の宝石」などと言われていました。その後、初めてオオルリを観た時は、カワセミのそれとはまったく異なる青色に衝撃を受けたものです。

光沢感のある随一の群青色に惹かれて
オオルリのルリは瑠璃色を表します。瑠璃とは日本の仏教の教典に出てくる金、銀、瑪瑙(めのう)といった七種の宝の一つで、古くから私たちが親しんできた青色です。オオルリの、特に背中の羽根の青は、やや紫色を帯び透明感もあわせ持つ濃い青色で、まさに「大瑠璃」の名にふさわしいものです。

まだ日が差す前の早朝のしっとりした青もいいですし、日中の強い日差しを受けてまるで濡れているような光沢を見せる群青色も魅力的です。ちなみに「瑠璃」を名前に持つ鳥は、他にルリビタキやコルリ、ルリカケスなどがいます。

ところで、オオルリもカワセミも、羽根自体には青い色素を持っていません。実は、私たちが見ているのは光の波長と同じくらいに微細な羽根の表面の構造により、光が干渉・回折・散乱した結果「発色」した青色ということになります。これを構造色と言います。分かりやすい例としてよく例えられるのがCDやDVDなどの光磁気ディスクやシャボン玉の泡の表面の色ですね。
光のあたり具合によって微妙に変化するオオルリの羽根の色は写真ではなかなか伝わらないものです。
渓谷に響き渡る囀りの声

私がオオルリと初めて出合ったのは、以前紹介した早戸川林道(神奈川県相模原市など)でした。
オオルリの姿は遠く離れた高い一本の杉の梢にありましたが、その距離を感じさせない存在感でした。その訳は囀りの鳴き声にあります。
オオルリはよく通る尻下がりの声で「ピィピィピィピィピィ……ジジッ」と鳴きます。この最後の「ジジッ」が特徴です。これはあくまで一つのパターンで、オオルリの鳴き方のバリエーションは多彩です。
同じような環境に生息するキビタキやクロツグミの声を真似ることもあります。江戸時代には美声を競わせる鳴き合わせも行われていました。古くからウグイス、コマドリとともに日本三鳴鳥の一つと呼ばれる所以です。
互いに鳴き交わすオス
囀る様子を撮影した動画を掲載しますので、耳を澄まして聞いてみてください。渓谷には複数のオオルリがいて、互いに鳴き交わしていることも分かります。こんな感じで長いときは5分も10分も囀りの美声を聞かせてくれるのです。
今年は夏鳥のオオルリに早く会いたくて、シーズン最初に林道を訪れたのが4月上旬でした。夏鳥との邂逅は冬鳥とのそれと比べ、徐々に萌黄色に染まる山間の風景と相まって期待感やワクワク感が格段に違います。ただその日はオオルリを観察するにはちょっと早過ぎたようでした。林道で同好の人とすれ違う際には、
「いました?」
「声だけですね〜」
といった挨拶代わりの言葉を交わしました。待ちきれない気持ちは、皆同じだったようです。
オオルリの見つけ方
オスは樹木の高い梢などで囀ります。鳴き声が聞こえてきたら、高い梢や声のする方向を探してみましょう。渓谷の谷底より高い場所を通る林道なら目線の高さで観察できる場合もあります。双眼鏡で梢を一つ一つ確認していくと、青いオスの姿が見つかるかもしれません。

これからの時期、オオルリは繁殖活動に入っていきます。渓流沿いの林道を歩いていると、巣材を咥えたメスに出合うことがあります。メスがそのまま動かない場合は近くで巣作りをしている可能性があるので、速やかにその場から離れましょう。

営巣中はオスの姿が意外にも至近で観察できることもあります(抱卵はメスのみが行います)。先に述べたように巣が近くにあることがあるので、そんなときは少し距離を置いて(離れて)観察しましょう。繁殖期以降は囀りの頻度は徐々に低くなっていきますが、近くで観察できるチャンスは増えます。
渓谷の歌い手は他にも
この時期は同じ環境に生息するキビタキやクロツグミにもきっと出合えるはずです。この2種もまた素晴らしい歌い手です。オオルリとは違い、キビタキは樹木の葉陰の枝に居ることが多く、クロツグミは枝で囀っているとき以外は地面で採食していることがあります。
オオルリなどが生息する初夏の林道はたくさんの蚊も居ます。虫刺され対策やヤマビル対策をしっかりして、初夏の野鳥観察を楽しみましょう。