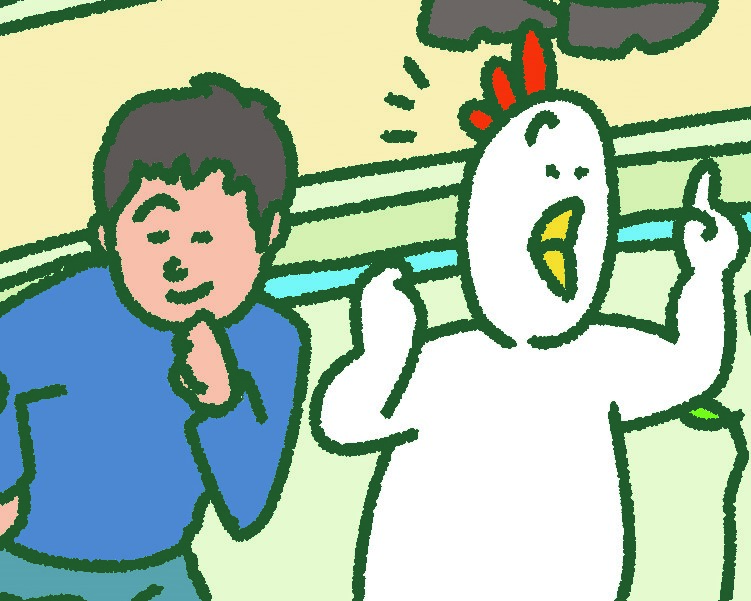CONTENTS
ホトケノザはどこで見つけられるのか
日本における分布地域と開花時期

ホトケノザは北海道を除く日本各地に生育しています。
一般的には、秋から冬にかけて芽を出し、3月前後にピンク色の花を咲かせることから春の雑草というイメージですが、秋や冬にも花を付けることがあります。
写真のホトケノザは12月に撮影したものですが、日当りの良い場所だったせいか花を咲かせていました。
生育場所

ホトケノザは街中であれば道路の脇、空き地、街路樹の下などちょっとした隙間に生えています。郊外では土手や畑など様々な場所に生育しています。
ただ、花が咲いていないとあまり目立たないので、案外、見落としてしまうかもしれません。
名前の由来と花言葉

ホトケノザ(仏の座)という名前は、外観が仏さまの座る台座に似ていることに由来しています。また、ホトケノザの花言葉は、「調和」、「輝く心」、「小さな幸せ」です。
雑草の名前は見た目から付けられることも多く、例えばイヌノフグリという雑草は、果実の形が犬の陰嚢(フグリ)に似ていることから名付けられました。
ホトケノザと比べるとちょっとかわいそうな気がします。
白花もあります!

ホトケノザはピンク色の花を咲かせる個体が圧倒的に多いのですが、白色の花を咲かせるシロバナホトケノザが存在します。ネット検索をしてみると、全国各地に生育しているので、意識して探せば案外見つかるかもしれません。
写真のシロバナホトケノザは、数年前に鹿児島で偶然見つけたものです。また、黄色い花のタンポポや、紫色の花のカラスノエンドウの中にも白花を咲かせる個体があるので、ぜひ探してみてください!
アリが種子を運ぶ

ホトケノザの種子はタンポポの綿毛のように目立たちません。このため、葉の色が黄色くなってきた頃にビニール袋に入れてよく振ると、種子を集めることができます。

ホトケノザの種子の表面は黒色で、ゴマの半分くらいの大きさです。
ホトケノザの種子には、エライオソームと呼ばれる白色の物質が付着しています。エライオソームには、アミノ酸や糖分など栄養分が含まれていることから、アリがエサとして巣に持ち帰ります。
アリ達は、エライオソームだけを食べてホトケノザの種子は捨ててしまうので、その結果、種子が遠くまで拡散し、ホトケノザがあちこちで増えていきます。エライオソームは、種子を遠くに運んでくれるアリへのお礼のようなものかもしれません。
食べても大丈夫?
ホトケノザはシソ科の雑草です。シソ科には、ハーブとして使用されているバジルやミント、薬味に使われる青じそなどがありますが、ホトケノザはそれほど香りが強くはありません。
ホトケノザに毒はありませんが、食べて美味しい雑草ではないので、観察にとどめておく方が無難ですが、花の付け根のところを舐めると、甘い蜜を味わうことができます。
ホトケノザは“名ばかり春の七草”だった!
ホトケノザと聞くと、春の七草を思い浮かべるかもしれませんが、実は春の七草の中に今回紹介しているホトケノザは入っていません。
春の七草としての位置づけ

春の七草は毎年1月7日に食べられていますが、一般的に「セリ」、「ナズナ」、「ホトケノザ」、「ゴギョウ(ハハコグサ)」、「ハコベラ(ハコベ)」、「スズナ(カブ)」、「スズシロ(ダイコン)」の7種とされています。
最近ではパック入りの七草が販売されているので、利用している方も多いと思いますが、パックに入っているホトケノザの正体はコオニタビラコという別の雑草です。
コオニタビラコってどんな雑草?

コオニタビラコは、キク科の雑草です。本州から四国、九州まで幅広く生育していて、花が咲いていないときは、タンポポにも似ています。主な生育場所は湿地なので、田んぼの周辺に多く生えています。
コオニタビラコと似ている雑草にオニタビラコがありますが、こちらは道端や空き地など市街地でも見つけることができます。
オニタビラコもコオニタビラコと同様に食べることができるので、食べ比べをしても面白いかもしれません。
ホトケノザと似ている?ヒメオドリコソウを探してみよう!
ホトケノザと同じような時期に花を咲かせるヒメオドリコソウという雑草があります。花の形や色、背丈はホトケノザとよく似ています。
ヒメオドリコソウとは?

ヒメオドリコソウはホトケノザと同じシソ科の雑草で、原産地はヨーロッパです。明治時代の中頃に日本にやってきたと考えられているので、もう100年近く経ちます。
ほぼ全国に生育しており、空き地や畑、道端などですぐに見つけることができます。秋や冬に芽を出し、春に淡いピンク色の花を咲かせます。
基本的な見分けのポイント

ホトケノザの開花時期は3月頃から始まりますが、ヒメオドリコソウはそれよりも、やや遅い開花となります。このため、ホトケノザが枯れた後でもヒメオドリコソウをよく見かけます。
また、ヒメオドリコソウの特徴は葉の色で、紫紅色をしているので遠くからでもかなり目立ちます。葉の色を見れば、ホトケノザとすぐに区別することが可能です。
ヒメオドリコソウは食べられる?
ヒメオドリコソウに毒は無いので食べることができますが、美味しいかどうかは別問題なので、好んで食べる人は少ないようです。
雑草の中にはアクや毒を含む種類も多いので、名前の分からない絶対に雑草は食べないようにしてください!
庭や畑に生えたホトケノザはどうする?
春は作物の苗を植えたり、種をまいたりする時期ですが、同時にたくさんの雑草が生えてきます。しかも、作物よりも雑草の方が早く育つのでとても厄介です。
抜かなくても大丈夫?
雑草は、作物の成長に必要な養分を奪い、大きくなると作物に光が当たらなくなってしまうため、全て除草するというのが農業の鉄則です。
ホトケノザやヒメオドリコソウは大きくなっても20センチ程度な上に、6月頃には枯れてしまうので、畑に多少残っていても大きな問題にはなりませんが、作物の害虫や病気が付着している場合があるので注意が必要です。
また、種子を付けた後に除草しても、種子が拡散してしまうため、農地の周囲では種子が付く前に除草することが大切です。
家庭菜園ではどう処理する?
抜き取ったホトケノザやヒメオドリコソウは根に土が付いたままだと再生してしまうので、土をしっかりと落とします。その後は、畑の横に置いておけば乾燥してやがて土に戻ります。
その他に、江戸時代の人々が畑から抜いた雑草を土に埋めて肥料にしていたように、生ごみなどと一緒にして堆肥にするという方法もあります。