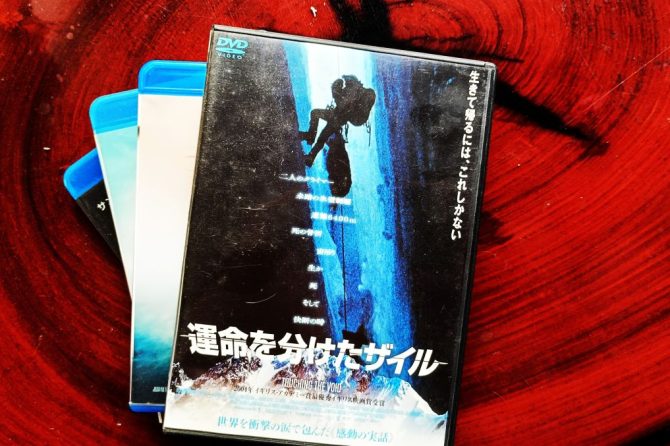- Text


【プロフィール】
1978年、千葉県出身。ディレクターとして「ガイアの夜明け」(テレビ東京)、「世界遺産」(NHK)などを制作。2013年、中国人の妻と南京市に移住。2015年に『我住在这里的理由』の番組制作を開始し、200人以上の日本に住む中国人、中国に住む日本人に密着し、動画サイトで4年間に再生回数6億回を突破。2021年、Newsweek誌「世界が尊敬する日本人100」選出。著書に「架僑 中国を第二の故郷にした日本人」(角川書店)がある。2024年『再会長江』は北京国際映画祭上映作品に選出。
「中国に来て改めて、あの戦争の傷跡はとても深いなと。あれだけ広い中国のどこに行っても必ず日本軍が侵攻した跡があり、侵略の歴史を聞かされます。それは、こんな田舎にも!? と驚くほどで、その感覚は中国に住まないとわからないかも。それほど深い傷跡を残した戦争なのに、なぜその敵国である日本人の子供を、貧しい中国の東北の人たちは養ったのだろう? いつか残留孤児の話を撮りたい、そう思っていました。僕らの年齢だと当時、ニュースでたくさん取り上げられましたが、それはあくまで日本の視点からのもの。そこで中国の視点も入れ、日中合作というカタチで描こうと思ったんです」

『名無しの子』を手掛けた竹内亮監督はいう。第二次世界大戦末期、国策によって旧満州に暮らした日本人155万人がソ連軍の侵攻から逃げ、その過程で取り残された何万人もの幼い子供。彼らを、我が子のように育てた中国の養父母たちがいた――。竹内監督は残留孤児とその家族を含む三世代、約100人を2年に渡って取材した。
最初に会ったのが、この映画の主軸となる上条真理子さんだった。残留孤児二世で日本に暮らし、自宅を開放して主に残留孤児のための老人介護施設を運営している。
「最初は20分ほどのネット番組にしようと思ったのですが、上条さんの運営する介護施設を利用するおじいちゃんが面白くて。ああこれは映画になる、利用者一人ひとりを深堀したらきっと面白くなるだろうと」
取材を申し込むと、誰もが基本的にウェルカムだったそう。それは竹内監督が、中国で多くのフォロワーを持つインフルエンサーでもあるから。取材は、信頼関係があってこそ成り立つ。長期密着となるドキュメンタリーなら尚更のこと。しかし、それが残留孤児二世を中心としたストリートギャング「怒羅権(ドラゴン)」創設者で初代総長が登場するに至り、ビックリ仰天することに。
「チャイニーズ・ドラゴンは絶対に取材したくて。狙っていたのですが、なかなか取材させてもらえそうな人は見つからない。たまたまYouTubeを開いたら、その人が出てきたんです。え、チャイニーズ・ドラゴンの総長、YouTubeを始めたの!? って(笑)。それはきっと、皆に訴えたい何かがあるということで、可能性があるなと連絡を取ると、トントン拍子に決まりました」
内心バクバクだったかもしれないが、この総長との対峙が見もの。多くのドキュメンタリーを手掛けた竹内監督ならでは手腕、相手の懐にするりと入り込み、いつの間にか心を開かせて素顔を記録することに成功している。

観客としても、この映画には忘れられないシーンがいくつもある。事実という重みに胸が締め付けられそうになったり、あまりのことに呆然としてしまったり。現場にいた監督は尚更だろう。
「映画の冒頭、黒竜江省にある日本人のお墓が出てきます。5,000人ほどの日本人が合葬されているのですが、あれを見たとき、こんなところに日本人が155万人も住んでいたのか! と。しかもそのうちの5,000人が、たったひとつのお墓に埋まっている。あまりの数の膨大さに対してハレーションを起こす、というのではありませんが、衝撃が大きく、うまく理解出来なくて。しかもそれだけの日本人が集団で渡ってきて、そこに暮らしていた中国人から土地を奪ったわけで。想像を遥かに超えるスケールで、複雑な気持ちになりました。ウチの奥さんも黒竜江省出身で。親戚のおじさんに会い、僕が日本人とわかるといきなり、日本語はしゃべれないのに、「君が代」を歌い始めたんです。きっと戦時中、強制的に覚えさせられたのでしょう。そうしたことを目の当たりにし、僕を含め、やっぱり日本人は事実を知らないんだな…と」

しかも当時の貧しい中国の養父母は、見ず知らずの、どころか敵国の子供を引き取って我が子として育て上げた。自分の身に置き換え、なぜそんなことができるのだろう? と信じられない気持ちに。
「中国人、特に東北の人は大陸気質というのか、細かいことは気にしない。なんでも来い! 助けてやる! みたいな性質があるみたいで。映画のなかに、90歳近くになった残留孤児89人が黒竜江省ハルビンへ行き、残留孤児の物語を舞台にして自らが演じて公演を行なったんです。それを観て、この人たちの母国は日本かもしれないけど、祖国は中国。産みの親より、育ての親なんだと改めて感じました。それで彼らの中では、まだ戦争は終わっていない。現在進行形の物語で、80年経ってようやく癒え始めるくらいのものなのだなと思ったんですよね」