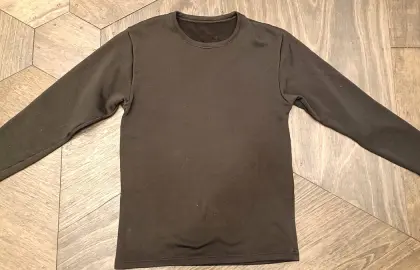ナズナの学名はCapsella bursa-pastoris
アブラナ科の越年草。高さ10~40㎝。3~6月に白い小さな花を咲かせる。果実は平たいハート形で、茎から少しはがしてくるくる回すとペンペンという音がする。
若葉を七草粥などで食用。平安時代中期の『延喜式』(927年)には宮中に供される雑菜(野菜)として掲載されている。江戸時代には陰暦4月8日にナズナを行灯につるして虫除けのまじないにした。
春の七草として知られるナズナは、ロゼットで冬越しをし、別名「ぺんぺん草」とも呼ばれる。
ナズナはアブラナ科の越年草で、日本全土に分布する。花期は3~6月ごろで、株の中心から立ち上がる茎の上部に次々と花をつけてのびる。
花は、花弁が4枚、メシベが1本、オシベが6本で、アブラナ(菜の花・ナタネ)の花と同じ造りだ。実の形が三味線のバチの形に似ており、「ぺんぺん草」とも呼ばれる。
人里や耕作地周辺に多いありふれた野草だが、とんでもなく効能の多い薬草でもある。日干ししたのちに煎じて服用すると、血液の凝固(止血作用)の促進やむくみの改善、便秘や利尿、解熱に効果があるとされ、古くから民間療法で用いられてきた。
ナズナの花期は3~6月ころだが、タネができると全草枯れてしまう。大きな株になると、3000個ものタネがこぼれ落ちる。こぼれたタネは秋のはじめごろに発芽するが、双葉がのびるのはほんの数株だ。多くのタネは夏の暑さで死んでしまうのか、ほかの草の勢力に負けてしまうのだろうか。
小さな双葉もやがて本葉をのばして、秋の終わりごろにはロゼットの形に育つ。ロゼットの形のナズナを引き抜いてみると、なんと、根はとても長く地中へのびていた。これは、やがて来る寒い冬の霜柱に浮かされて枯れてしまうのを防ぐためだ。
大きめの鉢に土を入れて、集めたナズナのタネをまいてみよう。上手に手入れをすれば、のび上がる茎先の花が夜にはしぼんでしまうのを観察できる。若芽をおひたしにしたり、自分流の楽しい野草遊びを楽しんでください。
花の形は?若芽の食べ方は?

越冬するナズナのロゼット。

花の造りはアブラナと同じだ。

実の形は三味線のバチに似ている。

このぐらいの若芽をおひたしにするとおいしい。
おくやまひさし プロフィール
画家・写真家・ナチュラリスト。
1937年、秋田県横手市生まれ。自然や植物に親しむ幼少期を過ごす。写真技術を独学で学んだのち、日本各地で撮影や自然の観察を開始。以降、イラストレーター、写真家として図鑑や写真集、書籍を数多く出版。
イラスト・写真・文 おくやまひさし
(BE-PAL 2025年6月号より)