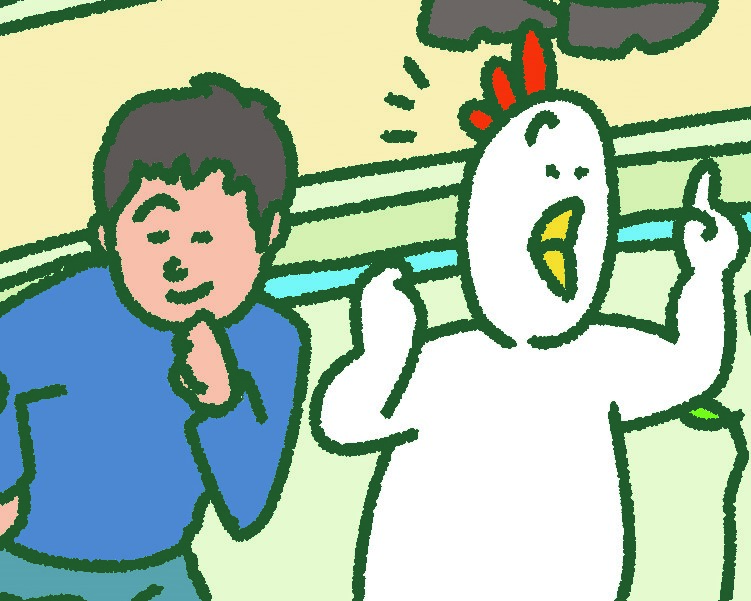CONTENTS
ずるい雑草とは?知っておきたい基礎知識
せっかく作物を植えたのに先に雑草が大きくなってしまったり、観葉植物を育てている植木鉢に雑草が生えてきた経験をしたことはありませんか?その中には、「ずるい雑草」が混ざっているかもしれません。
ずるい雑草とは?

例えば、ゴルフ場では芝生をキレイに整えるために何度も芝刈りを行うので、多くの雑草は枯れてしまいます。それでも、よく観察するとスズメノカタビラやヒメクグなどの雑草が存在しています。
このような場所では、大きな植物が育たないために光は当たるし、芝生の肥料をもらうこともできるので、人間が作り出した環境に便乗しているずるい雑草といえます。
その他にも、靴の裏やペットの毛に付着して種子を遠くまで運んでもらうずるい雑草もあります。
なぜ、ずるをするのか?
雑草は種子を昆虫に食べられたり、せっかく芽を出しても動物に踏まれたり、人に刈り取られながら育ちます。また、天気が急変して温度が下がれば一瞬で枯れてしまうことがあるので、あえてバラバラに芽を出すことで全滅を回避しています。その他、雑草は種子をあちこちに飛ばすことで、環境のよい場所を探していますが、その際には人や動物、昆虫も種の運び屋として利用してます。ずるをするのは、雑草の生き残り戦術のひとつなのです。
超ユニーク!タイプ別ずるい雑草図鑑
ここから、ずるをしている雑草を紹介していきたいと思います。そこには雑草達のたくましさ、したたかさがあります。
タイプ1・他の雑草から栄養を吸い取る寄生型
植物は普通、自分の根から水や栄養を吸収して大きくなります。ところが、雑草の中には、他の植物から栄養を吸い取って育つ寄生雑草と呼ばれるものが存在します。
たくましい雑草でさえも寄生雑草に栄養を奪われてしまうと、枯れてしまいます。
ヤセウツボ

ハマウツボ科のヤセウツボは、地中海沿岸が原産の外来雑草です。
ヤセウツボは、様々な植物に寄生して栄養を奪いながら育ちますが、マメ科の植物が好きなようです。河川敷に見つけたヤセウツボも、マメ科のアカツメクサ(赤紫色の花を咲かせるクローバーの仲間)に寄生していました。
植物といえば緑色をしているのが普通ですが、ヤセウツボは地味な茶褐色です。もちろん、枯れている訳ではなくこれが通常の状態です。ヤセウツボは、クローバー(アカツメクサやシロツメクサ)を目印に探してみてください。
ネナシカズラの仲間

以前、散歩をしていたら黄色の細いつるに覆われている一角があり、近づいて見たらその正体はネナシカズラの仲間でした。
ネナシカズラの仲間にはアメリカネナシカズラやマメダオシ(豆倒し)などがありますが、見た目がすごく似ているので、判別することはちょっと難しいです。ちなみに、マメダオシは絶滅危惧種に指定されているので、中々見つかりません。
ネナシカズラの仲間に覆われたクズの一部が枯れていましたが、一部分にとどまっていました。寄生雑草とはいえ、やはり、クズのように自分の根で栄養を吸収する雑草の方が強いのかもしれません。
タイプ2・人や動物に種子を運んでもらうコバンザメ型
雑草の種子は、タンポポの綿毛のように風に飛ばされて周囲に散らばったりもしますが、それ以外にも、人や動物、昆虫まで利用して種子を運んでもらっています。
ホトケノザ


春の七草に出てくるホトケノザ(キク科のコオニタビラコ)とは別物の、シソ科のホトケノザは種子をアリに運んでもらっています。
ホトケノザの種子には、アミノ酸や糖分を含むエライオソームと呼ばれる白色の物質が付着していますが、アリがエサとして巣に持ち帰るため、種子を遠くに拡散することができます。
アリに食べられずに残った種子は新しい場所で芽を出すことができますが、アリが変な場所に種子を運んでしまうと、写真のように空き家の室内で育つことになってしまいます。刈られることがないので安全な場所かもしれませんが、ちょっと窮屈そうです。
オオバコ

オオバコの種子は水に触れると粘液を出し、靴の裏などにくっついて広がるので、公園や砂利道によく生えています。ただ、人がよく通る場所に芽を出すと、踏まれてしまい大変そうですが、オオバコは葉が切れたりしながらも育っています。
もしかしたら、オオバコは踏まれる方が好き?‥ということは無いかもしれませんが、人によく踏まれる場所には他の雑草が入ってこないので、案外、快適なのかもしれません。
コセンダングサ

キク科のコセンダングサの種子は見るからによく刺さりやすそうな形をしています。公園を歩いたり、草刈りをした後で、服にコセンダングサの種子がたくさんくっついていた経験はありませんか?
服に刺さった種子は手で抜き取って庭先や、道路などに捨ててしまうと思いますが、これはコセンダングサの思うつぼです。捨てられた種子は、大量発生の原因になります。コセンダングサにはかわいそうですが、外に捨てずに焼却ゴミの中に入れてください。
タイプ3・休眠、抜け駆け型
雑草の種子は、熟した後に冬眠状態に入り(休眠といいます)、好みの温度や水分条件になると芽を出し始めます。この条件は雑草によって様々で、そこに雑草の生存戦略が隠されています。
タチスベリヒユ

雑草の研究をしていた頃に色々な雑草を栽培していたのですが、その中で、1番早く芽を出すのがタチスベリヒユでした。タチスベリヒユは、横にはうように育つスベリヒユという雑草の仲間で、立ち上がるように成長するのが特徴です。
雑草は、常に他の雑草と生存競争をしているので、早く芽を出せば、光や肥料分を独占できるので、とても有利です。でも、これには欠点があり、一斉に芽を出すということは、天気の急変や人に刈られることで一気に全滅するリスクがあります。
抜け駆けして芽を出しても、安心できないのが雑草の世界です。
オナモミの仲間

オナモミの仲間は、ちょっと毛虫に似たギザギザした果実を付けます。オナモミの果実の中には2粒の種子が入っていますが、そのうちの1粒は早めに芽を出し、もう1粒はゆっくり芽を出すことで発生時期をずらし、いずれかの種子が生き残ろうとしています。
どちらの種子が生き残るかは運次第ですが、真っ先に芽を出そうとするタチスベリヒユよりもずるい戦略かもしれません。
また、オナモミの仲間には、オナモミ、オオオナモミの他に果実の大きなイガオナモミがありますが、普段見かけるのはオオオナモミが圧倒的に多く、オナモミは絶滅危惧種となっています。
ずるい雑草は、じつは真面目に生きている!
今回は、雑草から養分を奪ってしまう寄生雑草、人や昆虫、動物に種子を運んでもらう雑草など、身近にあるものを上手く利用しながら拡がる、ずるい雑草達を紹介しました。
あえて、「ずるい」と表現しましたが、ある一面を見れば、賢くてしたたかな雑草像が浮かんできます。また、「ずるい」というと悪いことをしている感じですが、実は、雑草達が生き残るための知恵のようなものなので、どうか、ずるい雑草達を優しく見守ってあげてください!