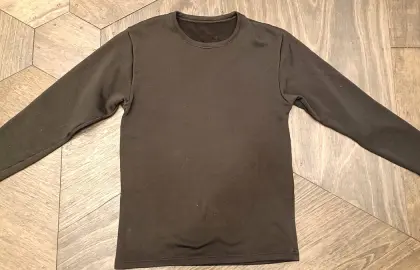ただし、山菜採りは地権者や入会権を持つ地元の人々にのみ許されている。筆者は、西目屋村のマタギの家系にある工藤光治さんの案内で深いブナ林へ入った。工藤さんが採った山菜はなんと11種類!
それでも、決して採りすぎない。自然を守りながらその恵みをいただいてきたマタギの山の作法。それは自然との共存の極意であった!

西目屋では、まだ雪の残る4月からさまざまな山菜が採り頃を迎える。最近は林道がかなり奥まで入るために、都会からたくさんの人々が山菜採りに訪れる。
しかし、都会からの来訪者は概して山菜採りのマナーがよくないという。見つけ次第、片っ端から採ってしまう。工藤光治さんは「同じ時期に同じ場所で、同じ質のものを同じ量、採れるように」という、マダギ伝来の山菜採りに関する極意を示してくださった。
決して採りすぎないのがマタギの山菜採り
ブナ林を歩きながら、次々と代表的な山菜を見つけていく。毎年、出る場所は決まっていて、その場所を荒らさないように採るのが一番大切だとおっしゃる工藤さん。
モミジガサ(しどけ)は、おひたしやあえものに適した代表的な山菜ともいえるものであるが、「10本が固まって生えているうちのせいぜい4〜5本。せっかく採るのだから、太いのを選んで採ります。細いのは来年までに栄養を蓄えます」。
ミヤマイラクサ(あいこ)は、細かい刺があるため、必ずゴム手袋をはめなければならないが、「1本だけ生えているのは採らないで、株になっているものから間引くように採ります」。

野鍛治が打ったアイゼンをつけて雪渓を行く!
工藤さんは、雪渓を登るために長靴に4本爪のアイゼンをつけた。田代にあった野鍛冶が打ったもので、30年使って1.5cmすり減ったという。紐(ほなり)は、もとは豚の毛でつくったそうだ。
ナンブアザミ(あざみ)は、採取用に木でつくった鑿(つくし:突串。道南から東北で使われてきた「農作業などに使う先のとがった棒」。『日本国語大辞典』より)で採ると、根も茎も痛めない。


つくしは持ち運ぶものではなく、その場で作るものだという。先が尖っているので、持ち運ぶうちに万が一にも転んでしまったら大怪我をするからだろう、とわたしの想像。あざみは大きくなったものは皮を剥いで、長さ3cmぐらいに折る。ただし料理する直前にしないと、あくで黒くなる。


ワサビは根を採らずフキは刃物で刈る理由とは?
ワサビ(わさび)は、「大きくなるには6〜7年かかるので、根はめったに採りません。葉と茎を採集してきざんで熱湯をかけて酢醤油で食べます」。白神では、わさびは人の通るところにあちこち移植されていて、人が通らないところではいい湧き水があってもないという。

ウワバミソウ(みず)は春先だけではなく、9月頃まで食べられる便利な山菜であるが、やはり「10本あるうちのせいぜい4〜5本、根茎を左手で押さえておいて、1節だけ採ります」。

来年の芽を残しておくためだ。そうでないと「尽(つ)けてしまう」とおっしゃる。これらの山菜はすべて手で折りとる。簡単に手折れるところまでが柔らかくておいしいが、無理に折れないところを持って帰っても、堅くて食べられない。

例外もある。この地域にはあきたぶきとよばれる大きなフキがある。重要な山菜であり、沢沿いの岩の上のものが良質であるという。
「これは茎を刃物で切ります。そうでないと根が抜けるし、中心の株を痛めてしまいます。そして切ったあとを踏みつぶしておかなければいけません。そうでないと切り口に水が溜まって株全体が腐ってしまうからです」。
マタギの文化から自然との共存の思想を知らせる活動
工藤さんは、このような知恵をお父さんから教わり、それを代々伝えていくことが自分の使命であるとおっしゃるのだ。


工藤さんはクマ狩りについても、獲物は「山神様からの授かり物」なので、無理に獲ろうとしても無駄だし、授けてくださるものを拒否してもいけないと教えてくれた。このような狩猟や採集では危険と背中合わせである。自然の恵みとして、クマも山菜もすべてが授かり物のひとつであり、それを粗末にすると「ばちがあたる」のである。
白神マタギ舎では、このように自然を敬いながら、自然の恵みをいただくというマタギ文化に接してもらうことで、自然との共存について考えながら白神の自然を満喫してもらうようなエコツアーを実施する団体として活動を続けている。