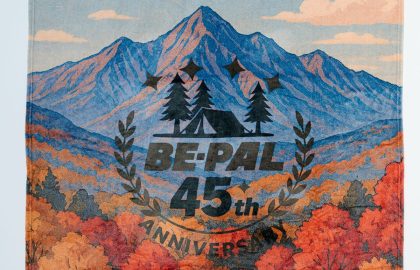【前回までのお話】イチからレッスンを受けたことで、スキーとサーフィンの相性をはじめて体感し……。
三浦豪太の朝メシ前 第11回 大阪万博とエベレスト

プロスキーヤー、冒険家 三浦豪太 (みうらごうた)
1969年神奈川県鎌倉市生まれ。祖父に三浦敬三、父に三浦雄一郎を持つ。父とともに最年少(11歳)でキリマンジャロを登頂。さまざまな海外遠征に同行し現在も続く。モーグルスキー選手として活躍し長野五輪13位、ワールドカップ5位入賞など日本モーグル界を牽引。医学博士の顔も持つ。
世紀の大挑戦!エベレストからのスキー大滑降
エベレスト・サウスコル。標高8000mに位置し、世界一高い峠とされるこの場所は〝死のにおい〟がするという。空気は地上の3分の1、平均温度はマイナス30度C、つねに強風が吹き荒れるこの地に1分1秒でも滞在するだけで体を蝕み死に近づくという。
1970年、このサウスコルから遥か2000mもの標高差を落ち込む氷の奈落=エベレストの南斜面、通称「ローツェフェース」を、父、三浦雄一郎が覗き込んでいた。
信じられないだろうが、この斜面はエベレストの標高8000m地点にありながらも太陽が当たるとその輻射熱で氷の表面が融ける。融けたのちは、吹き付ける強風と低温によって、表面は凍てつき、巨大な鱗のような氷となって固まる。
また、この斜面には頻繁に落石があり、大小さまざまな石がこの斜面にめり込んでいる。極め付きは平均斜度が45度、体感的にはほぼ垂直の斜面である。お世辞にも、理想のスキーゲレンデというにはほど遠い。
風が止んだ。
おもむろに父はスタートした。低い姿勢でまっすぐ斜面に落ちるように滑走する。通常、スキーヤーはターンの出来栄えを自慢するが、父はその対極ともいうべき直滑降=スピードが矜持だ。富士山直滑降、キロメーターランセ(最高スピードを争うレース)でさまざまなスピード記録を打ち立てた父にとって直滑降はトレードマークでもある。
増幅したスピードをコントロールするには〈パラシュートの紐を引き、背中のパラシュートが開く〉しかない。それが唯一父のスピードをコントロールする手段である。だが、このパラシュートはローツェフェースの乱雑な風に引っ張られ、父の体は右に左に翻弄され、硬い氷の斜面に足元を払われた。父は完全に体勢を失い転げ落ちる。
氷の急斜面は巨大な死の滑り台と化した。片方のスキーがはずれどこかに飛んでいく。「ローツェフェース」に出口があるとしたら、それはその下に広がる「ウェスタンクーム」といわれる氷河帯だ。その手前にはポッカリと巨大なクレバスが口を開き、父をその喉元に収めようと待ち構えている。
滑落を止められない父は中腹にある岩に激突した。この岩は今でも健在で、エベレスト登山者にとって「ローツェフェース」の目印でもある。この岩に体を持ち上げられ、再度斜面に叩きつけられる。
ここで奇跡が起きた。落下した場所には薄い雪の層があり、偶然にも残っていた片方のスキーが胸の前に入り込んだ。父はそのスキーを斜面に押し込むようにつかみ、滑落は止まった。
数秒の沈黙……。サポート隊、カメラ隊が固唾を呑んで父の様子を見守る。そして父はゆっくりと、確かにストックを振って自分の無事を知らせた。
この描写は、長編ドキュメンタリー映像としてアカデミー賞を受賞した『The Man who Skied Down Evere
st』を基に僕が再現した。これについて、現在開催中の大阪万博ヘルスケアパビリオンの大会場で話をした。
1970年と2025年の大阪万博がリンクする
「お父さんは、あの斜面を滑落しているとき、何を考えていたの」と僕が質問すると、父は
「うーん、落ちている途中から生きるのを諦めて、これで死んだら来世どうなるのかな、何に生まれ変わるのかなと考えていて、するとそっちの好奇心のほうが強くなった」というから、なんとも大胆な人である。
なぜこの話を今年の大阪万博でしていたのかというと、55年前のエベレスト・チャレンジと、その年、1970年に開催された万博と大いに関係しているからだ。
1970年にエベレストからのスキー滑降を目指した三浦隊は、まずはネパール政府へ向かった。当時、外国人によるヒマラヤ遠征登山は、地元の山麓民族との混乱を避けるため、ワンシーズンに一国一隊というルールが設けられていた。ゆえに各国の長いウェイティングリストがあった。
だが、この制度を乗り切るべく活躍したのが三浦雄一郎の登山を支えたプロジェクトマネージャーである加藤幸彦氏(通称ドンチャン)である。彼は当時日本を代表する登山家のひとりだった。1960年代前半からヒマラヤ山脈を登り始め、1964年には未踏峰のギャチュンカンの初登頂に成功。ヒマラヤからアルプス、アンデス、アリューシャン列島、チベットの山々への登頂を成功させてきた。
ビジネスマンとしても活躍し、銃弾が飛び交うベトナムの最前線で日本製の音響機器も売るという鋼鉄のハートを持っている人だ。一流の登山家でありながら一流のビジネスマン、そんなドンチャンは、父のエベレスト大滑降にロマンを感じて協力してくれた。
そこで55年前の大阪万博である。大阪万博協会は、1967年に行なわれていたモントリオール万博よりも、多くの参加国を集めたいと画策したが思うように進んでいなかった。万博協会はこれまで参加していない国のひとつ、ネパールに参加を促そうとした。その手段として(交渉する人物として)、協会は数々のヒマラヤ遠征やビジネスを通じて、ネパール外務大臣と親交があったドンチャンに白羽の矢を立てたのだった。
ドンチャンはネパールに直接飛んで交渉に行った。交渉材料は「ネパールが経済的理由で参加できないのであれば、そのパビリオン建設は万博協会が持つ」というもの。とはいえ、先方はそれで万博に参加したとしても「何を展示していいのかわからない」となった。ドンチャンはすかさず、
「とんでもない! ネパールにはほかの国が逆立ちしても敵わないものがあるではないか!」と政府関係者の前で強く宣言した。
「エベレストだよ! ネパールの展示にはエベレストの大パノラマ写真を特大パネルにして飾る。エベレストスキー滑降の様子も含めて収録した映像をもとに、ネパールの観光映画をつくりパビリオンで上映しよう!」と話した。
となれば当然、その交渉から得られるのはエベレストの遠征許可だ。こうして乗り気になったネパール政府を味方につけ、三浦隊のエベレストの登山許可が降りることになった(『絶対に死なない──最強の登山家の生き方』加藤幸彦著から一部抜粋)
当時の日本は高度経済成長期の真っ只中にいた。日本の存在感がいよいよもって世界に発信されるそのときに、大阪万博があり、未知の世界的冒険に燃える男たちがいた。
続く。

1970年5月、全長約3㎞にわたる、あまりにも有名なエベレスト滑降シーン。時速は150㎞にもなったという。

55年ぶりに開催された「大阪・関西万博」では父・雄一郎とともに、大阪ヘルスケアパビリオン・リボーンステージに登壇した。
(BE-PAL 2025年9月号より)